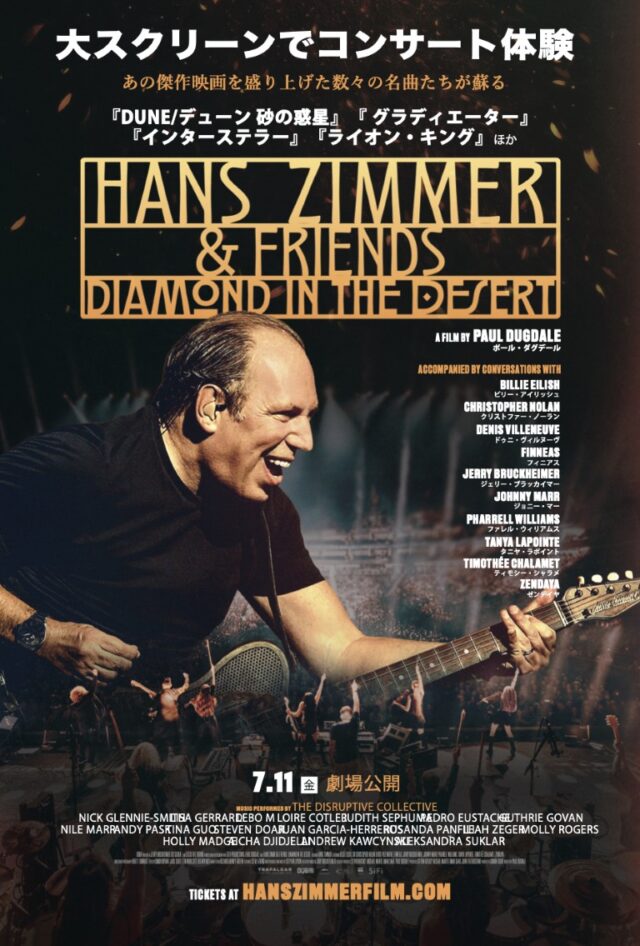時間・記憶・アイデンティティ
もとよりクリストファー・ノーランという映画作家は、手がける作品やジャンルにかかわらず、頻繁に「時間」の問題を扱ってきたフィルムメイカーだ。前述の『メメント』や『ダンケルク』だけでなく、長編デビュー作『フォロウィング』(1998)から、物語の時系列をバラバラにしていたのだ(この映画も3つの時系列から構成されていた)。
他者の夢に潜入するスパイ映画『インセプション』も、現実、夢、夢の中の夢、さらにその中の夢という、物語上の4階層に流れる時間がそれぞれずれている。近未来を舞台にした“SF大河ドラマ”である『インターステラー』(2014)でも、地球上と宇宙では時間の流れる速度が異なった。作品ごとにアプローチは異なるが、ノーランにとって「時間」は大きなテーマのひとつ。『オッペンハイマー』もその例外ではないのである。
ノーランの映画には、ほかにもいくつもの共通するテーマやモチーフがある。代表的なもののひとつが「記憶」で、これはしばしば「記録」と対立する形で描かれてきた。『メメント』は、まさに失われてゆく記憶と記録が交錯する物語。マジシャン同士(ヒュー・ジャックマン&クリスチャン・ベール!)が因縁の対決を繰り広げる『プレステージ』(2006)も、あいまいな記憶がミステリの鍵を握り、その一方で日記という記録が物語を推進する構造だった。
『オッペンハイマー』もまた、主観と客観のずれを通じて、人間の記憶のあいまいさを取り上げている。聴聞会の場で、オッペンハイマーは自らの記憶を常に問われるが、しばしば彼は何をどのように回答すべきかと躊躇する。厳しく問いかける原子力委員会のメンバーには資料という記録が渡されているが、オッペンハイマーと彼の弁護士がその記録を見ることはできないのだ。しかも、その資料がオッペンハイマーの真実を歪めていることさえある。

本作に限らず、ノーランが主人公の主観に惹きつけられてきたことを鑑みれば、こうした登場人物の主観的体験が映画のテーマやモチーフに関わってくるのは当然のことだろう。彼が手がけた作品において、ほとんどの主人公は、自らの目的に対する狂気的な執着心をもつ。その恐るべき執着心が、必ずしも周囲から理解されるとは限らない。
『メメント』では亡き妻の復讐、不眠症の刑事と殺人犯の対決を描くサスペンス『インソムニア』(2002)では刑事が考える“自らの正義”。『プレステージ』では奇術師2人がライバルを超えることに取りつかれている。『ダークナイト』3部作のバットマン/ブルース・ウェインにも、『インセプション』の産業スパイ・コブにも、『インターステラー』の元エンジニア・クーパーにも、『TENET テネット』の相棒・ニールにも、それぞれに“何を犠牲にしてもよい”と考えるほどの目的があった。
そして多かれ少なかれ、そのような執着心は彼らのアイデンティティに結びついている。自分は何者なのか、あるいは「何者でなければならない」のか。この世界でどんな役目を担い、何を守らなければいけないのか、自分が大切にしているものは何か。そうした個人的な核心が揺らぐことは、すなわち自分という人間を保証するものが揺らぐことだ。
『オッペンハイマー』で描かれたのも、そうした執着心とアイデンティティの関係だった。科学に魅了されてひたすら研究に邁進したオッペンハイマーは、その執着心ゆえに原子爆弾という脅威を人類にもたらした。いったい彼は、その先の恐ろしい未来をどれくらい想像していたのか。「天才」と言うほかない知性にあふれていた彼が、あえて目を瞑ったことは何だったのか。戦後、オッペンハイマーは自らの行いが招いた結果を知り、自分は何をしたのか、自分は何者なのかという問いに直面せざるを得なくなる。

「われは死神なり、世界の破壊者なり」。現実のオッペンハイマーは、古代インドの聖典「バガヴァッド・ギーター」の一節と自分自身を重ね合わせた。劇中でキリアン・マーフィー演じるオッペンハイマーがこの言葉を口にする時、彼をとりまく世界は大きく変化している。そのときは、むろん彼自身もまた大きな変化の渦中にあるのだ。