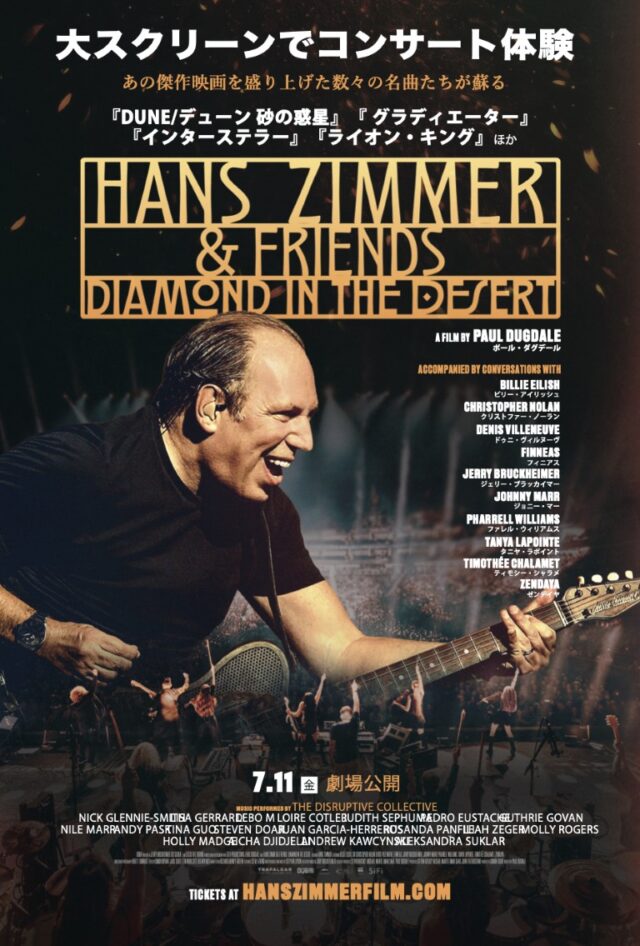クリストファー・ノーランと「語り」の冒険
クリストファー・ノーラン作品の特徴のひとつは、観客に挑戦するかのごとくトリッキーな語り口にある。出世作『メメント』(2000)の主人公は、10分間しか記憶を保持できない記憶障害を患う男・レナード。彼は最愛の妻を殺害した犯人に復讐するため、あらゆる人やモノをポラロイドカメラで撮影し、手に入れた情報をタトゥーとして肉体に刻んでいく。
物語はレナードが男を銃殺する場面から始まる。しかしこの映画は、あいまいな記憶を持つレナードの主観で、しかも時系列をどんどん逆行してゆくカラー・パートと、彼が保険調査員時代の出来事を語る、客観的かつ時系列順のモノクロ・パートが交互に展開する構成だ。あらゆる情報の断片を重ねた合わせた先で、レナードによる復讐劇の真相が明らかになる。
『オッペンハイマー』は、この『メメント』に最も近い構造をそなえている。ノーランは主人公・オッペンハイマーの視点で物語を体験する形式にこだわり、彼の主観的体験を描いたパートを「核分裂(FISSION)」と称してカラーで撮影。もうひとりの人物を軸とした客観的パートを、「核融合(FUSION)」と名付けてモノクロで撮影した。

カラーとモノクロ、主観と客観。ノーランにとっては原点回帰というべき構造を支えているのが、“もうひとりの主人公”と言うべき、アメリカ原子力委員会の委員長ルイス・ストローズ(ロバート・ダウニー・Jr.)である。原爆開発で称賛されたオッペンハイマーを、プリンストン高等研究所の所長に抜擢した人物だ。しかし1959年、彼は商務長官への任命承認をめぐる公聴会で、オッペンハイマーとの因縁や過去を追及されることになる。
野心あふれるオッペンハイマーが原爆開発に取り組む経緯、1954年のオッペンハイマーの聴聞会、そして1959年のストローズの公聴会。ノーランはこれら3つの時系列を高速でスイッチしながら、オッペンハイマーという天才の全盛期と凋落に近づいてゆく。いわゆる伝記映画としては複雑すぎるほどの語り口だ。
しかし、思えばノーランは『ダンケルク』(2017)でも、第二次世界大戦のダンケルク撤退作戦(ダイナモ作戦)を陸・海・空の3視点で、それぞれの時系列をずらしながら描いていた。『オッペンハイマー』の劇構造が、このように「時間」をあらゆるレベルで操作する、ノーラン流ストーリーテリングの発展型であることは言うまでもない。