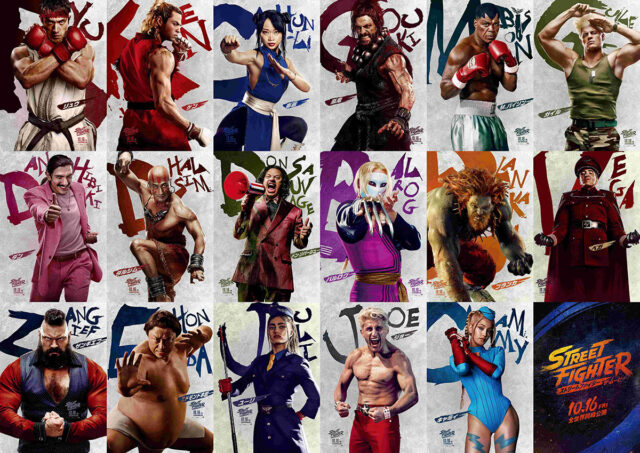映像化不可能と言われてきた東野圭吾原作のミステリー「パラレルワールド・ラブストーリー」の実写化で、『レインツリーの国』(15年)以来、4年ぶりに映画に主演した玉森裕太。メガホンを執った森義隆監督(16年『聖の青春』)に追い込まれ、現場で実際にやつれていくほどだったという彼が、作品のこと、現場のことを語ってくれた。撮影期間中の大変だった経験をも何でもないことのように淡々と語るその姿からは、いつも穏やかな彼自身の根底に秘めた芯の強さやブレなさを感じた。
物語を理解する“助けになった”2冊の台本、演じる上で大切にしたこと
――ふたつの世界を描いている本作ですが、脚本の段階から複雑な部分があったと思います。
本当にとても難しいお話で、台本も通常のものと、本作の秘密に関わる部分を明かしているものと2冊あったんです。だから撮影中も常に両方を読み込んで、今、どちらの世界を描いているのか迷わないように演じていました。やっていてわからなくなってくるので、2冊あったのは助けになりましたね。ただ、ふたつの世界があって、片方の世界では当たり前だと思っていたことが徐々に崩されていくので、自分はそういう経験はないから演じていてすごく不安になるし、強烈な恐怖を感じていました。
――複雑な物語だからこその面白さもありましたけど、玉森さんご自身はどんな点に興味を引かれましたか?
どんなに深い友情でも恋愛には勝てないのかなとか(笑)、(演じた)崇史という人間は一見、イヤなヤツに思ってしまうけど、とても純粋なんだろうなぁとか。人間のありのままの欲望という部分に面白さを感じました。崇史に共感できるところはもちろんありましたけど、自分ではマネできない考え方もありましたね。物語の設定としては異色かもしれないですけど、その中に描かれる人間の感情はリアルだと思いました。

――崇史はちょっとイヤなヤツだとおっしゃいましたが、演じる上で大切にしていたことは?
崇史の中で大切にして意識していたのは、ずっと麻由子(吉岡里帆)を好きということ。どんな状況になってもやっぱり麻由子のことがすごく好きで、その中で喜びだったり憎しみだったり、いろいろな感情が出てくるんです。この物語の中で恋愛している描写はそんなに多く描かれないですけど、「好き」という気持ちがちゃんと軸としてあるというのはすごく感じていました。
――英語や専門用語をしゃべるシーンもありましたね。
そうですね。英語のシーンは長かった(笑)。ちゃんと先生に習って、ここでは音が上がるとか下がるとか音楽の勉強みたいな感じで、ひたすら何度も何度も練習して。発音も本当に大変でしたね。専門用語は台本で読んだ時にまず意味がわからなかったので、ただ口に出すだけじゃ伝わらないだろうからちゃんと意味を調べました。現場に入る前に専門の研究者の方に会いに行って、実際どういう仕事をしているのかなど見学させてもらって勉強したことも役立ったと思います。だから家には、今、その分野の本がいっぱいあります(笑)。僕自身はそういう勉強をしてこなかったので、理系は未知の世界ですね。

――座長として意識していたことはありましたか?
作品はみんなで作るものだし、率先して声を出してこうしましょうとかあまり言わないので、僕はどの現場でも「僕についてこい」というタイプではないんです。座長を全く意識していないわけではないけど、かといって意識していることもそんなにない。現場でのキャプテンは監督で、監督の言うことが全部正しいと思っているというのもあります。監督の指示に柔軟に対応していくことが大切というか。
――そうなんですね。撮影現場を見学した時に、自分の出番がなくても楽屋に戻らず現場にずっといた姿が印象的で、その辺りも主演として意識されていたのかと思っていました。
常に現場にいるようにしようということは考えていたと思いますけど、今、思い返すとそこまで意識していたのかもあまりはっきりしないかも(笑)。とにかく全力でぶつかって、良いものを作るぞという気持ちが強かったです。