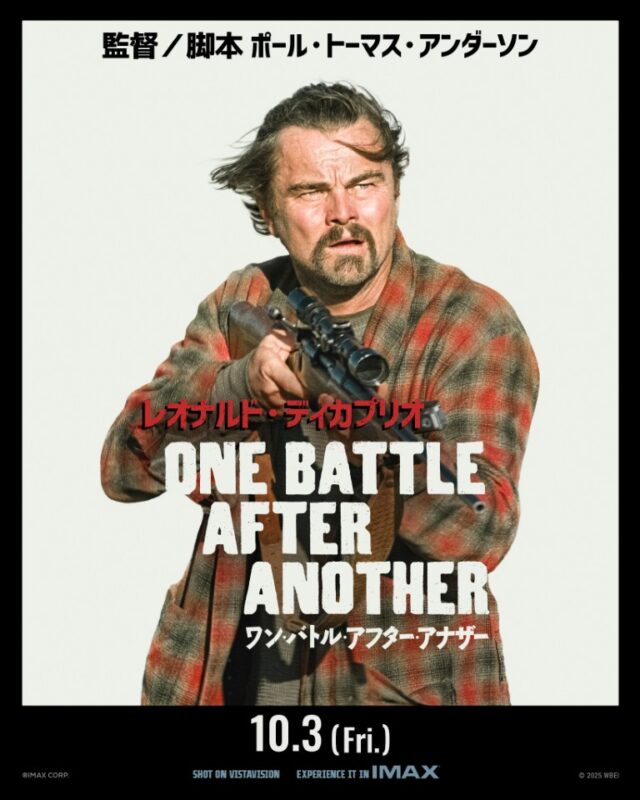愛し愛されて生きる
すべての映画は、出逢いから始まる。
ボーイ・ミーツ・ガールでも良いし、ボーイ・ミーツ・ボーイでも、ガール・ミーツ・ガールでも、ジェンダーレスな出逢いでも良い。もちろん、動物でも、外星人でも良い。
とはいえ、出逢いを描くことは単純なようで難しい。世紀を超える映画の歴史は、そのまま出逢いの歴史と言い換えて良い。したがって、もはや印象的な出逢いの場面を生み出すことは困難になったのか、ストレートな描写は避けられ、モノローグや音楽で恋したことを説明したり、出逢いの瞬間を省略してしまう映画もある。しかし、そうした見せ方はサボっているように筆者には見えてしまう。演出・撮影・照明・美術、そして演技と台詞が一体となって “出逢い”と“恋する瞬間”を具体的に見せるのが映画だと信じているからだ。
その意味で、最高の〈出逢い〉を見せてくれたのが『リコリス・ピザ』である。トイレに仕掛けられた爆竹が爆ぜるところから始まり、学校アルバムの写真撮影アルバイトをしているアラナ・ケイン(アラナ・ハイム)と、高校生のゲイリー・ヴァレンタイン(クーパー・ホフマン)が、学校の外廊下ですれ違う。
ゲイリー役のクーパー・ホフマンは父にフィリップ・シーモア・ホフマンを持ち、アラナ役のアラナ・ハイムは劇中にも姉役で登場する実姉2人と共にバンド、ハイムで活動するミュージシャンであり、2人はともに映画初出演だ。
かつて映画監督の大島渚はキャスティングについて、「一に素人、二に歌うたい、三、四がなくて五に映画スター、六、七、八、九となくて十に新劇」というテーゼをよく口にした。つまり、映画の主役なんてものはプロの俳優である必要はなく、素人(新人)や歌手が一番良く、それがいなければスターが良いのだという独自のキャスティング論である。事実、『戦場のメリークリスマス』の坂本龍一をはじめ、大島映画では、素人や歌手が主役を演じることが少なくなかったが、本作もまさに素人と歌手の組み合わせによって、得難い瑞々しさを獲得している。

冒頭に記した2人の〈出逢い〉をもう少し見てみよう。外廊下で出逢った瞬間、ゲイリーはアラナに魅せられる。そして彼女へ猛烈にアタックする。饒舌に自分のことを――子役として活動し、こんな作品に出ていると早口にまくしたてて興味を引こうとするが、アラナは相手にしない。25歳の彼女から見れば、15歳のゲイリーは子どもでしかない。しかし、廊下から体育館に入って受付を済ませ、イヤーブックの撮影のために仕切られた一角に腰掛け、カメラを前にしてもゲイリーは絶え間なくアラナに思いを伝え、遂に食事へ誘い出すことに成功する。
この長いシークエンスを観ていれば、誰もがアラナに魅せられてしまうだろう。軽薄に声をかけてきた少年への拒絶と警戒を経て打ち解け、やがて、まんざらでもない気持ちになる彼女の心情を見事に映し出すからだ。体育館で写真撮影を終えたあと、その日のディナーを約束して別れた2人を、キャメラは画面奥の扉に向かって歩くゲイリーの後ろ姿を捉えつつ、手前に向かって歩くアラナの全身をフレームに収めながらトラックバックする。そのときの彼女のさりげない表情、足取りは、他人から好きになられたことへの喜びをさりげなく漂わせて素晴らしい。
こんな繊細な描写が冒頭から登場するのだから、このあとの2時間強が、極上の映画体験をもたらしてくれると予感する観客は多いに違いない。実際、アラナとゲイリーは、映画が終わりを告げるまで何度となく出逢いなおし、そのたびに観客は冒頭以上の〈出逢い〉を目にすることになる。