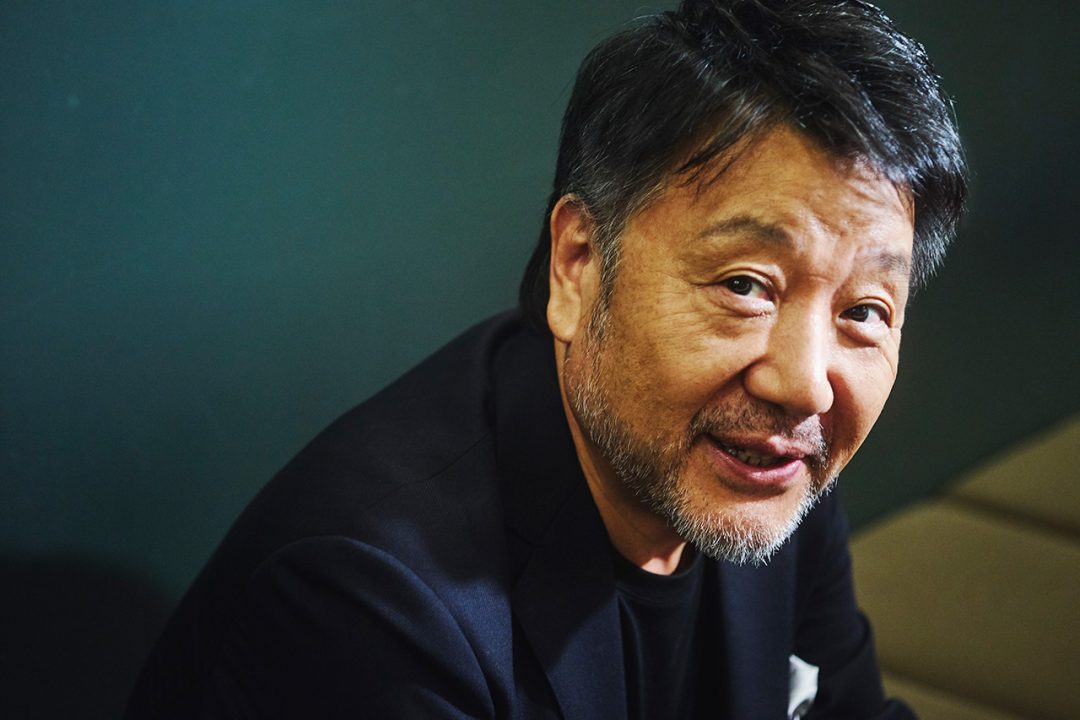『関ヶ原』はア・ボーイ・ミーツ・ア・ガールの物語
──これまでの歴史ドラマでは、石田三成=融通の利かない文官というイメージで描かれることが多かったのですが、『関ヶ原』では徹底したリアリストである徳川家康とは対照的に最後まで自分の理想を貫こうという青臭い若者となっていますね。
融通が利かない人だったことは事実のようです。ただ領民たちから愛され、武術や馬術にも優れていた人物でした。そんな三成に岡田准一さんが大変な集中力で成り切ってみせ、乗馬シーンなどもすべて吹替えなしで自分で演じてみせています。現実主義者の家康も僕は嫌いではありません。家康は権謀術数を得意にしていましたが、映画監督という仕事をやる上でもそれは必要なものです。僕も家康と同郷の静岡出身なこともあり、親しみも感じます。僕の中には三成が7、家康が3の割合でいますね(笑)。僕が嫌いなのは豊臣秀吉。若い木下藤吉郎の頃は太陽のように輝いていたと司馬先生も書いていますが、権力を手にしてからの秀吉はどんどん下品になっていったからです。

──『関ヶ原』で重要なキーパーソンとなるのは、亡くなった豊臣秀吉の親族ながら西軍を裏切ることになる小早川秀秋(東出昌大)。従来は頭の弱い、愚者のイメージが強かった秀秋を、本作ではメインキャストとしてクロースアップしていますね。
小早川秀秋に関しては25年前から、通説とは異なるキャラクターを考えていました。小早川秀秋は東軍が勝利した最大の功労者にも関わらず、マイナスイメージでしか語られてこなかった。これは多分、石田三成もそうですが、小早川秀秋を貶める風説を徳川方が流したんだと僕は思っています。今回の映画では、秀秋は家康によって長い時間を掛けて取り込まれてしまった悲劇的キャラクターとして描いています。三成と秀秋の間に確執があったのは事実のようです。秀秋にとって家族同然の存在だった豊臣秀次が理不尽な理由から豊臣秀吉から切腹を命じられ、秀次の身内も全員処刑されています。処刑されるまで秀次の身内を預かっていたのが秀秋で、三条河原での処刑を秀吉に命じられて行なったのが奉行職だった三成。今回の映画では、三条河原を様々なドラマの起点としています。三条河原で三成は初芽(有村架純)と初めて出会い、また映画の最後に再会を果たすことになります。そして、三成の片腕となる島左近(平岳大)とも出会う。この映画はア・ボーイ・ミーツ・ア・ガールの物語でもあり、ア・ボーイ・ミーツ・ア・マンの物語でもあるんです。

──「三成には過ぎたものが2つある。佐和山城と島左近」と当時謳われた勇壮な侍大将・島左近も『関ヶ原』を語る上で外せません。
島左近がどのようにして三成の家臣になったのかは、よく分かっていないんです。原作でも三成は一晩じっくり話し合って家臣にしたとありますが、具体的なことには触れていません。小説はそれでもいいんですが、映画はキーワードにきっちり触れないといけない。三成はそれまで誰にも話したことのない心情を初めて左近に吐露することで、左近は自分の生涯を三成に賭けることを決意します。このシーンを思いついたことでようやく脚本がまとまることができましたね。

──決戦シーンで左近が石垣ならぬ人垣を築いて、東軍に最期の抵抗を試みる場面は戦う男たちの異様さを感じさせます。
僕が子どもの頃に観たフリッツ・ラング監督の「ニーベルンゲン ジークフリード」(24年)に騎士団が玉砕するシーンがあったことが、とても印象に残っていたんです。それで「ニーベルンゲン」を見直したんですが、僕が記憶していたシーンはありませんでした(笑)。どうも別の映画だったようですが、戦う男たちの潔さを描いたシーンはどうしてもやりたかった。あの人垣は導入シーンに映し出される「五百羅漢」とリンクさせたものです。三成は戦場で死ぬことを良しとせず逃げ落ち、でも左近たちはここを自分の死に場所と定める。三成と左近との対照的な生き方を描いています。このシーンはスクリーンでぜひ観てほしいので、予告編には入れないようにしました。今回は合戦シーンに一日につきマックスで400人をエキストラとして用意しました。僕が出演したハリウッド大作「ラストサムライ」(03年)のときは500人を動員していましたが、実はあのときの鎧武者は半分だけだったんです。鎧兜を一人ひとり準備するのに非常に時間が掛かり、今回の400人が限界でしたね。馬も今の日本で準備できるのは1日30頭が限度でした。足りない分はCGで増やすことで成立させたんです。今の時代だからこそ描くことができた合戦シーンでした。