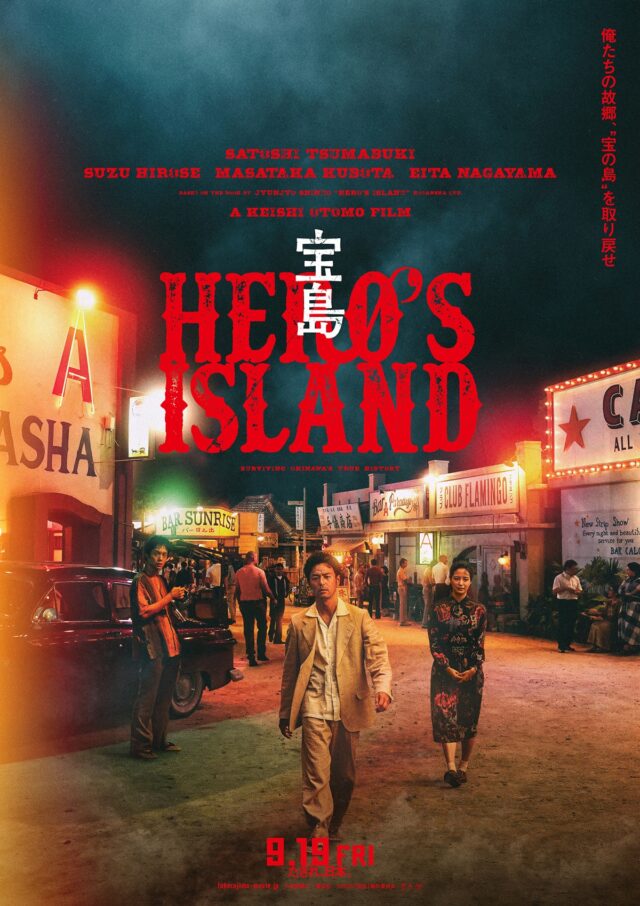ミニチェアの家の窓から何が見えるか?
――映画『Red』では恋愛シーンだけでなく、主婦だった塔子が鞍田に紹介された新しい職場で働く姿も同等の比重で描いています。中でも塔子と鞍田がミニチュアの“理想の家”を夢中になって作るシーンはとても印象的です。
“生き方の映画”にしたいと考えた時点で仕事をきちんと描くのは必要だと思いました。どう生きたいかということは、何をしたくて、何を愛したいのか、何を見たいのかを描かなくてはいけないかなと。それで原作とは設定を変えて、塔子は設計事務所で働くことにしたんです。その家で暮らす人が何を眺めていたいのかということは、家を設計するうえでの基本です。塔子は夫の真(間宮祥太朗)たち家族と暮らす家には、自分の居場所がない。鞍田も秘密を抱えて一人で暮らしている。そんな孤独な二人の居場所はどこなんだということを、視覚的に見せたかったんです。

――鞍田が設計したミニチュアハウスの小さな窓から何が見えるのかを、塔子は懸命に覗こうとする。せつないシーンです。
あのシーンの塔子の心情が、うまく伝わってくれていると嬉しいです。恋人という一番近い他者に出会った時、最初はお互いを見つめ合っていたいという気持ちが強いと思うんですが、やがて二人で何を見たいのかに変わっていくと私は思うんです。塔子の夫・真は塔子と一緒に暮らしているのに、同じものを見ることができずにいる。すき焼きを一緒に食べていても、片方はお肉を見ていて、もう片方は相手の顔を見ている。お互いにまるで違うものを見ている、ネジレの関係です。夏目漱石が「I Love You」を「月がきれいですね」と訳したと聞いていますが、それって同じものを眺めている人同士は愛情に近いものを感じるからだと思うんです。二人で同じものを見つめること=共有できることが愛にも繋がるんじゃないでしょうか。
――ミニチュアの“理想の家”とは違って、真の家には窓がありませんね。
そうなんです。国分寺に実際にあるお家をお借りして撮影させていただいたんですが、美術スタッフが庭に面した大きな窓を塞いでくれましたし、撮影としても意図的に窓が映らない閉塞感を強調するアングルにしてくれています。塔子にとっては、いくら広い家でも息苦しく、居心地のよくない空間に意図的にしています。

“Red”を象徴したベッドシーン
――原作ではタイトル『Red』の意味は説明されていませんが、映画では吹雪の中を舞う赤い布が流されていくシーンが象徴的に描かれています。
トラックの荷台から荷物がはみ出した際に付ける警告用の赤い旗です。塔子が真に電話をしている時に運命的に飛んで流れてくる。塔子はこれからどこへ向かうのかを予感させるものです。赤色って、いろんな意味があると思うんです。警戒を促す色でもあり、情熱を示す色でもあり、火ならば焼き尽くすものでもあり温めてくれるものでもあり、落ちた血ならば死、体内で流れる血なら生きていることを象徴する色でしょうね。太陽とするならば、暗闇に光りを与えてくれるものでもあります。

――塔子と鞍田が愛し合うシーンで、夏帆さんの耳や目元が紅色に染まっていくシーンも、とても印象的です。
ベッドシーンの撮影は、気分が高揚し、体温が上がっている様子まで伝わらないとリアルではないと思っていたので、そこはぜひ撮りたかったんです。一連のシーンはカメラをカットせずに、ずっと回し続けて撮りました。感情に火がついて気持ちが盛り上がり、体温が上がっていくというプロセスを踏まないと、肌は紅潮しないんです。夏帆さんの肌を紅潮させることは重要でした。それまで人形のように生きていた塔子が、自分の尺度を持つことで血の通った人間に変化していく様子を流れで見せたかったんです。夏帆さんの肌が紅潮しているのは、メイクでも照明のせいでもありません。夏帆さんだけじゃなくて、妻夫木さんの耳も赤くなっています。本当に二人とも体温が上がっていたんです。
――最後のベッドシーンは、印象的でした。
夏帆さんも妻夫木さんも、すごい集中力で演じてくれました。あのシーンを撮り終わった後、15分くらい夏帆さんが動くことができなくて、妻夫木さんがずっと背中をさすっていたんです。その中には、監督である私も無神経には入っていけず、しばらくそっとしておきました。そのくらいせつなく内容の濃いシーンになっていると思います。