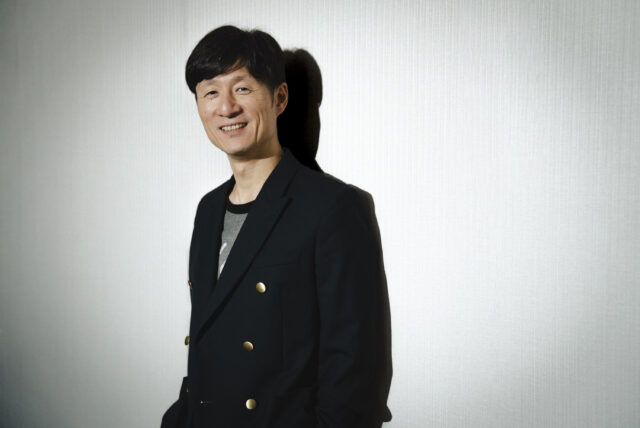思い通りにならない自然の風景を前に、生きることの意味を問う
池ノ辺 この映画は、お話自体が1年間のことですから、その撮影で1年、準備も含めるとかなりの時間をかけたんじゃないですか?
中江 撮影が1年半で、その8か月くらい前に、まず畑を耕すというところから始めました。
池ノ辺 監督が自ら耕したんですか?
中江 耕しましたよ、少しは。主にはスタッフがやりましたけど(笑)。
池ノ辺 あの古民家も素敵なところでしたね。どうやって見つけたんですか?
中江 あれも本当に運なんです。最初に行ったロケハン地で見つけました。とにかく雪がないとダメというのがありましたから、その雪の具合なども確認したくて冬に探しに行きました。
長野県の中で、茅葺の家がある廃村のことを聞いて、除雪していない中を膝まで雪に埋もれながら3、40分歩いて辿り着いたのがあの古民家でした。辿り着いた時に、それまで曇っていたのがちょうど雲が切れて陽が差してきたんです。晴れて明るくなったところで家の向こう側に北アルプスがダーンと見えました。

その時に、自分の中でのツトム像も、はっきりと見えたんです。彼は流行作家としてこれまでやってきて、いろんなことが自分の思い通りにできる。そういう人脈もお金もある。だからこそ、自分の思惑でもどうにもならない、動かせない、そういうもの、そういう風景を見ていたくてここに住んだんじゃないだろうか。自然は自分の思い通りにはならないですからね。
そしてそこで、自分の小ささとか一人で生きることの意味を問い続け、そこで見出したいと思ったんじゃないかと感じたんです。ですから、あの家の中で、一つだけ、その山々が見渡せるように大きな窓を作ってほしいと美術担当に伝えました。そしてツトムはたいていその窓辺にいるような設定にしたんです。
池ノ辺 台所や囲炉裏も雰囲気があって、素敵な場所でしたね。監督が耕したという畑の感じも良かった。
中江 あの畑のある所はもともと熊笹がびっしり生えている原野だったんです。そこを開墾して石を退けて耕して、種を蒔いて野菜を育てるということをやりました。
池ノ辺 料理も器も素晴らしいもので、でもそんな中で、人を愛し生きているからこその切なさも感じました。それはツトムもわかってるように思えたんですが。
中江 最初はツトムもおそらくわかっていなかったんじゃないかと思います。それが、あの山の生活をしていく中で、少しずつわかってくるものがあったんじゃないか。自分はそう簡単には死なないと思ってたけれど、そうじゃない、人は死ぬ、自分はどこかで必ず死ぬんだとわかる。でも死を前提にすることで、逆に日々の物事が大切になり豊かなものにみえてくる。そうツトムも思い始めたんじゃないでしょうか。