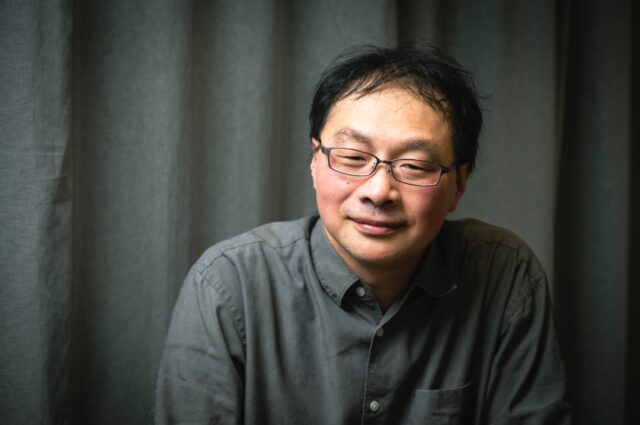映画はそこにあったかもしれない時間を描く
池ノ辺 2人の関係性が濃密に描かれているだけに、すみれが突然いなくなってしまうと、残された真奈の喪失感が痛すぎるほど伝わってきました。
中川 20代前半ですごく大事な人を失うというのは、これはもう全く比較できるような体験じゃないのは分かっているんですけれど、戦争体験はまさにそうですよね。自分の祖父が96歳なんですが、祖父の世代は、若い頃に戦争で友人を亡くす体験が沢山あったと思います。そのことに対して、自分たちの世代は幸せなんだけど、一方で生ぬるい中で生きているという感じがずっとあったんです。それで僕が大学に入って出逢った友人が死んだ時、これからずっと一緒に生きていくはずだった存在が、突然寸断される感覚に、意味合いやニュアンスはだいぶ違うとは思いますが、戦争を体験した祖父のことを思い出したんですね。
池ノ辺 突然大事な人がいなくなるってことは、つい最近までは自然災害とか、戦争とは別なものが私たちの前に起こっていましたが、今はまた戦争によって大事な人を失う可能性が出てきましたよね。監督にとっては友人の死を思い返しながら、この映画を撮っていったわけですか。
中川 友人と最後に話した会話の中で、「いや、お前はどうせ死ねないよ」みたいなことを言われたんですよね。その時は「どうせお前は死ねないでしょ」みたいなネガティブなニュアンスで受け取っていたんですけど、今にして思うと、映画を撮っていて辛いことがあると、その言葉は、むしろ励みの言葉なんですね。しぶとさとか図々しさとかを肯定されたような気持ちになれるというか。言葉の意味合いが、時間を経ることで捉え方が変わる。

池ノ辺 時間が過ぎて、いろんな経験を積み重ねてきたことで、同じ言葉にも違う意味で捉えることが出来るようになったというわけですか。
中川 そういう感じって、映画の中の真奈とすみれで言ったら、「本当は真奈は強い人だと思うよ」みたいなことを言うのとか、実はその源流に、僕の友人の言葉があるのかなという気がしますね。
池ノ辺 2人が過ごした時間、すみれがいなくなってからの時間が、すごく重みを感じました。
中川 映画というのは、やっぱりそこにあったかもしれない時間を描くもの。真奈とすみれも、一緒に同じ時間を過ごしていたように見えて、違う世界の側面を見ていたわけですね。2人の関係が分かれても、その一緒に過ごした時間は残っているということをやりたかったんですね。
池ノ辺 時間を記録するという意味では、原作になかったビデオカメラを映画で使ったのも、すごく効果的でしたね。
中川 そうですね。世界をどういう風に見ているかということを視覚的に表現するには、ビデオカメラって非常にいいわけです。終わってしまう瞬間を切り取っていくものでもあるから。