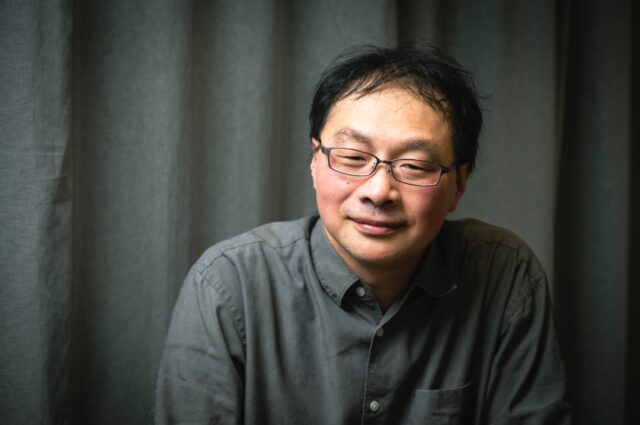「男女雇用機会均等法」の時代――ドラマからドキュメンタリーへ
池ノ辺 そして最初に入った映像の会社がドラマ制作で有名なテレパックさんですね。
信友 大学の頃に向田邦子さんが好きで、ドラマにも興味があったんです。私が入った年は、男女雇用機会均等法が施行された年だったんですが、まだ映像業界では、女性はアシスタント・プロデューサー(AP)からプロデューサーになるっていう道しかなくて。それで、転職する時にいろいろプロダクションを探すと、テレパックっていう会社は女性プロデューサーが活躍していたんです。石井ふく子さん、あと武敬子さんといって、後に『男女7人夏物語』をやった人がテレパックにいて。私もああいう風になりたいなと思って入ったんです。
池ノ辺 ただ、ドラマのプロデューサーからドキュメンタリー監督への道のりは、同じ映像の世界でも遠い気がするんですが、どうやって移ったんですか?
信友 テレパックに入社して2年後に、ドキュメンタリーの企画募集があったんです。ドラマの会社だから、ドキュメンタリーをやってる人はいないんですよ。だけど若いから、やっぱり認めてもらいたい自己承認欲求みたいなのがすごいあって、企画を出したんです。そうしたら通って。
池ノ辺 どんな内容ですか?
信友 「日本人はなぜ万歳をするのか?」というものでした。でも、会社では「誰がやるんだ?」ってことになって。「じゃあ、もう信友がやれ」みたいな感じで、プロデューサーをやったのが最初です。
池ノ辺 そこでドキュメンタリーと出会ったわけですね。ドラマと比べてどうでした?
信友 やっぱりドラマって大所帯だから、自分のできることってすごく限られているんです。特にAPって潤滑油というか、現場をうまく回すためにいるような感じ。だから、自分のアイデアが反映されるってことは少なくて、それよりも女優さんの機嫌を取るとか、弁当が足りてるか、ロケ現場の人に迷惑かけてないかとか、そういう上手くいくためのことばっかり考えてました。逆にドキュメンタリーは動く人たちも少なくて、私のアイデアもすごく採用されて。思い通りのものができていくっていう快感がすごくありました。それにハマっちゃったんですよ。

池ノ辺 それで数年後にはテレパックをお辞めになって、ドキュメンタリーにのめり込んでいったわけですね。私と監督とは年齢も近いので、同じ様な経験をされているかもしれませんが、映像業界は男性社会だから、大変だったんじゃないですか。
信友 体を壊すぐらいの勢いで仕事をしないと認められなかった時代でした。だから、私は体を壊して乳がんになったんですよ。好きな仕事だったから大変だとは思わなかったんですが、体は大変だったんでしょうね。
池ノ辺 私もそうでした。寝なかったし、帰らなかった。結婚していても週末しか帰らなかったですから。
信友 パートナーがそれを許してくれたんですね。
池ノ辺 だから、6年しか続かなかった(笑)。あの頃は本当に女性なんてって言われる時代でしたからね。でも、昔も今もやったもん勝ちで、作ったものを世の中に出して、それが素晴らしかったら次のチャンスが来ますからね。
信友 そう思います。自分の企画を出して良かったら、絶対次があるって言いたいです。この世界では、可愛い美人さんが最初に仕事をもらったりするんですよ(笑)。でも、出来たものが良くなかったら、やっぱり次は来ないんですよね。だから下駄を履かせてもらっていない私が作ったものでも内容が良かったら、次は絶対こっちに来るって自分に言い聞かせてたし、後輩にもそう言ってました。それである程度作品の本数を重ねていくうちに、もう男、女って言われなくなりました。