
人間の心の闇に迫る純文学性と読者を夢中にさせる巧みなミステリー性を兼ね備えた中村文則の小説は、若い世代を中心に熱烈な支持を集めている。中でも衝撃的な結末が用意されている『去年の冬、きみと別れ』(幻冬舎文庫)は映像化不可能とされてきた人気作。この難しいハードルに挑戦したのが瀧本智行監督だ。これまでにも映画化は困難と思われた『脳男』(13年)や『グラスホッパー』(15年)の映画化に成功している。文章表現の限界、映像表現の限界にそれぞれ向き合う二人のクリエイターが、『冬きみ』映画化の舞台裏を語った。
『冬きみ』の小説と映画は「兄弟みたいな関係」
──映像化不可能と言われてきた『去年の冬、きみと別れ』ですが、瀧本監督の手によって明快なサスペンスエンターテイメント作として映画化されました。生みの親である中村さんの感想から教えてください。
中村 映画化のお話が最初に来た時は、「どうやって映画化するんだろう?」というのが正直な気持ちでした。あの小説をそのまま映画化することは絶対に不可能でしたから。気になって脚本を読ませてもらったところ、「そうか、この手があったか」と(笑)。原作の核となる部分は変えずに、でも映画としての面白さを最大限に活かした、まさしく映画ならではのものになったなと。これが僕の感想ですね。映画化するのは難しい小説でしたが、逆にこの映画を小説にするのも難しい。そういう意味でも、『去年の冬、きみと別れ』の小説と映画は兄弟みたいな関係だと思います。小説を映画化する上で面白い、理想的な形でしょうね。
瀧本 嬉しい言葉です(笑)。初号試写で中村さんに観てもらったんですが、「中村さんが来るよ」と聞いて、初号試写の前夜は眠れなかったんです。中村さんが怒って、途中で退席したらどうしようと心配になって。映画監督って、そんなことばっかり考えるんですよ(笑)。初号試写は、監督にとっては死刑宣告が待っている裁判に出頭するような心境なんです。だから、試写が終わって、中村さんが「良かったですよ」と声を掛けてくれた時は、「やっと自分の仕事が終わったな」とホッとしました。
中村 とんでもございません(笑)。脚本を読んだ時は、「これを演じる役者さんは大変だ、そして映画として構築する監督はものすごい大変だ」と思ったんです。でも、瀧本監督とは以前お会いしたこともあり、瀧本監督が撮った作品は拝見させていただいていたので、その点は安心していました。実際、完成した映画は素晴しいですしね。
瀧本 いやいや。
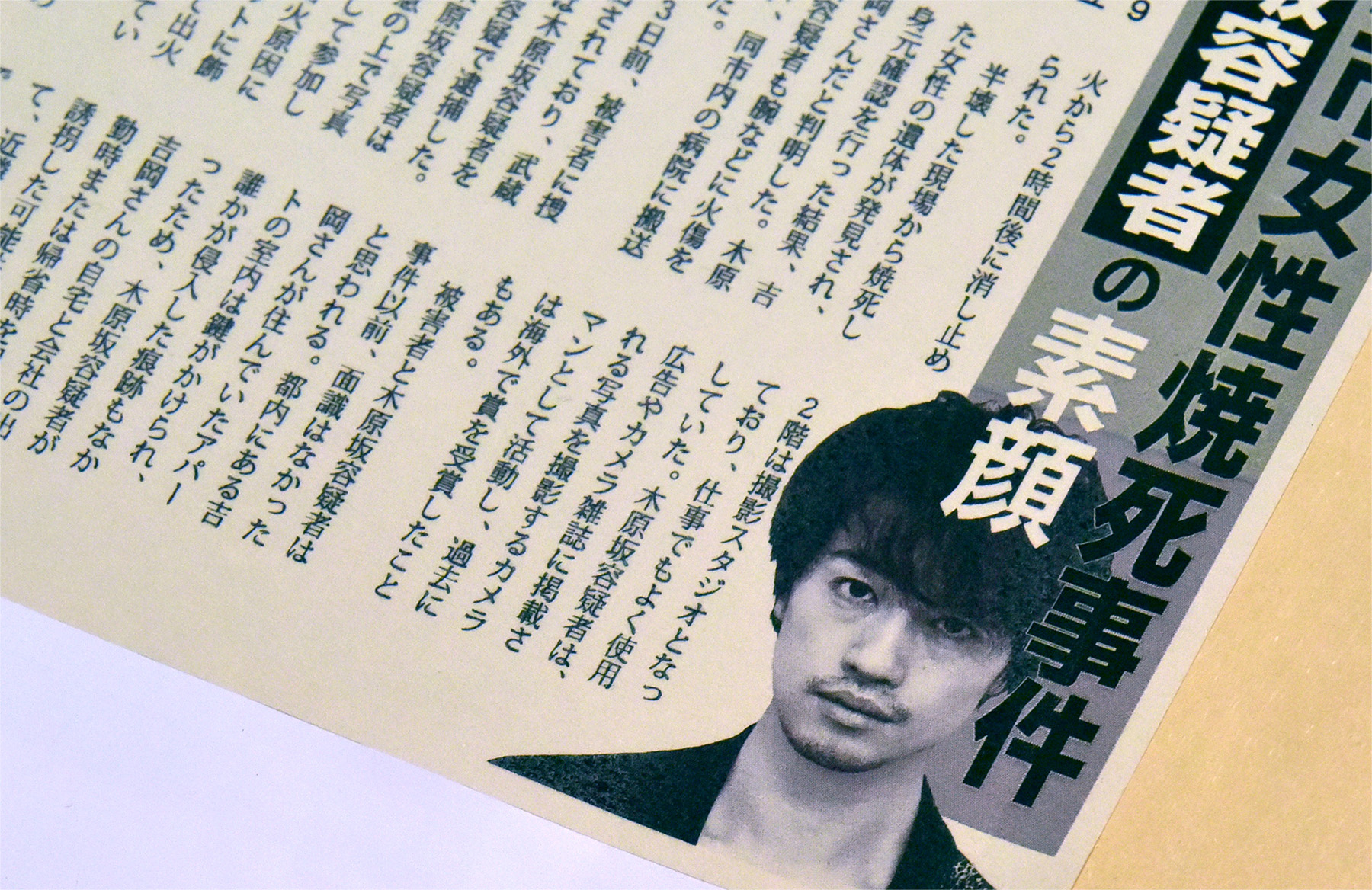
中村 でも1シーン1シーン、凝った映像を撮り上げるのは大変だったでしょう? 瀧本監督のこれまでの作品とも違ったタイプの映画にもなっているし、瀧本監督の新しい一面を観ることができて、感動しているんですよ。
瀧本 その言葉を聞けただけで、僕はもう満足です(笑)。
核となる部分は変えず、中村文則の美しい文体をどう映像化するか
──これまで映像化不可能と言われてきた小説を次々と映画化してきた瀧本監督ですが、文章表現を映像表現に置き換える際に、一番気をつけていることは何でしょうか?
瀧本 中村さんが先ほどおっしゃいましたが、作品の核となる部分は絶対に変えないということですね。そこは守らないと、まったくの別物になってしまいますから。当然ですが、小説と映画は似て非なるものなんです。どんなに読み物として面白いものでも、僕らはやはり映画脳で再構築していくことになるんです。ご本人を目の前にして言うのもおこがましいんですが、中村さんの小説はほぼ読ませていただいていて、中村さんはとても希有な作家だと思っています。エンターテイメント性と純文学とのハイブリッドな作品になっている。書店に行くと、中村さんの小説は、日本文学のコーナーとミステリー小説のコーナーと両方に置いてあるんですよ(笑)。
中村 あー、見たことあります(笑)。
瀧本 中村さんの小説のそんな面白さを、映像化する上でもうまく表現しなくちゃいけないと思ったんです。それと今回、意識したことは中村さんの文体、文章の美しさです。えげつない描写もあるけれど、嫌悪感なく、小説の世界に入っていける。それって、文章の力だと思うんです。我々にしてみれば、それは映像の力に当たる。なので、カメラ、照明、美術など、こだわれるものは極力こだわって映像にしていったんです。

──なるほど。中村作品の文体の美しさを映像に置き換えると、妖しくも美しい映画『冬きみ』の世界になるわけですね。
瀧本 「そうです」とは自分の口からは言えませんが、いろいろと試行錯誤した上で、出来上がった作品ですね。









