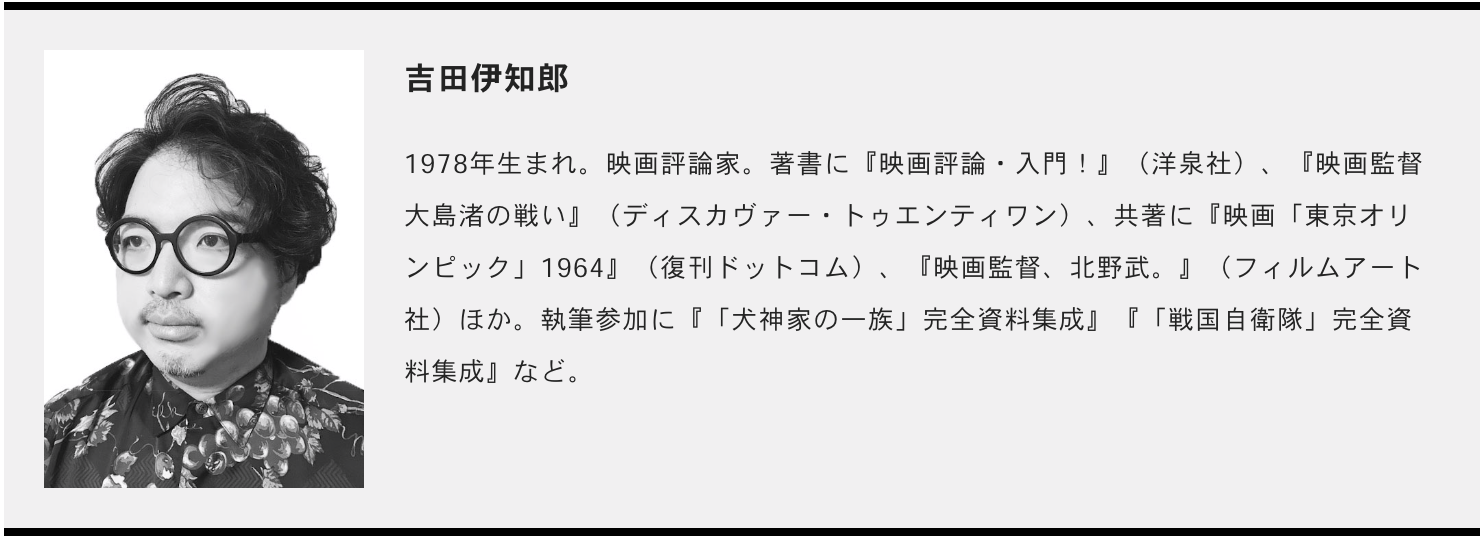映画の誕生を見届ける職人集団 " 東京現像所 / Togen " 05:東京現像所が挑む東宝特撮デジタル修復 (前編) 『地球防衛軍』はいかにして作られたか 解説コラム part2
東京現像所は、フィルム時代から今日に至るまで、映像業界の発展に寄与してきた幅広い映像作品の総合ポストプロダクション。劇場用映画・TVアニメからネット配信コンテンツなど、撮影データから初号完成に向けたDIを始めとする、長年の経験値を織り交ぜたポスプロ作業やヒューマン・ソリューションを提供。新作のポスプロの他にも、名作映画・ドラマなどの貴重なフィルムやテープ素材をデジタルデータに置き換え、必要に応じて高品質のデジタルリマスタリングを行う「映像修復 (アーカイブ) 事業」にも力を注いでいる。(東京現像所沿革)
2023年11月末 (予定) に、惜しまれつつも全事業を終了する。事業終了した後、DI事業、映像編集事業、アーカイブ事業は、東宝グループに承継され、現在携わっているメンバーは、大半が東宝スタジオに移籍する予定。
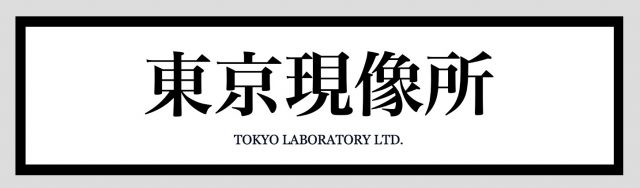
カラー映画の需要が高まりつつあった1955年、既存の東洋現像所(現IMAGICA)に競合する大規模な現像所として設立され、それから68年にわたって、映画・アニメ・TVを中心として映像の総合ポストプロダクションとして数々の名作を送り出してきた。
「午前十時の映画祭」で上映された『地球防衛軍』(1957)の4Kリマスターが大きな話題を集めている。東京現像所が総力を結集して、フィルム・音声を修復し、目が覚めるような画質と音質で甦らせた。
映画が黄金時代を迎えていた1957年、『地球防衛軍』はどのようにして作られたのだろうか。前回に続き、その軌跡をたどってみたい。さらに、(後編) では、実際に作業を行った東京現像所スタッフへのインタビューを掲載する(近日公開予定)。
→東京現像所特集 はこちら
のどかな日本の田舎町に突如として巨大ロボット・モゲラが出現し、それをコントロールする遊星人・ミステリアンが安住の地を求めて富士山麓の原野に巨大なドームと共に姿を現す。半径3キロの土地と、地球人との婚姻の自由を求める平和的な姿勢を見せるミステリアンだが、土地の占拠、女性の拉致を平然と行う姿に、防衛軍は徹底抗戦を決定する。しかし、圧倒的な文明の差によって防衛軍は完敗。このままではミステリアンに地球を侵略されてしまう。世界各国が参加する地球防衛軍が結成され、総力を結集してミステリアンに立ち向かうことになる。
壮大なスケールの物語を、円谷英二 率いる東宝特撮スタッフが映像化し、日常のディテールを丁寧に描く本多猪四郎の演出と見事な調和を見せる『地球防衛軍』を観れば、誰もが66年前にこれだけ質が高く、想像力に満ちた和製SF映画を生みだしたことに感嘆する。

本多猪四郎と『地球防衛軍』
特撮の準備が進む一方で、本多猪四郎監督ひきいる本編の撮影は、1957年8月末から10月にかけて行われた。7月23日付の『毎日新聞』夕刊では、出演者は宝田明、佐原健二、白川由美、団令子となっているが、撮影開始時には、平田昭彦、佐原健二、白川由美、河内桃子に変更されている。撮影開始時期が当初の7月末から1か月ずれこんだ影響が出たのかもしれないが、結果として『ゴジラ』『空の大怪獣ラドン』のキャストが集結しており、特撮に慣れた面々が揃うことになった。
本多が、「こういう作品の場合は、その人が内容とかテーマに興味を持ってくれないと。いくら肉体がそれらしい演技をしていても、ダメです」(前掲『東宝SF特撮映画シリーズVOL.5』)と語るように、俳優たちの真剣な眼差し、姿勢が特撮にリアリティをもたらす。
本作の出演者たちが、実際にどう考えていたかは、『東宝』(58年1月号)掲載の佐原、平田、河内、白川による撮影を振り返った対談から、うかがい知ることができそうだ。興味深い発言をいくつか抜粋してみよう。
「白川 特技監督の円谷さんが、“白川君、こういう作品にまた出演させてすまんね。河内君にしても君にしても、やっぱり二枚目を相手にラヴシーンをやっている方がいいだろうにね”っていわれたけれど、私は相手が二枚目だろうと怪獣だろうと、演技の勉強にかわりはないし、なまじ自分の下手な演技で相手の男優さんに御迷惑おかけするより、モゲラや宇宙人の方が気軽にやれるから、これからもどしどし出演させて下さいってお願いしたの」
「河内 平田さんはね、今度の役で私に仇をうったッて大威張りなのよ。
白川 どうして?
河内 前の『ゴジラ』の時ね、私にふられる役をやったでしょう。その3年も前のことを覚えていてね。いつかは私をふるような役をやろうッて考えていたのね。(略)だから、今度は僕が君をふったんだッてイバるのよ」
特撮映画に出演することを馬鹿馬鹿しいと思っていれば、こうした発言は出てこないだろう。しかし、楽しんでいるばかりではなく、その場にいないものに向かって演技することの難しさも語られている。
「白川 御殿場のロケーションで、モゲラに追いかけられ、必死の形相でふり返るカットを撮ったんだけど、何回やってもNGの続出。怖がり方が足りないって監督さんからも云われるンだけど、あんまり想像力のたくましくない私だから、それが実感となって出ないのね。自分ながら情けなくなって半分泣きながらやったら、“そうそう、その顔がいい!”ってほめられてやっとOK!(笑)」
本作では、モゲラに続いて宇宙人のミステリアンも登場する。しかも人間と変わらない風貌だけに、同じ驚くにしても、モゲラと異なる驚き方をしなければ単調になってしまう。この対談で平田が冗談めいた調子で、「セットに僕たち4人集まるといつも“驚き”表情コンテストをやったね」と語っているが、それこそは本作に欠かせないレッスンだったのではないか。
その意味で、ミステリアンの総領を演じた土屋嘉男は、本人が乗りに乗って演じなければ、ここまで強烈な印象を残すことはなかっただろう。なにせ顔がほとんど隠れている上に、無機質な一本調子の声(AI音声のようなもの)だけに、誰が演じているか、クレジットを見なければ気づかない。顔が売れることを第一に考えれば、名のある俳優は嫌がるところだ。しかし、SF好きの土屋は自ら志願してミステリアンの総領を買って出て、表情や声に頼らない演技を見せている。
本編の撮影を見ていくと、映画の冒頭を飾る富士山の裾野にある村で行われる盆踊りの場面は、都内の氷川神社で撮影された。のんびりとした祭りのムードを丹念に見せた後、木が根元から燃える不可思議な山火事が発生する。川を挟んで山が燃えるのを右往左往しながら村人が見つめるカットは合成だが、このカット一つ取っても合成カットの質の高さがわかるだろう。本作では、ミステリアンのドームと人間の合成をはじめ、随所に合成が多用されているが、いずれも映画への没入感を削ぐことがない。
モゲラの出現後は、本編と特撮のカットバックが見事だ。静岡県駿東郡小山町、御殿場線の山北―谷峨間の鉄橋を中心にロケーションされた逃げ惑う人々と、光線を吐いて家屋を破壊しながら進行する無機質なモゲラは、当然ながら本編のロケと、スタジオのミニチュアと着ぐるみで撮影された特撮を組み合わせたものである。これらが編集でひとつながりになったときの統一感は今見ても素晴らしい。
軒を並べた家屋が炎上するなかをモゲラが歩を進め、消防隊が放水して撃退しようとする。本編部分の放水カットと、特撮部分のモゲラに放たれる水のつながりも絶妙で、こうした細部の充実ぶりが、虚構を真実に変えていく。
また、モゲラが鉄塔を倒して周辺の民家が停電し、入浴していた白川由美が薄暗い浴室の窓からモゲラを目撃するくだりなど、現実に異物が不意に現れた恐怖を生々しく映し出し、本作屈指の名シーンとなっている。目を光らせながらゆっくり歩くモゲラは、特撮と本編の呼吸が少しでもずれれば、途端にチープなものになりかねない。この場面では、全身を見せずに頭部のごく一部を窓枠と木々の間から、かすかに見せるのも効果をあげている。
陸上自衛隊富士学校が全面協力した自衛隊のモゲラ攻撃シーンは、実際の演習を事前に通知してもらい、その場所にカメラを置いて待機することで、あたかも映画のために撮ったかのように見せた逆算が、映画のスケールを広げている。
本多によると、「映画の中で戦車が走ったり銃を射ったり火炎放射器をやったりなんかするのは全部本物の自衛隊です。(略)どれとどれの武器を使うというのはこっちの画面になるように協力してくれました」(『特撮をめぐる人々 日本映画 昭和の時代』)と、好条件での撮影が迫力ある場面を生み出したと明かす。当然、被写体となる隊員たちにも撮影が行われることは周知されており、絶対に笑わないようにという撮影スタッフからの注意事項も伝達されていたという。
本作では、モゲラだけでなく、ミステリアンの高度な文明に人間側が翻弄されていくだけに、本編部分では、通常の撮影にはない苦労があった。白川がミステリアンに誘拐され、空中に待機する円盤に引き上げられる場面は、服の下に装着した金属のコルセットに細いピアノ線を結びつけ、スタジオの天井に付けられた滑車で引っ張り上げることで撮影された。白川は、スタッフ2、3人がかりで引っ張り上げられる際に、ピアノ線が音を立てるたびにヒヤリとした。しかし、声を立てるわけにはいかないと我慢したものの動悸の高鳴りが自分でもわかったという。
本編の撮影は10月には終盤を迎え、本多猪四郎監督が「映画史上、最も特殊技術の真面目を発揮した作品とし、最もスケールの大きい空想科学映画にしたいと考えている。それとともに『地球防衛軍』には東西両陣営という意識を払拭して、全人類が一つになって平和な生活を造りたいという、世界の素朴な願望を映画の底流として織りこみたいとも考えている」(『TOHO STUDIO MAIL』)という願いをこめた映画が形になろうとしていた。

円谷英二と特撮スタッフが挑んだSF超大作
円谷英二監督が指揮を執る特撮班は、1957年6月から準備を始めて8月初旬より撮影を開始。本編のクランクアップから1か月遅れの11月いっぱいまでかかる予定でスケジュールが組まれていただけに、特撮の分量がいかに多いかが想像できよう。
特に大がかりだったのが、富士の原野に出現するミステリアンの建設した要塞ドームと、地球防衛軍との攻防。まず、地下に潜っていたドームが地中に姿を現す仕掛けが必要となる。これは床下に1メートルほどの空間を確保し、その上に富士の原野をセットで造り、床下に設置されたロクロにドームを乗せて昇降させたものだ。なお、このドームはアクリル製で出来ており、内部に照明が仕込まれて、青、紫、赤などに発光する。
さらに、ドームの周辺には円盤が飛び、アルファ号、マーカライト・ファープ等が入り乱れての撮影となるだけに、ピアノ線を張って周到に準備を重ねての撮影は時間がかかった。
たとえば、アルファ号はタイヤが格納式になっているため、モーターで自動的に収納できるようにしたものの、アルファ号の胴体部分にモーターとタイヤが収まるように仕込むのに手間がかかり、数回の作り直しを経てセットに持ち込むと、タイヤの引き込みが上手くいかない。作業用の部屋へ持ち帰ると上手く作動する。しかし、スタジオのセットに持ち込むと動かない。原因は照明の熱だった。シネマスコープのために通常の3倍の照明を用いたために室温が上昇し、金属が膨張したことでモーターに不具合を起こしていたのだ。そのためにミニチュアの設計をやり直すということになった。こうした悪戦苦闘の中で、9月末の時点では、特撮パートはまだ3分の1しか消化できていなかった。
本作の最大の敵になったのは、モゲラでもミステリアンでもなく、〈電力〉だった。シネマスコープを意識して広大なセットが組まれたが、前述したように、それは照明の使用量が3倍に増すことを意味した。もともとカラー撮影は照明が従来よりも必要となっていたが、シネマスコープとなると、比較にならないほどの電力使用量になる。カラーのシネマスコープ作品を東宝スタジオで複数撮影することが困難になるほどだった。
実際、「カラー、ワイド映画『続柳生武芸帳』『地球防衛軍』の2本をかかえ、電力受入れの関係上この2本を同時にはやれないので『地球防衛軍』がしばらくの間毎晩6時から翌朝5時までの撮影を強行させられるというのが、昨年までは見られなかった撮影所の年末風景」(『読売新聞』57年10月22日・夕刊)と記事になるほど、シネマスコープの電力使用問題は『地球防衛軍』に影響をもたらしていた。なお、記事中の『続柳生武芸帳』とは、『地球防衛軍』の1週遅れで公開された『柳生武芸帳 双龍秘剣』のことである。
電力については円谷も、「我々が本腰を入れて撮影すると、撮影所中の撮影を全部休まなくてはならないんです。だから、みんな撮影が終わってしまってから、我々が出てきてやるんです。夏なんか冷暖房の電気も止めて、汗水たらして撮影するような始末ですね」(『中学一年生コース』58年3月号、『定本 円谷英二随筆評論集成』収載)と語っており、カラー・シネマスコープの使用が大きな負担になっていたことをうかがわせる。
11月1日には、モゲラを撃退するために鉄橋を爆破するシーンの撮影が、東宝撮影所のオープンセットで行われた。前半の見せ場であり、火薬の使用量も多い場面である。2日間にわたって準備と打ち合わせを行い、この日の午後3時に、いよいよ本番となった。2台用意されたカメラは、爆破の影響を極力避けるために、厚いベニヤ板に穴をあけ、そこからレンズを向けていた。火薬をセットし、カメラが回り始める。現場の様子は、撮影を取材した『毎日新聞』(57年11月2日・夕刊)から引用しよう。
「ドカーンと広い撮影所がふるえ上がるくらいの音とともに怪物モゲラの姿は鉄橋の下敷きに‥‥ヌイグルミの中の手塚克巳君は直前に逃げ出すという仕掛けだったが、計算よりも大きな爆発で爆風に吹きとばさるもの、破片で軽傷した者が続出するというさわぎだった」
記事に出てくる手塚克巳は、怪獣の中に入るスーツアクターとして、中島春雄と共に『ゴジラ』『ゴジラの逆襲』『空の大怪獣ラドン』に出演している。アンギラスに入ってゴジラと戦ったのが手塚である。本作でも、中島と共にモゲラへ入ることになったが、これまではいかに生物らしさを取り入れるかに苦心してきたが、今回は「いかに人造機械らしい動きをしたらいいかと苦心している」(前掲『東宝』『定本 円谷英二随筆評論集成』)と円谷は記している。
彼ら以外にも、もう1人、怪獣を演じる手タレというか、ハンドモデルというか、手で怪獣に演技を付ける人物がいた。東宝特殊撮影部操演係の中代文雄である。『ゴジラ』の口の動きは、中代が手を入れて動かしたものだ。アンギラス、ラドンも同様である。モゲラでも上半身部分の寄りのカットは、中代の手によって演技が付けられることになった。その様子を見て、他のスタッフが面白がってやってみようとするが、とても敵わないという。円谷は中代を「東宝怪獣園の園長」(前掲『中学一年生コース』『定本 円谷英二随筆評論集成』)と評している。
なお、この鉄橋爆破シーンは、美術スタッフの井上泰幸によれば、円谷が爆破直後に出来がもうひとつという理由でリテイクを告げたという。井上はどう映っているかをラッシュ試写で確認してからにしてくれと進言し、円谷を煙たがらせたが、ラッシュで確認すると、このカットは映っていなかったという。フィルムが噛んで撮影できていなかったのだ。どうやら円谷は撮影時にその報告を受け、担当していた撮影助手をかばうために理由を作ってリテイクを告げたようだ。結局、再度鉄橋を作り直してリテイクされることになり、現在観ることができる爆破シーンとなった。
撮影中、円谷を慌てさせた事件が起きた。1957年10月4日、ソビエト連邦が世界初の人工衛星となるスプートニク1号の打ち上げに成功したのだ。劇中にも人工衛星が登場するだけに、近未来を見越してデザインにも苦心してきた円谷にとっては、まさか撮影中に現実が追いついてこようとは、想像もしていなかった。
本編を撮影中だった本多猪四郎監督は、スプートニク・ショックについて円谷と語りあったという。曰く、「とうとう飛んじゃったけど、今時分こんな宇宙ものダメになるんじゃないかということを話し合った記憶がありますよ。撮影所で」(前掲『特撮をめぐる人々』)。
円谷はスプートニク対策として、脚本を一部改訂し、ラストカットを追加した。それは外星人からの地球への侵略を事前に察知するため、監視用の人工衛星が地球の上に浮かんでいるカットだった。
この人工衛星のデザインについては、ソ連のスプートニク型ではなく、アメリカの科学雑誌に掲載されていた米国製の人工衛星を参考にしたが、円谷はその理由を、「別に私がソ連ぎらいのアメリカ・ファンというのではなく、その方がイメージにピッタリだから」(前掲『漫画読本』『定本 円谷英二随筆評論集成』)と明かしている。
余談ついでに記せば、本作に登場する円盤について、円谷は機動性があるものと解釈し、それらしい円盤にしたと語っているが、UFOの目撃経験が円谷にはある。『ハワイ・マレー沖海戦』(1942)の撮影を行っていた1942年8月、東宝スタジオ上空を猛スピードで北から南へと飛翔する楕円形の発光体を目にしたのだ。それも雲ひとつない白昼の出来事だった。そのときは未確認飛行物体という認識はなかったが、後年になって、あれは円盤だったと思うようになったという。
本作には、ビルの屋上から人々が東京上空を猛スピードで飛翔する円盤を目撃するシーン(日比谷の東宝本社屋上で撮影された)があるが、あの見事な飛翔は、円谷の実体験が反映されているのかもしれない。

『地球防衛軍』の光と音
長期間にわたる特撮パートの撮影は、年末に入り、ようやく終わりを迎えた。11月12日に後楽園競輪場で行われた東宝の運動会では、本社対撮影所の対抗戦で行われた仮装コンクールに、撮影所側は『地球防衛軍』にちなんで宇宙人と自衛隊戦闘を披露するなど、映画が完成に向けて盛り上がりを見せ始めていることを感じさせる。
だが、撮影を終えても円谷は気が休まらなかった。『地球防衛軍』の成否は、撮り終わったものへの合成、加工にかかっていた。特に円谷が重視したのは、〈光線〉と〈音〉だった。実際、これまでの特撮作品と比べても、本作は光線が多用されており、ミステリアンばかりか、地球防衛軍側も発射する派手な光線同士の対決となるだけに、派手でありつつ、単調にならないようにしなければならない。
円谷は「地球軍の熱線は、特殊な波長を放射する白色光、ミステリアン側は、ガンマー線を含んだ電光のような形にした」(前掲『漫画読本』『定本 円谷英二随筆評論集成』)と双方を差異化させ、形状、色に違いを持たせて変化をつけた。
線画による光線の合成を担ったのが飯塚定雄。東宝特撮における光線表現を確立した立役者である。本作で初めて光学作画に挑んだ飯塚は、円谷からの光線の色に変化をつけるという要望に悩まされる。その苦労を次のように語っている。
「当時カラーで光線に色を付けるってのは、凄く大変だったんですよ。どうするかっていうと、マスクで1回抜いて、そこにフィルターで色を付けて、合成を焼く。だからモゲラの光線を見ると、周りが白っぽくて中に色が付いてる」(『僕らを育てた合成のすごい人 増補改正版』)
もうひとつ、〈音〉の問題が残っていた。録音を担当した宮崎正信は、「こんどの“地球防衛軍”では、モゲラの移動する音、ミステリアンという宇宙人の音、ドームが地下からせり上がる音など、いろんな音を考えなければならないので、今から頭痛のタネだ」(『読売新聞』57年9月7日・夕刊)とこぼしている。ゴジラの鳴き声をコントラバスで、アンギラスを木管楽器で、ラドンはコントラバスと人間の叫び声に加工を加えて合成するなど、様々な奇想で怪獣の声を作り出してきた宮崎をもってしても、本作の音は難易度が高かった。
『毎日新聞』(57年9月26日・夕刊)には、「円盤の飛ぶ音など特殊な音響効果を受け持たされた録音部は、録音機を持って珍しい音響の収集に飛び歩いている」と書かれているが、円盤の飛翔音は3種類の音を混ぜて作られることになった。テレビに登場する円盤の音と差別化し、複雑さを持たせるためである。
マーカライト・ファープの音になると、さらに複雑さを増す。「グランドピアノのふたをあけ、2人くらいがその上に乗っかるんですよ。そして、10円硬貨でケンの上をガーッとこするんです。それとバクパイプの音、それから子供用ヴァイオリンのコマの上をこすったり、こまどめの上をこすったりした音をテープにとるんです。それらの音を合成するわけなんです」(前掲『中学一年生コース』『定本 円谷英二随筆評論集成』)と、宮崎は語る。
こうして企画開始から足かけ3年、撮影準備も含めて半年にわたって製作が続いたSF大作『地球防衛軍』は、1957年12月10日に完成を迎えた。
直前まで光線の修正や追加撮影を行っていたためか、円谷は翌日に東宝本社でひらかれたセシル・B・デミル監督のスペクタクル大作『十戒』(1956)の試写を失念してしまう。特殊技術をふんだんに使用した大作だけに、円谷は観るのを楽しみにしていたのだ。その失望感は次の文章からも感じることができるだろう。
「折悪く、『地球防衛軍』の追い込み撮影で徹夜をつづけ、いささかグロッキーで、すっかり日数が混乱していた時なので勘違いをして見落としてしまい、翌日気がついた私は頭をかかえて思わず長嘆息したものである」(『映画評論』58年4月号、『定本 円谷英二随筆評論集成』収載)
幸い公開前に試写会で観ることができたが、『地球防衛軍』を完成させて次なる企画へ思いをはせていた時期だけに、円谷は『十戒』に大いに感銘を受け、その特殊技術から大いに刺激を受けたに違いない。

その後の『地球防衛軍』
1957年12月28日、『地球防衛軍』は『サザエさんの青春』と2本立てで、東宝の正月映画として一斉公開された。前々日の『読売新聞』夕刊には全面広告で、この2本が宣伝されている。「お正月のお楽しみは東宝で」「日本中が湧くこの素晴らしい2本立」「バラエティに富み!面白く御家族揃って楽しめる」という惹句が、いかにも正月映画らしいにぎやかさを伝える。
公開前の宣伝には、ユニークなものがあった。電報作戦とでも言うべきもので、「一九五七ネンヨリ一九五八ニカケ ニッポンヲモクヒョウニ チキュウヲコウゲキ チキュウボウエイグントケッセンス ミギケイコクス」と書かれた電報を作成した。宛名は「ギンガケイ タイヨウケイ チキユウ ニッポンノミナサン」、差出人は「ミステリアンAX」となっている。
電報用紙も本物とそっくりのものを用意し、発信局が「地球防衛軍電波局」になっている。これを映画館の従業員が各家庭の郵便受けに入れて回って宣伝したのだ。「この特電につき疑問の点がありましたら、◯◯◯◯の東宝宣伝部へお問い合わせください」と書いてあるところからも直ぐに宣伝とわかるようになっていたが、「電報局からは“こういうまぎらわしい印刷物は今後なるべく作らないように”との要望書が東宝宣伝部に届けられました」(『宣伝・ここに妙手あり』)と、やんわり注意を受けたようだが、この電報を自宅に投函してほしいと思うファンは今も多いに違いない。
『地球防衛軍』は大ヒットを記録し、海外市場でも35万ドルの収益を上げるなど、東宝特撮が世界に通用する高い質を誇ることを実証した作品となった。
なお、原作者の丘美丈二郎は、本作が公開された直後、『中学生の友』(58年3月号)に『ミステリアンまた来襲す!!』を執筆している。挿絵を小松崎茂が描いたもので、15年後を舞台にした『地球防衛軍』の続編である。
1975年、ミステリアンは火星で態勢を立て直し、再度地球への襲撃を画策していた。前回は平和的に装って地球人に接近したが、今度は一挙に総攻撃を仕掛けて来るという。地球防衛軍司令部で働く15歳の花村雪男少年は、父の花村博士から、ミステリアンの人工衛星に原子爆弾が搭載されていることを知らされる。地球で作られたものより20倍の威力があり、日本など1発落とされるだけで壊滅するという。ミステリアンは10時間以内に世界各地で原爆を搭載した人工衛星を爆発させ、人類を全滅させるつもりらしい。地球防衛軍は、戦闘用のロケット宇宙船で応戦することになり、雪男少年も父と共に搭乗することになる。花村博士は、今回の戦闘では〈静かな戦争〉を行うという。撃ち合いをすることなく、敵の原爆を取り上げて、無力化してしまう。その方法とは――。
というもので、映画を踏まえた内容になっているだけに、映画化されなかったことが残念でならない。もっとも、攻撃を行わない〈静かな戦争〉が特撮映画に相応しいものになるかどうかは別の話だが。
最後に、『地球防衛軍』の完成を見届けることなく世を去った俳優についてもふれておきたい。ミステリアンの一員を演じた海上日出男である。
戦前、河合映画から巣鴨撮影所、大都映画、吉本興業などを渡り歩く大部屋俳優だった海上は、戦後、紆余曲折を経て一念発起して「生活圏外の人」というプロットを、東宝の重役だった森岩雄に送る。採用はされなかったものの、これまでの経歴を買われて、東宝の演技課に入ることになった。大部屋俳優として、『七人の侍』(1954)、『空の大怪獣ラドン』等にも出演したが、海上が異色なのは、ここで突然、ゴジラの新作脚本を書いてしまったところだ。
当時、すでに『ゴジラ』『ゴジラの逆襲』が公開されていたが、それに続く新作として、海上は『ゴジラの花嫁?』を自発的に執筆し、森へ送る。アンギラス、大ダコ、人魚も登場する破天荒な内容だったが、田中友幸プロデューサーが興味を示した。事実、それから約30年後に公開された1984年版『ゴジラ』の企画開発の段階でも、『ゴジラの花嫁?』をひな形に脚本開発が進められた。特に、劇中に登場する「子馬程の吸血鬼?(蚤の化け者)」は、ゴジラやアンギラスについていた蚤だと説明されるが、この設定は84年版『ゴジラ』の巨大なフナムシに継承されており、海上の才能がここからも垣間見える。
もっとも、海上が『ゴジラの花嫁?』を書いた当時の東宝は、ゴジラ映画を2本で打ち止めにしており、それ以外の企画を求めていた。そこで、海上がかねてより考えていた『液体人間』の話をすると、田中は「すぐにホンにして来いといっておいたが、10日もしない内に出来てきた。手は早い男だった」(『週刊サンケイ』58年7月20日号)と証言する。
この時期、円谷英二とも面識を得たが、『液体人間』の原稿を読んだ円谷は、これなら映画になると太鼓判を押した。海上の原作をもとに、木村武が脚本を書いた『美女と液体人間』は、1957年10月に書き上がった。この時期、海上はミステリアン役として俳優業に打ち込んでいた。
小松崎茂のデザインに基づいたミステリアンの衣装は、高度な文明を反映したものになっており、頭にはヘルメット型のマスクをかぶり、光沢のある服をまとっている。これをガラス繊維で作ったために、ガラスの粉が飛び散って、スタッフ、俳優はチクチクするために難儀したという。なお、この衣装は京都衣装が作ったもので1着1万円である。
こうした撮影を俳優として続けながら、海上は『美女と液体人間』の実現を心待ちにしていた。ところが『地球防衛軍』の撮影を終えた翌月の11月、心臓麻痺で急逝してしまう。前掲の『週刊サンケイ』では、本多猪四郎と円谷が、それぞれ追悼の言葉を寄せている。本多は「非常に熱心な人でした。演技もいろいろ工夫していたようですが、性格が地味な人だから、目立たなかったようですが」と語り、円谷も「せっかく空想科学班に有力な一員が得られたと思ったのに」と、その才を惜しんだ。
俳優としての遺作となった『地球防衛軍』が観客を沸かせた1958年の正月が明けると、円谷は仕事始めに次なる映画へ取りかかった。海上日出男原作の『美女と液体人間』である。
『地球防衛軍』に海上の名前はクレジットされていない。ミステリアンの中の誰が海上なのかも、見分けがつかない。しかし、東宝のSF特撮に多大な功績を持つ優れた人物が、人知れず懸命にミステリアンを演じていたことは記憶しておきたい。
文 / 吉田伊知郎
撮影 / 吉田周平
写真協力:TOHOマーケティング
【参考文献】
「読売新聞」「毎日新聞」「週刊娯楽よみうり」「週刊サンケイ」「中学生の友」「東宝」「キネマ旬報」「映画評論」「東宝特撮映画全史」(東宝株式会社)、「東宝SF特撮映画シリーズVOL.5 キングコング対ゴジラ・地球防衛軍」(東宝出版事業室)、「定本 円谷英二随筆評論集成」(円谷英二 著、ワイズ出版)、「円谷英二の映像世界」(実業之日本社)、「神を放った男 映画製作者 田中友幸とその時代」(田中文雄 著、キネマ旬報社)、「小史にかえて 博覧会と田中友幸」(日本創造企画株式会社)、「特撮映画美術監督 井上泰幸」(キネマ旬報社)、「「ゴジラ」東宝特撮未発表資料アーカイヴ プロデューサー・田中友幸とその時代」(角川書店)、「特撮をめぐる人々 日本映画 昭和の時代」(竹内博 著、ワイズ出版)、「僕らを育てた合成のすごい人 増補改正版」(アンド・ナウの会)、「映画唯物論宣言」(三隅繁 著、樹花舎)

株式会社東京現像所 (TOKYO LABORATORY LTD.)
所在地:本社 東京都調布市富士見町2-13
1955年、東宝・大映・大沢商会など、映画関係各社の出資により設立。2023年11月30日に全事業を終了。

映画『地球防衛軍』【東宝特撮Blu-rayセレクション】
富士山麓で奇怪な山火事と山崩れが発生。調査に向かった渥美の前にロボット怪獣モゲラが姿を現した。モゲラ出現が異星人の仕業と推測した安達博士と渥美ら一行は、空飛ぶ円盤が頻繁に目撃されているという現地に到着。すると地表を突き破り、突如巨大ドームが姿を現した。ドームに身を隠していたミステリアンと名乗る宇宙人は、ドームから半径3キロの土地の割譲と地球人女性との結婚の自由を要求してくるがーー。
監督:本多猪四郎
出演:佐原健二、平田昭彦、白川由美、土屋嘉男、河内桃子、藤田進、志村喬、小杉義男
発売・販売元:東宝
「地球防衛軍」© TOHO CO., LTD.
発売中 (※4Kリマスターではありません)
販売サイト:https://tohotheaterstore.jp/items/TBR20063D