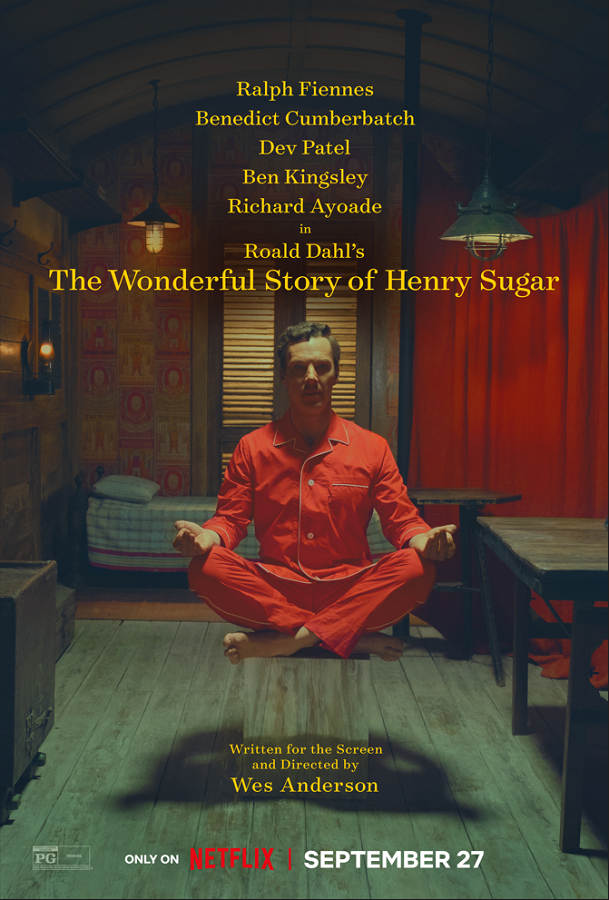デザインとディテール=ストーリーテリング
撮影前にウェス・アンダーソンはプロダクション・デザインのアダム・シュトックハウゼンと共にロケーション予定地周辺を何度も訪れるという。何度もその地を訪れながら、繰り返し目に入るもの、その土地に根付いた類似性をピックアップしていく。たとえば『グランド・ブダペスト・ホテル』の石炭を燃やす暖炉器具は、現地を回る際、何度も目にしたことからインテリアとして採用されたのだという。この繰り返し目にすることで立ち上がる「反復のイメージ」は、とても映画の作用と似ている。『フレンチ・ディスパッチ』では、ロケ地となったアングレームの街の細かい坂道や階段が繰り返し描かれているのが印象的だ。野良猫たちと人間が路上で共存する架空の街、アンニュイ=シュール=ブラゼ。坂道や階段のデザインが自ずとストーリーを語り始める。そして『フレンチ・ディスパッチ』自体が、旅する野良猫と野良犬が編まれた「アンソロジー映画」ともいえる。
ベニチオ・デル・トロが演じる画家であり囚人でもあるローゼンターラーは、まさしく旅する野良犬だ。ローゼンターラーは戦場を始め、各地を渡り歩いた末に、刑務所にいる。あるいは自由の戦士として永遠のアイコンとなるゼフィレッリ(ティモシー・シャラメ)。パリに移り住んだ黒人小説家ジェイムズ・ボールドウィンが明確に参照されているローバック・ライト(ジェフリー・ライト)というキャラクター。そしてこの作品の全ての始まりとなる「遺言」を残した、フレンチ・ディスパッチ編集長、ハウイッツァー(ビル・マレーイ)。例外的なまでに一人の俳優=レア・セドゥに捧げられているといえるシモーヌという役柄や、悲しみを瞳の奥に隠したクレメンツ(フランシス・マクドーマンド)、名前のないショーガール(シアーシャ・ローナン)に至るまで、彼ら彼女らは一様に取り残された孤児であるかのようだ。

『フレンチ・ディスパッチ』は、ウェス・アンダーソンのこれまでの作品がそうだったように、野良犬、野良猫たちによる冒険譚であり、たとえばシモーヌが流す涙や、クレメンツの涙のない涙、そして汚れた世界に映える一輪の花のようなシアーシャ・ローナンの美しい青い瞳のクローズアップのように(『グランド・ブダペスト・ホテル』のアガサのマジカルなクローズアップを想起させる)、俳優のディテールに対するこだわりが映画を駆動させている。大きな視点から始まるのではなく、小さな視点の積み重ねられた集合体こそが、『フレンチ・ディスパッチ』という作品を形作っていく。
『フレンチ・ディスパッチ』のオールスターキャストは、信じがたいことに誰もが映画を駆動させる原動力として個別の肖像を纏っている。プラダのショートフィルムで初めて出会い、本作で大きな役を任されているレア・セドゥは、キャスト、スタッフ、エキストラに至るまでヒエラルキーのないウェス・アンダーソンの現場が楽しくてしかたがないのだという(エキストラへのこだわりは「ペットを飼っている人」とのこと)。
『ダージリン急行』を見て、ファンレターを出したことから連絡の交換が始まり、もはや常連となったティルダ・スウィントンは、ウェス・アンダーソンの現場を「サーカス団」に例えている。同じホテルに泊まり、同じ食事をとり、話し合う。ホテルのホールにはウェス・アンダーソンの用意した映画ソフトが並べられていて、それについて語り合うこともできる。事前に準備された自由な創作の雰囲気。完璧主義でほとんど隙のないように見えるウェス・アンダーソンの映画だが、俳優の演技の作り方には大きな自由が与えられているのだという。ジュリエット役のリナ・クードリはインタビューで次のように語っている。
「あるシーンでは私たちがやりたいことを自由にできるようにしてくれます。“次のテイクは君のものだ、君のビジョンを見せてくれ”みたいな感じです。だから私たちは何かを提案し、彼自身の指示も受けながら、それに取り組んでいくことができるのです。枠に守られているようでいて、同時に自由であることは、俳優として非常に楽しいことです」
出典: Fandom Wire 「The French Dispatch: Lyna Khoudri On Working With Wes Anderson & Timothée Chalamet」
(リナ・クードリ)