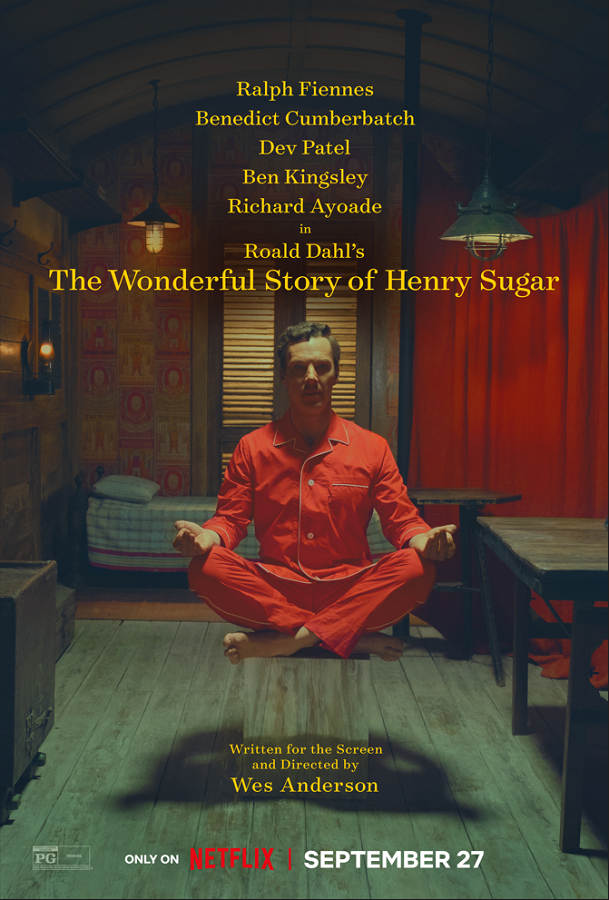ウェス・アンダーソンによる待望の新作『フレンチ・ディスパッチ』は、この作品のモデルとなったニューヨーカー誌の偉業に捧げられているだけでなく、映画を介して、すべての創作に関わる者への「連帯」を示している。本コラムでは、いまだ謎のベールに覆われているウェス・アンダーソンのメソッドを探っていくと共に、「連帯」の意思が、どこからやってきて、どのような創意工夫でそれがフィルムにつなぎ止められているかを探求していきたい。
ワーカホリック、且つ、完璧主義者でありながら、常に自由であることの喜びと悲しみをメランコリックに歌い届けてくれる映画のマエストロ。こうしている間に、ウェス・アンダーソンは既に次回作の撮影をスペインで終え、イングランドでさらなる新作の撮影に入ろうとしている。フレンチ・ディスパッチ事務所に刻まれている「ノー・クライング」の掟のように、涙を流す余裕さえ許されないスピードで。まずは、この大傑作の放つ絢爛な色彩と加速度を増していく感情のスピードを全力で受け止めたい。

異邦人としてのフランス映画
「レオス・カラックス監督の『アネット』が公開されたカンヌ国際映画祭で、この映画が初公開されたのは不思議な縁です。レオス・カラックスの映画のいくつかのシーンが、本当にインスピレーションを与えてくれたのです」
出典: i-D.Vice 「How Wes Anderson built the world of The French Dispatch」
(ウェス・アンダーソン)
ウェス・アンダーソンの新作『フレンチ・ディスパッチ』は、ニューヨーカー誌やジャーナリストたちへのラブレターであるだけでなく、キャストのレア・セドゥやリナ・クードリも言うように、ウェス・アンダーソンによる「フランス映画へのラブレター」でもある。
ジャック・タチ監督による『ぼくの伯父さん』でムッシュ・ユロが住んでいた、あの風変わりな構造のアパートメントが、そのまま巨大化したようなビル。その上層階に位置する「フレンチ・ディスパッチ編集部」。架空の町アンニュイ=シュール=ブラゼの象徴として示されるこの建築物は、ウェス・アンダーソンのこれまでの作品の舞台がそうであったように、架空の島、あるいは架空の墓でもある。ウェス・アンダーソンは、この町の汚れてしまった部分に関心を寄せる。ペストの広がりを防疫するために施行された「パリ改造」以前の風景を参照にしたというアンニュイ=シュール=ブラゼには、いまは消えてしまった風景、捨てられてしまった風景への憧憬がある。このことは、前作『犬ヶ島』が廃棄物の島を舞台にしていたことを真っ先に思い出させる。