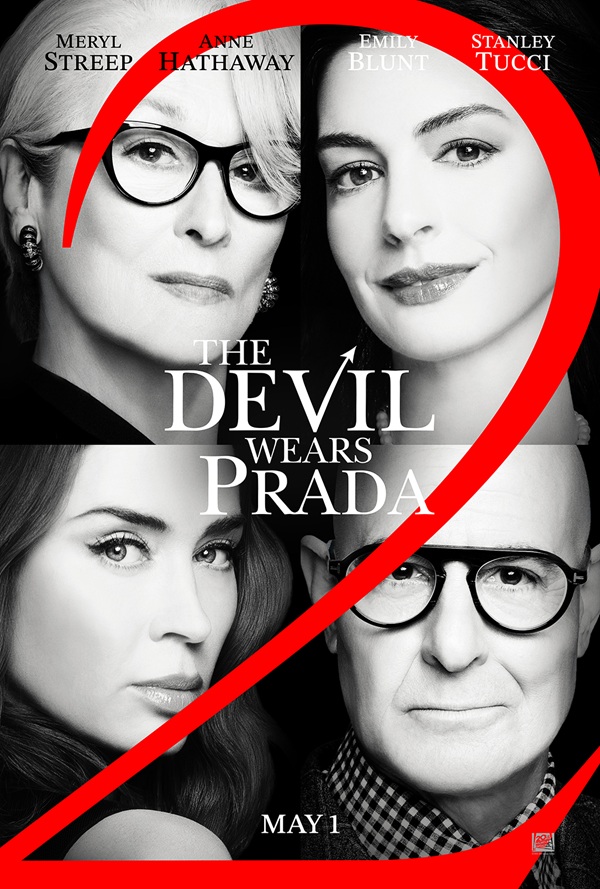北アイルランド紛争とホームコメディ
物語の舞台は1969年の夏、北アイルランドのベルファスト。ブラナー自身の故郷であるこの街で、プロテスタントの集団がカトリックの住民たちを攻撃し始めた。事件の背景にあるのは、宗派の対立と北アイルランドの領有権をめぐって勃発した「北アイルランド紛争」。1990年代末に解決を見るまで、およそ30年間で約3600人が犠牲となった。映画の冒頭では、穏やかで平和な街が、突如として戦場さながらに変貌する様子が描かれている。
ブラナー自身を投影した9歳の少年・バディ(ジュード・ヒル)は、暴動で激変した世界を生きていく。家族のため出稼ぎをしている父親・パ(ジェイミー・ドーナン)はたまにしか家に帰ってこられないが、パに代わって家族を守る母親・マ(カトリーナ・バルフ)、祖父のポップ(キアラン・ハインズ)と祖母のグラニー(ジュディ・デンチ)、兄のウィル(ルイス・マカスキー)との生活は続くし、思いを寄せているクラスメイトのキャサリン(オリーブ・テナント)に近づきたい気持ちも変わらない。しかし情勢の緊迫は続き、暴力の気配は日常に充満している。家族を案じるパは、いっそベルファストを離れ、一家で新たな地へ移住することを提案するが……。
ブラナーが本作を着想したのは2020年のこと。新型コロナウイルス禍によって、日常生活があっという間に変わってしまったことがきっかけだったという。1960年生まれのブラナーは、ロックダウンの生活を送る中、かつてベルファストで過ごした先行きの見えない日々を思い出し、当時と現在には通じるところがあるとして、「あの頃のベルファストを描く映画を作りたい」と考えたのだ。バディが体験する出来事の多くは、ブラナーの自伝本『私のはじまり ケネス・ブラナー自伝』(白水社刊)に記されているエピソードに基づくもの。映画化にあたり脚色は加えられているが、作品の根底に自身の体験が横たわっていることがうかがえる。

本作の白眉は、ほとんど戦時下ともいうべき紛争状態を背景にしながら、ブラナーがこの物語を一種のホームコメディとして描いていることだ。バディやウィルを守りながら生活を維持せねばならないパとマにとっては終始深刻な時代だが、子どもの視点から見れば、街にはあっけらかんとした空気さえ漂っている。
この、「子どもの目から見たベルファスト」を大人の観客にも受け入れさせるところが、映画という虚構から現実を捉えることの効果のひとつだ。家族と出かけた映画館、学校での甘酸っぱい恋模様、年上の少女・モイラ(ララ・マクドネル)にけしかけられての万引きなど、厳しい情勢下ながらもシリアスさではなくハートフルさを、“笑い”や“温かさ”を前面に押し出すテイストは、ブラナーのフィルモグラフィにおいても珍しいものだ。大人目線や神の視点では描けない、かつてブラナー自身が見たベルファストの街がここにある。
こうしたテイストを結実させたのは、ブラナーこだわりのキャスティングだろう。パ役のジェイミー・ドーナン、祖父役のキアラン・ハインズはベルファストの出身であり、マ役のカトリーナ・バルフ、祖母役のジュディ・デンチはアイルランドにルーツを持つ。コロナ禍のために実際の街ではあまり撮影できず、多くのシーンはセットでの撮影となったが、役者たちがその土地に暮らす家族の雰囲気を醸し出したのだ。

俳優それぞれの個性をきちんと活かしつつ、家族としてのまとまりを生み出したのは、実力者たちのアンサンブルとブラナーによる演出の妙。バディ役のジュード・ヒルは本作が映画デビューの新人とあって、フレッシュな演技の魅力を引き出すべく、ヒル本人には「まだリハーサルだから」と伝えておきながら、こっそりとカメラを回していたことも多かったそう。完成した映画にも“偽リハーサル”のテイクが多数使用されているということだ。
ちなみに「紛争」と「コメディ」というキーワードで言えば、バディやパに接近する過激派の男、ビリー・クラントン役を演じたコリン・モーガンの果たした役割も大きい。本作でほとんど唯一の悪役を務め、ハードな時代背景や暴力の匂いを一手に担った彼もまた、ベルファストの大学で演劇を学んだという経歴の持ち主だ。劇中では、ただ単純に暴力をふるうだけではない繊細な人物造形を垣間見せてくれる。