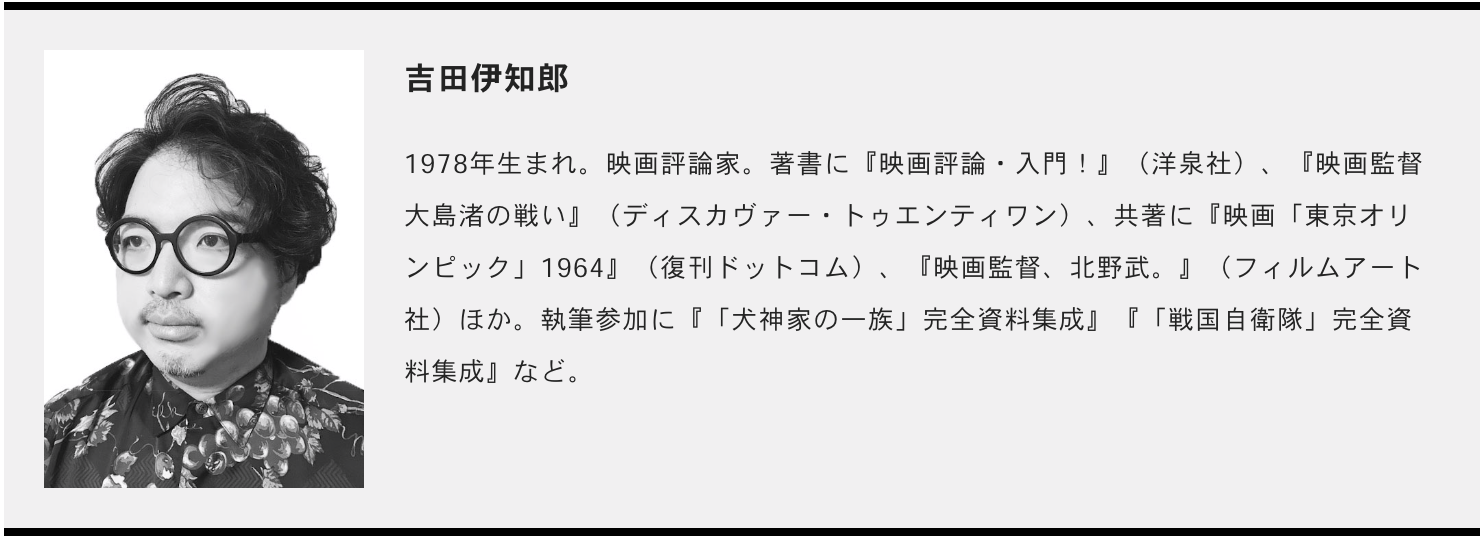映画の誕生を見届ける職人集団 " 東京現像所 / Togen " 07:画期的な色彩を生み出した銀残しと現像 映画『おとうと』
東京現像所は、フィルム時代から今日に至るまで、映像業界の発展に寄与してきた幅広い映像作品の総合ポストプロダクション。劇場用映画・TVアニメからネット配信コンテンツなど、撮影データから初号完成に向けたDIを始めとする、長年の経験値を織り交ぜたポスプロ作業やヒューマン・ソリューションを提供。新作のポスプロの他にも、名作映画・ドラマなどの貴重なフィルムやテープ素材をデジタルデータに置き換え、必要に応じて高品質のデジタルリマスタリングを行う「映像修復 (アーカイブ) 事業」にも力を注いでいる。(東京現像所沿革)
2023年11月30日に、惜しまれつつも全事業を終了する。事業終了した後、DI事業、映像編集事業、アーカイブ事業は、東宝グループに承継され、現在携わっているメンバーは、大半が東宝スタジオに移籍する。
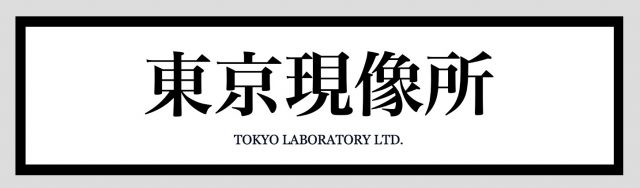
カラー映画の需要が高まりつつあった1955年、既存の東洋現像所(現IMAGICA)に競合する大規模な現像所として設立され、それから68年にわたって、映画・アニメ・TVを中心として映像の総合ポストプロダクションとして数々の名作を送り出してきた。
1960年公開の映画『おとうと』で、映像技巧に長けた監督・市川崑×キャメラマン・宮川一夫のコンビは、大正時代を色彩で表現するという大胆な試みに挑んだ。
相談を持ちかけられた東京現像所は、意見交換を行い試行錯誤の上、カラーポジフィルムの現像工程の中で、銀を洗い流す工程を省いて生み出した、世界初の映像表現〈銀残し〉を用いて作られることになった。今回は、『おとうと』映画化への軌跡と「銀残し」について解説する。
→東京現像所特集 はこちら

『おとうと』映画化への軌跡
フィルムからデジタルへ――映画撮影の主流が変わったことで、最も大きな革命が起きたのは、ポストプロダクションだろう。
フィルムの現像がなくなり、撮影された素材は、そのままデジタルデータとしてコンピュータに取り込まれ、ソフトウエア上で編集作業が行われるようになった。最近ではカラーグレーディングの技術も向上し、作品の世界観に合わせて細かな色調を作り込むことが可能となり、また、肌のみを明るくするなど、細部の変更も容易となった。
こうした時代に、例えば市川崑監督の映画を観ると、まるでデジタルで編集したのかと思うような緻密な編集が施され、フィルムの色調も作品ごとに凝った作り込みが行われていることに驚かされる。なかでも『おとうと』(1960) は、東京現像所によって画期的な現像技術が用いられた作品として知られている。
幸田文原作の「おとうと」は、「婦人公論」1956年1月号から翌年の9月号にかけて連載され、同年に単行本が刊行された。幸田の自伝的小説となる本作は、大正時代末期の東京の下町を舞台に、勝ち気な弟が結核に倒れ、その面倒をかいがいしく看る姉が描かれている。
幸田の前作「流れる」が成瀬巳喜男監督によって東宝で映画化(1956)されたように、「おとうと」も松竹での映画化が早々に決定していた。大映と専属契約を結んでいた市川も映画化に意欲を持っていたが、映画会社との壁に阻まれ、指をくわえるしかなかった。
ところが、松竹での映画化は遅々として進まず、遂に映画化権が手放される。そこで市川は大映に権利を取得するように働きかけるが、内容が暗いといった理由で会社側の反応は芳しくない。そうこうするうち、東宝傘下の東京映画が権利を取得してしまう。だが、ここでも映画化は見送られる。すでに書かれていた水木洋子による脚本がシナリオ専門誌に掲載され、それを読んだ市川は、その脚色の素晴らしさもあって、いっそう映画化に執着する。その後も東映が手を挙げるなど、各映画会社が興味を示しつつも二の足を踏むうちに、ようやく市川が権利を獲得する算段がついたことから、大映を説得し、1960年にようやく映画化が実現することになった。
主演は岸惠子、その弟役に川口浩、両親役は森雅之と田中絹代である。
市川崑と宮川一夫
1960年の市川崑は、絶頂期と呼ぶに相応しい八面六臂の活躍をみせていた。三島由紀夫原作の「金閣寺」を映画化した『炎上』(1958)の頃から文芸作品の映画化に突出した才を見せ始め、単に原作をダイジェストにして映画にするのではなく、独自の映像美学を軸に原作を解体・再構築することによって、映画ならではの表現を充満させた作品を連発していた。
大映京都撮影所で初めて撮影することになった『炎上』では、市川は名キャメラマンの宮川一夫を指名。以降、『鍵』(1959)、『ぼんち』(1960)、『おとうと』、『破戒』(1962)、『ど根性物語 銭の踊り』(1964)、『東京オリンピック』(1965)と7本にわたってコンビが続くことになる。
映像技巧に長けた2人は、白黒作品では色彩を感じさせ、逆にカラー作品では色を感じさせないようにするというアンビバレントな試みを見せている。
たとえば『炎上』では、金閣寺(劇中では驟閣寺)が炎上するのを主人公が裏山から見上げるカットで〈色〉を感じさせる。撮影時に金粉を空に吹き上げ,光を当てて撮影することで、本物の炎を撮るだけでは映らない美と色をフィルムに定着させたのだ。
また、本作ではロケーションも曇天を狙って撮影され、さらにNDフィルターをかけることで空を暗くさせて沈鬱な雰囲気を作り出している。崖の上に主人公が立つシーンでは、崖に噴霧器で墨汁を撒き、黒々とした威容を生み出すなど、カメラのフィルター処理や、撮影現場で手を加えることで、現実とは異なる陰影をフィルムに焼き付けている。
谷崎潤一郎原作の『鍵』はカラーで撮影されたが、出演者たちは死人のようなメイクを施され、色を感じさせないくすんだ色合いで日本家屋が撮影されるなど、ここでも色へのこだわりがうかがえる。
世界初の 「銀残し」
市川崑×宮川一夫のコンビとしては4作目となる『おとうと』で、2人は色彩への大胆な試みに挑むことになる。この作品で市川は、大正時代を色彩で表現してみようと思いつく。それは次のような理由からだった。
「明治は外国の文化を取り入れて未来に大きなイメージをいだいた時代でした。昭和は、今日につながるなまなましさに満ちています。大正はその間にはさまれた、暗い、無風状態の一時代ではなかったでしょうか」(「キネマ旬報」60年11月下旬号)
そこで大正を舞台にした『おとうと』では、色彩を抑え込むことで時代色を出そうとした。その意図を受けて、宮川は「採光の悪い室内は勿論、室外でも色を殆んど感じさせない、つまり黒白の中に淡く色が感じられるといったもの」(「映画技術」60年6月号)と、色彩のイメージを具体化させていった。
もっとも、この表現を突きつめようとすれば、これまでのようにカメラにフィルターをかけたり、照明で陰影を付けるだけでは限界がある。撮影後の現像処理によって、モノクロとカラーの配分をコントロールするような方法を編み出さねばならない。
こうした映像効果の前例としては、ジョン・ヒューストン監督が『白鯨』(1956)で、銅版画のイメージを基に、カラーから色を抜いた映像を作り出している。こちらはテクニカラーの現像方式を用いて、3本の黒白ネガを装着するスリー・ストリップ・キャメラを用いて撮影し、シアン、マゼンタ、イエローの染料を転染する手法が取られている。
『おとうと』では、現像を担当する東京現像所に対して宮川は、「全体は白黒に多少色彩を感じる程度で、狙った色彩だけは鮮明に表現する方法はないか」(「映画テレビ技術」99年11月号)と相談を持ちかけた。応対したのは、『鍵』のタイミング(ネガからプリントを作成する際に、1カットごとに明るさや色の調子を整える)を担当した當間章雄である。その腕を買われて東洋現像所(現IMAGICA)からスカウトされたという経歴を持つ當間は、宮川と意見交換を行い、カラーポジフィルムの現像工程の中で、銀を洗い流す工程を省く〈銀残し〉が用いられることになった。
とはいえ、この手法で狙った効果が直ちに出たわけではなく、試行錯誤が繰り返されることになった。當間によると、「実際にテストに取りかかってみると、色調の問題、コントラストの問題など、頭の中で考えていたほど簡単には進まず、フィルムの種類を変えたりしている間に1ヵ月近い時間が経ってしまった」(「映画テレビ技術」99年11月号)という。
具体的なテストがどのように進められたかを、宮川が語っている。
「最初はアグファのネガでテスト、次に同じアグファのポジでテストしたがセットの部分は良好な結果が得られた。ロケの部分は暗部を多くして行ったが、標準露出だと大変にむづかしい状況だった」(「映画技術」60年10月号)
こうしたテストを行うなかで、當間は「現像」と「漂白」の時間を調整して銀残しを行うのではなく、焼付と現像時間を調整することで狙いに近づくことを発見する。漂白の工程を飛ばし、現像時間は通常の半分以下の時間にすることで、宮川が狙う「黒白の中に淡く色が感じられる」色彩が生まれた。

大映社長・永田雅一の反対
短期間で銀残しの技術を確立したことに、宮川は「東京現像所側の努力は非常なもの」(前掲誌)と絶賛したが、そこに至るまでには、技術的な問題以外にも、様々な事態が起きていた。
まず、東京現像所社内の問題である。前述したように、銀残しを行うためには現像システムを組み替えて対応せねばならない。つまり、銀残しを行う現像機は専用機となってしまうため、製作期間中は、通常の現像に使用できなくなる。当時、東京現像所にはアグファカラーポジの現像機は3台あったが、その内1台を『おとうと』が占有することは、会社の運営においても大きな問題を孕んでいた。大映との話し合いで、どうにか問題は解決したが、次は大映社長の永田雅一の爆弾発言が、銀残しの存亡を危うくさせる。
テスト撮影した銀残しのフィルムを15分ほどにまとめて大映本社へ運び、永田社長に見せることになった。當間によると、銀残しの説明を受けた永田は試写を見ることもないまま、こう言ったという。
「“貴重なカラーフィルムを使って白黒映画を作るのなら、白黒フィルムで撮影すればよいではないか”というような発言が飛び出し、テスト撮影が終わると今度は監督とキャメラマンが姿を消してしまった」(『映画テレビ技術』99年11月号)
永田の発言もさることながら、市川崑と宮川一夫が不意に姿を消したという記述が驚かせるが、これは永田の発言を受けてのボイコットである。撮影を目前に控えた時期に監督とキャメラマンが不在になると、製作準備はストップしてしまう。困惑した大映は、どうにか永田にテスト撮影したフィルムを見せたところ、態度が豹変した――「面白いやないか、存分にやれ!」(「映画テレビ技術」92年11月号』)。
コロリと言うことが変わったのは、監督とキャメラマンのボイコットを気にしたというより、銀残しの映像を面白がったからだろう。アグファカラー、イーストマンカラーをいち早く導入し、「大映カラー」の統一名称を用いて色彩映画を積極的に展開させた永田は、こうした試みを一度理解すれば、あとはスタッフを信用し、撮影に口を出すこともなかった。急転直下、事態が解決に向かうと、市川と宮川は揃って姿を見せたという。
銀残しのための撮影
銀残しといっても、現像での処理のみに頼り切るわけではない。充分な効果を出すためには、撮影現場で丁寧にライティングを行って質感を出し、ディテールを浮き立たせた上で、現実の色が現像後にどう変化するかを見極める必要がある。美術助手で付いた井上章によると、壁や板の色がどう写るか、テスト撮影の結果に一喜一憂したという。実際、壁に本漆喰を使ったり、病室の壁は油を塗って汚すなど、銀残しの結果を見越して作業が行われた。
ロケーションでは、前述した『炎上』と同じように、現実の色を変えることも行われている。撮影時にはグレーの塗料とバケツが常備され、木の葉にコンプレッサーで吹き付けるなど、撮影段階で相殺したい色をモノクロに近い色に変えることで、銀残しによる画面効果を高める方法が取られた。また、堤防のシーンや街などで撮影する際は、あらかじめ色が氾濫する場所は避けられた。
反対に、特定の色を強調する際も、現場での色のコントロールが不可欠だった。強調されたのはケシの花、インクなどの赤だったが、市川崑と宮川一夫は、映画の後半で岸惠子が、髪を島田(髷)に結い、赤紫の着物をまとって病室の川口浩を見舞う場面に特にこだわった。このとき纏っている赤紫の着物の発色は困難を極めた。どうしてもくすんだ色合いになってしまうため、テストを重ねに重ねて、ようやく狙った赤紫を出せるようになったが、それは透けるような薄いピンク色に近い着物を着て撮影し、銀残しの処理をすることで可能になった発色だった。
こうして世界初の銀残しによる画期的な色彩によって生まれた『おとうと』は、1960年度の映画賞で『悪い奴ほどよく眠る』『笛吹川』『秋日和』『裸の島』『豚と軍艦』などの強豪作品を抑えて、キネマ旬報ベストテン第1位をはじめ、毎日映画コンクール日本映画賞、監督賞、撮影賞、女優主演賞など、この年の映画賞を総なめにした。また撮影、照明、美術などの技術スタッフも高く評価され、日本映画技術賞選奨として「劇映画部門・ラボ技術=東京現像所」を受賞している。

フィルムとデジタルで復元される『おとうと』
『おとうと』が公開されてから63年――その後、ハリウッド映画でも「ブリーチ・バイパス」「スキップ・ブリーチ」といった手法を用いた銀残しは多用されており、『セブン』(1995)、『プライベート・ライアン』(1998)などでも、その効果を観ることができる。
だが、『おとうと』の銀残しを再現しようとすると、当時とは製造されているフィルムも現像環境も異なっているため、完全に再現することはできない。スキップ・ブリーチという、現像工程で銀を落とす工程を省略する手法が『おとうと』の手法に当てはまるが、今ではフィルムの銀の量が半分になっており、そのままでは同じ効果が出ない。
近年、東京現像所が『おとうと』の銀残しニュープリントを作成した際は、カラー現像の工程にモノクロ現像を加えることで調子を合わせたが、これは、『おとうと』に続いて東京現像所が銀残しを行った映画『親鸞 白い道』(1987)で用いた現像機が現役で稼働していたことと、当時、タイミングを担当した當間章雄のタイミングデータが残っていたことが幸いした。ニュープリント作業を担った東京現像所映像部(当時)の馬渕愛は、「銀量・硬さ・脱色具合・粒状性と大きくはこの4つをポイントに何度もテストを繰り返し、硬さに関してはオリジナルの硬さがそのまま出るように努力しました」(「映画テレビ技術」2010年2月号)と語る。
なお、現在、Blu-rayで発売されている『おとうと』は4Kデジタル修復されたもので、IMAGICAがデジタル上で再現した擬似的な銀残しであり、現像処理によるものではない。だが、現在の現像技術では不可能な色調を再現することも可能なだけに、フィルムからデジタルという大きな変革の波のなかで、〈『おとうと』と銀残し〉は、フィルム時代の終焉と技術の継承、そしてデジタルの可能性を示唆する作品と言えよう。
最後に、『おとうと』の予告編で冒頭に掲げられた永田雅一の言葉を引用しておこう。
「革新的な色彩映画に成功いたしました 私達はそれを皆様に自信を以てお目にかけることが出来るのを大変喜ばしく思います」
この自信に満ちた言葉を裏打ちしたのが、東京現像所だった。
文 / 吉田伊知郎
写真協力:株式会社KADOKAWA
【参考文献】
「映画技術」「映画撮影」「映画テレビ技術」「キネマ旬報」「季刊リュミエール」「キネ旬ムック 光と影の映画史 撮影監督・宮川一夫の世界」(キネマ旬報社)、「キャメラマン一代 私の映画人生60年」(宮川一夫 著、PHP)、「映像を彫る 改訂版 撮影監督 宮川一夫の世界」「市川崑の映画たち』(市川崑、森遊机 著、ワイズ出版)、「映画唯物論宣言」(三隅繁 著、樹花舎)、「市川崑 4K Master Blu-ray BOX』(KADOKAWA)、「キャメラも芝居するんや~映画キャメラマン宮川一夫の世界~(NHK、1993年10月8日放送)、「映画カメラマン 宮川一夫 没後10年世界がみとめた映像の技」(NHK、2009年8月24日放送)

株式会社東京現像所 (TOKYO LABORATORY LTD.)
所在地:本社 東京都調布市富士見町2-13
1955年、東宝・大映・大沢商会など、映画関係各社の出資により設立。2023年11月30日に全事業を終了。

映画『おとうと』 4K Master Blu-ray
これは人間の魂のふるさとの物語です。“家”というものは父性愛、母性愛、夫婦愛、姉弟愛で成り立っているといわれていますが、どんなに愛し合っていても人間は孤独です。孤独を前提として、いたわり合って暮らしているから、その愛情が美しいのだと思います。――市川崑(公開当時のプレスシートより)
げんと碧郎は、時には本気で喧嘩もするが仲の良い姉弟。厳格な父と病気がちの継母は小言ばかりで、碧郎はそんな家庭の雰囲気に反発するかのように万引き騒動を起こしたり、ボートや乗馬、ビリヤードに興じて姉のげんをいつも困らせた。2年後、碧郎の身体を結核が襲う。病室に付き添い、懸命に看病するげんに、碧郎はある願いを口にする‥‥。
監督:市川崑
出演:岸恵子、川口浩、田中絹代、森雅之、仲谷昇、浜村純、岸田今日子
発売・販売元:株式会社KADOKAWA
© KADOKAWA 1960
発売中
商品サイト:https://www.kadokawa.co.jp/product/video503/