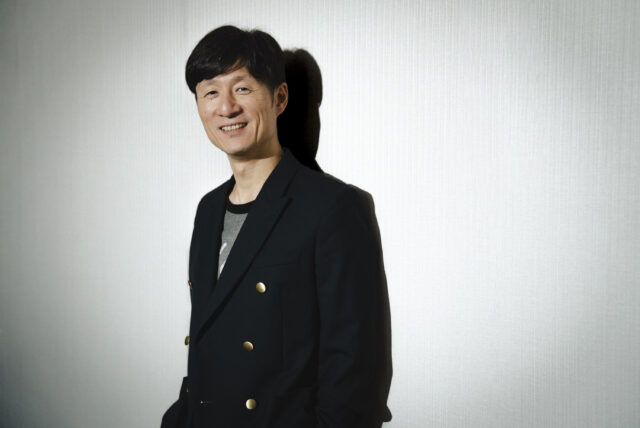フェイクニュースが戦争を招いた!? ロブ・ライナー監督の新作映画『記者たち~衝撃と畏怖の真実~』はイラク戦争開戦時の米国メディア界の内情を描いた実録サスペンスだ。9.11同時多発テロ後のブッシュ政権は「イラクは大量破壊兵器を保有している」と断定。米国の大手メディアはこれに同調し、イラク戦争へと雪崩れ込んだ。このことに反対した新聞社は、ナイト・リッダー社だけだった。本作の字幕監修を手掛けたジャーナリスト・池上彰氏が、記者視点からの見どころと現在も進化し続けるフェイクニュースの恐ろしさについて語った。
【前編】は こちら
何度断られても取材を続ける記者魂
──池上さんならではの『記者たち』の見どころはどこでしょうか?
ぜひ注目して観てほしいのは、記者と情報源との取材のやりとりですね。米国人って尋ねると、結構しゃべってくれるんです。それに対し、日本の政治家や官僚はなかなかしゃべってくれません。国民性の違いでしょうか。米国の記者たちのほうが取材はしやすそうですね(笑)。ウディ・ハレルソンが何度も電話でコメントを求めて一方的に切られてしまうシーンが繰り返されるところはとてもおかしいんですが、実際に取材ではああいうやりとりが多いんです。“勘を取る”と呼んでいます。コメントを取ることはできなくても感触はつかめるわけです。真っ向から否定するのか、それとも否定はせずに黙っているだけなのか、そういった微妙なニュアンスを感じ取るわけです。そういう取材のやり方もあるんです。

──コメントを取るだけが取材ではない?
そうなんです。『大統領の陰謀』(76年)という映画がありましたよね。ワシントン・ポストの記者たちがニクソン大統領を追い詰める実話サスペンスでした。記者役のダスティン・ホフマンが重要な情報源に電話で真相を確認するんですが、「俺は答えられない」と相手に断られてしまいます。そのときに「答えなくていい。こちらの言ったことが間違っていれば、すぐに電話を切ってくれ。正しければ、10秒間そのままでいてくれ」と頼みます。電話の相手は10秒間黙り続け「これでいいか?」とだけ言って、電話を切るわけです。相手に「守秘義務は守った」と言い訳できる状況を用意する。これもまた記者の取材のやり方なんです。
私も地方局にいた頃、記者としていろんな取材をしました。刑事は地方公務員法に違反するので、自分がどんな事件を担当しているのかしゃべることはできません。深夜、刑事部屋に刑事と私が二人きりでいると、「今、こんな事件を担当しているんだよなぁ」と刑事は独り言っぽく言いながら捜査資料を机の上に出して、トイレへ行くんです。もちろん、私は資料を開きます。刑事にしてみれば「記者が勝手に見た」と言い訳できるわけです。記者っていろんな取材のやりとりを経験するものなんです。
──取材相手との間に信頼関係があるからこそですね。
もちろんです。どこで情報を入手したかをペラペラと口にするようなことは決してしません。ウディ・ハレルソンが情報を握る女性に、同僚からバカにされながらも諦めずに何度も食らい付いていく。そういうところは、すごくリアルだなぁと思います。