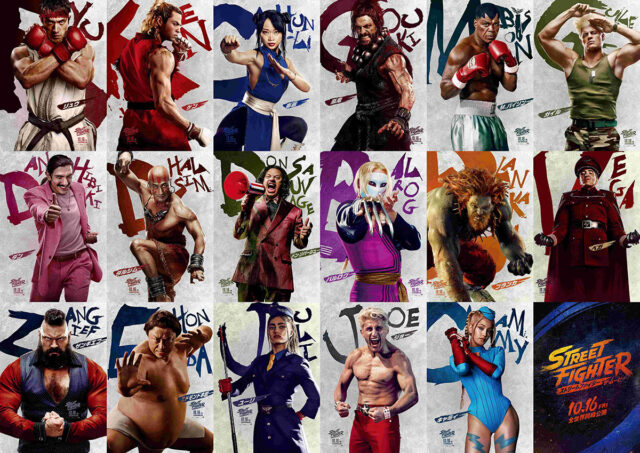大きなところから俯瞰視したものを見せている
──カイラートの背景は細かく描かれていませんが、森山さんは監督から彼の過去に何が起きたのかをお聞きになったのでしょうか?
彼が劇中に登場するまでの背景はもちろんあります。監督のエルラン(・ヌルムハンベトフ)と(竹葉)リサさんと話をする中で、カイラートが登場する理由も教えていただきました。ただ、それは劇中では描かれないのでここではあえて言いませんが(笑)。

──とても気になりますが我慢したいと思います(笑)。観る人が自由に想像できる部分でもありますしね。
そうですね。台詞含めて明確な背景は明かされませんが、彼が登場するまで、または登場したあとに彼自身が積み上げてきたものの匂いみたいなものが何かしら観客には伝わるのではないかと。カイラートだけでなく作品全体の時代背景もそこまで限定していません。だからこそ普遍性が増したようにも思うんです。そうしたことによって「もしかしたらカザフスタンの民間伝承の寓話なのかな?」と思えたりもするので、そういう匂いも持っているような気がします。

──“寓話”というワードがとてもしっくりきました。もちろんちゃんとしたストーリーはありますが、説明的な作品ではないですよね。
ストーリーや台詞といったものに重きを置いた作品ではないと思います。登場する人たちの人間関係があって、そこで交わされる言葉は必要最低限なことしか出てきません。現象も淡々としていて、大自然やとにかく大きなものに人間が取り巻かれていくような感じというか。もちろん人間同士のいざこざや事件も描かれていますが、もっと大きなところから俯瞰視したものを見せているようにも思います。先ほどカイラートについてエルランやリサさんと話したと言いましたが、その内容を自分の中に落とし込みつつ、だけどこの作品が切り取っているのはそこじゃないと感じながら立っていました。

──実際に起きた事件をモチーフに作られてはいますが、ある場面ではファンタジーっぽさもすごく感じました。
先ほど寓話と言いましたが、日本の神話にも通ずるものがあると感じます。例えば、ギリシャ神話やギリシャ悲劇だと教訓めいたものが絶対に入っていますよね。「どうこうしたらこんなことが起きてしまいますよ」という教訓を込めつつ荒唐無稽な話になっていたり。だけど日本の神話は教訓めいたものがあまり成立してないように思うんです。
『古事記』に収められている神話の『因幡の白兎』を読んでみると“嘘をついてはいけない”という教訓が込められているのかと思いきや、嘘をついた兎は大国主命の尊に助けられてちょっとうやむやになって終わりますから、なんやねん! と(笑)。今回の映画の邦題タイトルは『オルジャスの白い馬』(オルジャスは主人公の少年の名前)なので、それはきっと子どもにフォーカスして観て欲しいということだと思うんです。母と子の関係性も含めて。僕は原題の『Horse Thieves』という客観的な視点でこの作品を観ましたが、邦題はより観客に寄り添ったタイトルになっているのではないでしょうか。