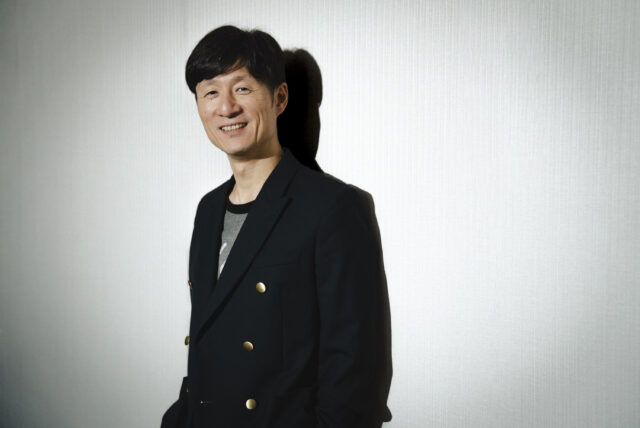映画監督は職業ではない
──『麻雀放浪記』の坊や哲はドサ健や出目徳といった強烈な個性を持った“師匠”たちと出逢い、たくましく成長していくことになる。白石監督の「映画放浪記」についても語ってもらえればと思っています。
北海道から東京に上京し、映画監督の中村幻児さんが主宰していた映像塾に通うようになり、そのとき僕の師匠となる若松孝二監督に声を掛けられて映画の現場に参加するようになったんです。僕が20歳くらいの頃に出会った人たちは、坊や哲が出会ったのと同じくらいおかしな人たちばかりでしたね(笑)。当時の若松さんは松竹系で公開された『エンドレス・ワルツ』(95年)などを撮った頃でしたが、やっぱりメジャーの本流ではない道を進んでいるアウトロー感がすごくありました。「映画放浪記」と言われましたけど、映画業界で働く人間はみんな放浪生活をずっと続けているようなものなんです。他にもいろんな監督の現場に助監督として参加しましたが、若松プロという小さいながらも帰れる場所があったことは僕にとってはすごく大きかったと思います。

──助監督時代は映画だけで食べていくのは難しかった?
現場があるときは若松さんから給料をもらっていましたが、撮影がないときは給料はありませんでした。それで深夜営業のファミレスでバイトしていたんです。夜9時から朝6時まで働いて、アパートに帰って少し寝て、毎朝11時くらいに若松プロに顔を出していました。若松さんがいるときは一緒にワイドショーを見て、若松さんがゴルフに出掛けているときは留守番しながら事務所にある本を読んだり、若松さんの昔の作品のビデオを見たりして過ごしました。ワイドショーを一緒に見ることで、若松さんが社会をどう見ているのかとか分かるようになりました。若松プロは映画関係者以外のお客さんも多かったですね。若松さんは後に『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』(08年)を撮りますが、公安からのガサ入れもありました。『孤狼の血』などのガサ入れシーンがリアルに描けたのは、僕自身が体験したことを再現しているからなんです(笑)。

──白石監督の作品を観ていると「この監督、腹を括っているなぁ」と感じます。
自分は映画監督にはなれないと思っていたんです。僕の監督デビュー作は『ロストパラダイス・イン・トーキョー』(10年)というインディーズ映画なんですが、たまたま次の『凶悪』に繋がった。でも実録犯罪ものなので、世間に広く受け入れられるとは思いませんでした。なら、最後の一本のつもりで自分の好きなように思い切って撮ろうと。それはいつも思っていることなんです。映画監督って職業だとは考えていませんから。人気商売でもあり、そうそうずっと撮り続けることはできないものです。だからこそ1作1作やりたいことをやるようにしています。若松さんと盟友関係だった大島渚さんは『愛のコリーダ』(76年)など多くの問題作を監督しましたが、「映画はスキャンダルでなくちゃダメだ」と言っていました。大島さんのその言葉は、僕の意識の中に今もあるように思いますね。
──大島監督や若松監督の作品に流れていたスキャンダリズムを、白石監督は受け継いでいるようですね。
だからといって、今回の炎上騒ぎは狙ったものじゃありませんよ(笑)。若松さんとの思い出でいえば、『南京1937』(95年)という香港・中国映画を若松プロが日本での配給をすることになったんです。南京事件を扱っているために若松さんは右翼団体と話し合うことになりました。「若松さんに何かあったときは、俺が盾にならなくちゃいけないな」と覚悟しました。結局、心配したようなことは起きずに済みましたけど(笑)。そんな若松さんへの想いを込めて、若松さんたちの青春時代を描いた『止められるか、俺たちを』(18年)は撮ったんです。(若松プロ出身の)荒井晴彦さんが編集長を務めている「映画芸術」では2018年のワースト1位に『止められるか、俺たちを』が選ばれました。とても愛のあるワースト1位だったと感じています(笑)。