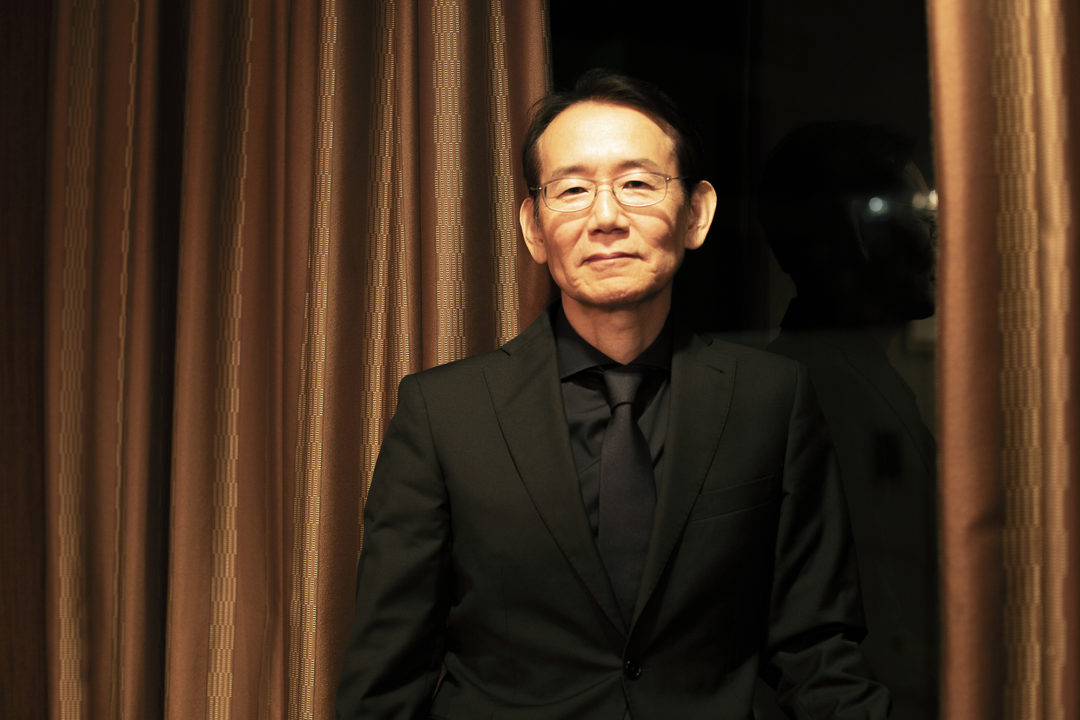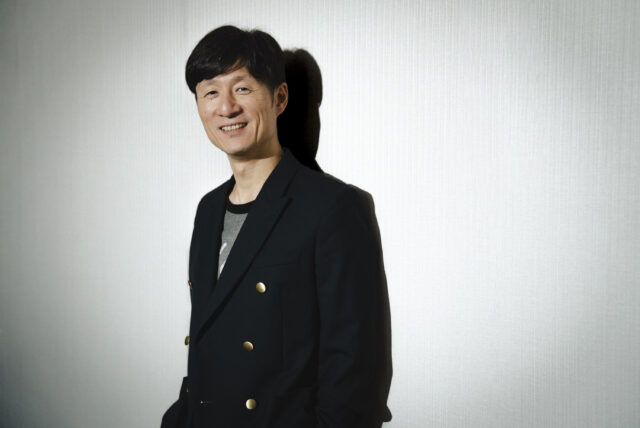ベテラン助監督がコツコツと書き上げた労作
――片島さんは、周防監督作品をチーフ助監督として長年支えてきた方。
大変な売れっ子助監督です。忙しい仕事の中で、コツコツと脚本を書き進めてきた。なかなかできることではありません。『舞妓はレディ』のころに、片島さんのシナリオを読ませてもらい、「これはおもしろい映画になる」と周囲に話していたところ、「そんなにおもしろいと思うなら、監督しませんか」とプロデューサーから言われ、僕が撮ることになったんです。

――ナイーブなことをお訊きしますが、片島さんはご自身で監督したいというお気持ちもあったんじゃないでしょうか。
おそらく、そうだったと思います。片島さんが「周防さんが撮ってくれるなら」と映画化をOKしてくれたことで、実現した企画です。シビアな話になりますが、今回の『カツベン!』は時代設定もあり、かなり予算を使うものでした。実現させるのが難しい企画だったんです。片島さんも、僕に任せたほうが映画化しやすいと考えたんじゃないでしょうか。そこは片島さん本人に訊いてみないと分かりません。でも、その分、僕はプレッシャーも感じました。おもしろい映画に仕上げないと、苦労してシナリオを書き上げた片島さんに申し訳ありませんから。

――ご自身で脚本を書かれてきた周防監督にとって、ほかの人の書いた脚本で映画を撮るのは初めての体験だった。
『カツベン!』を撮る上で、自分で決めたことがふたつあります。片島さんの才能を多くの人に知ってもらうためにも、必ずおもしろい映画にしようと。もうひとつは、脚本には自分で手を加えないということです。もし、脚本をいじる必要が生じた際は、必ず片島さんに相談して、片島さんの手で直してもらうようにしました。
それで、ある時、活動弁士が映画に活弁をつけることに疑問を抱くシーンが欲しいと感じました。そのことを伝えると、片島さんはベテラン弁士の山岡秋聲(永瀬正敏)が悩むシーンを新たに作ってくれたんです。「映画はそれだけでできているんじゃないのか。そこに俺たちは何を付け加えることがある?」というようなことを伝える秋聲の台詞がありますが、これは秋聲の一部モデルとなった実在の弁士・徳川夢声の言葉です。片島さんは徳川夢声のエッセイから引用して、秋聲の台詞を書いたんです。当時の弁士たちの中には映画と向き合ううちに、自分たちの説明は映画のためになっているのかと疑問を感じる人もいた。大衆のための単なる見世物だった映画が、ひとつの表現として、芸術として発展していく、その流れを感じてほしかった。片島さんの筆が生み出したからこその作品です。