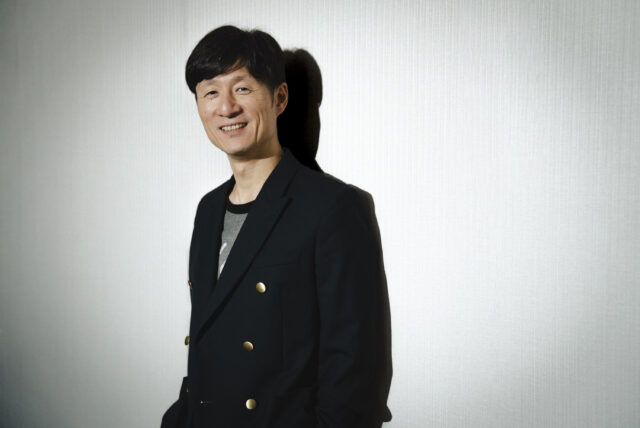社交ダンスブームを巻き起こした『Shall we ダンス?』(96年)、刑事裁判を題材にした『それでもボクはやってない』(07年)、京都を舞台にしたミュージカル映画『舞妓はレディ』(14年)など、ユニークなテーマで毎回話題を呼ぶ周防正行監督。5年ぶりとなる新作『カツベン!』は、映画黎明期の日本で活躍した活動弁士たちを描いた娯楽作となっている。リサーチにじっくり時間を費やすことで知られる周防監督に、活動弁士の魅力について語ってもらった。
無声映画をそのまま観ている人はいなかった
――“しゃべくり道中”と称して全都道府県を行脚し、『カツベン!』の宣伝に努めてきた周防監督。すっかり、語り尽くしたんじゃないでしょうか。
いやいや、しゃべることは大事です。言葉にすること、人に話すことで、より客観的になり考えをまとめることができますから。いろんな媒体の方たちから取材を受け、それに答えることで、自分のやってきたことを俯瞰して見つめることができるようになってくるんです。全国を回り、僕のしゃべりも少しずつ芸の域に近づいているかもしれません(笑)。

――活動弁士は、日本だけで花開いた独自の文化。しかも、隆盛を誇ったのは、明治末から、大正、昭和初期の約30年間。サイレント映画からトーキー映画へと変わり、多くの活動弁士たちは消えていった。そんな活動弁士のどこに周防監督は惹かれたんでしょうか?
『それでもボクはやってない』から助監督を務めてくれていた片島章三さんの書いたシナリオを読ませてもらったことが、きっかけでした。片島さんのシナリオを読んでいなかったら、いまでも活動弁士のことは無視したままだったと思います。僕は学生時代にかなりの数の無声映画を観ていました。映画が好きでしたから、京橋のフィルムセンター、いまの国立映画アーカイブに通い、映画が活動写真と呼ばれていたころの監督たちの技術を知りたかったんです。その時は弁士も音楽も付いていない無声映画を無音のまま観ていました。サイレント映画として作られたのだからサイレントのまま観るのが正しいと思っていたんです。でも、片島さんのシナリオを読んで、考えを改めました。どの無声映画にも弁士が付き、弁士が独自に考えた台本で映画を解説していた。さらに、生演奏の音楽もあったわけです。もちろん映画監督もその上映スタイルを承知したうえで撮っていた。当時、サイレント映画をサイレントのまま観ている人は誰もいなかったという当たり前のことに、ようやく気づいたんです。

――黎明期の映画が多くの人たちを熱狂させていた、本来の姿を知ったわけですね。
そうです。映画監督になってからも、ずっと活動弁士の存在は無視したままでした。シナリオを読んで、こりゃあ、弁士のことをもっと知らなくちゃいけないなと。それで、『カツベン!』を撮ることで弁士についてもっと深く知ろうと思ったんです。もちろん、片島さんの書いたシナリオが魅力的だったことも大きかった。弁士たちの物語を、まるで活動写真のようなスタイルで描くというシナリオだったんです。これはすごいと思いました。