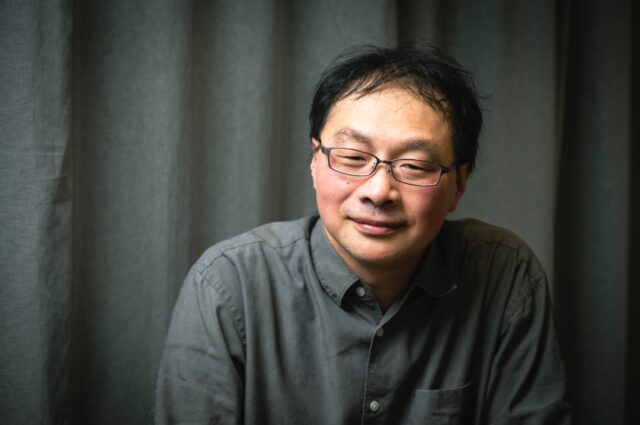―― この作品は3つの問題への勘案を勧める作品だと思いました。1つめは、家族の理解を得るのは難しいということ。2つめに老後の住む場所やどう生きるかという問題。3つめは2つめの問題と密接にかかわるものですが、介護の問題。本作で描かれるこの3つの問題は、全世界の人が少なからず直面するものでありながら、いまだよい解決方法が見つかっていません。身につまされます。
その通りです。ただ、この映画の舞台が東京やパリ、アムステルダム、ロンドン、ニューヨークのような大都会であれば、もう少し違ったものになっていたかもしれません。この映画は南仏の地方都市を舞台にしているので、保守的であること、カトリック信仰という背景、そして近隣の目など、都会に比べてニナたちの行動を阻むものが多いからです。
おっしゃるように家族についての問題は、人それぞれですが尽きないものです。子どもは両親に対して期待を寄せがちで、自分の親は特別だと思い込む傾向があります。例えば、マドレーヌの娘。彼女の年齢ならゲイ、あるいはレズビアンであることを特別だと捉える世代ではないでしょう。けれど、自分の母親は別。母親がレズビアンであるのは許せないわけです。つまり、両親に対して子どもが持っている特別の期待感が一般的な判断力を奪うわけです。
そして介護。マドレーヌが梗塞の発作を起こした背景には、ニナとの関係を隠していたストレスもあると思います。「隠しごと」は病気になる“12の原因”のひとつですから(笑)。この映画は確かにそれらの問題を描いており、それぞれの問題を引き起こす背景も提示しています。

―― ニナが抱えるそれらの問題について、役を作る上で解釈すると思いますが、どの段階でどんなふうに確定させるのでしょうか?
テーマによっては、撮影をしながら見えてきたこともありますし、撮影に入る前から考えていたこともあります。子どもたちの考え方については、撮影準備をしている段階でだんだん掴めてきた感覚がありました。要するに、人はなぜそう考えるに至ったかなど、すぐに理解できるわけではなく、役作りのプロセスの中で、また演技として状況を体験する中で、だんだん見えてくるものなのです。
ニナとマドレーヌの日常に関しては、撮影を進めていく中で考えました。2人の関係は29年続いたわけですが、その間、この人たちはどうやって会っていたのか。マドレーヌには夫がいたので気軽に会うことはたぶん叶わなかったでしょう。「買い物に行く」と言って出かけ、外で会っていたのか? 旅行に行くときはどうしていたのか? 2人が一緒に過ごす日常をかなり具体的に想像しました。
2人の間で“秘密”がどう作用したかは最大のテーマでした。例えば、法の下の夫婦であれば、長い時間をともにすることで生活はルーティンとなり、ワクワク感は失われていくように思われます。でもニナとマドレーヌには秘密があった。そのことによって冷めることなく関係が続いたのではないかと思いました。もしそうであれば、“秘密”という枷がなくなったとき、その関係性はどう変化したのか、などということも。