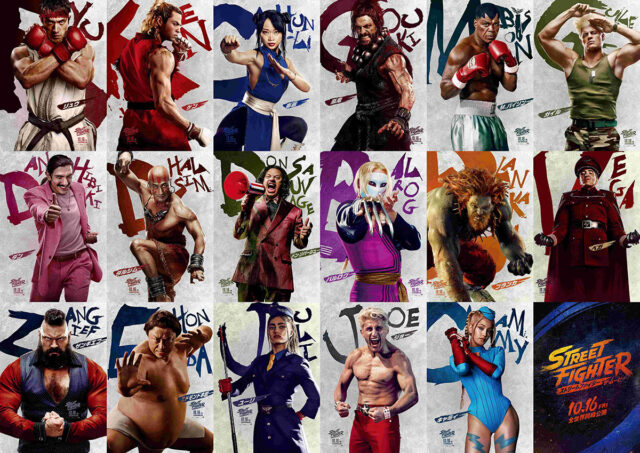常識から解放されることで見えてくるもの
――ダー子が「私たちは家族でも友達でもない」と、ボクちゃんやリチャードたちとの関係性をクールに語るシーンはとても印象に残っています。これって、古沢さん自身の人生観でもあり、ドラマ制作における脚本家・演出家・キャストとの関係性を物語っているようにも感じられます。
う~ん……。『コンフィデンスマンJP』って、友情とか家族の絆とか夫婦や恋人たちの恋愛感情とか、そういった世間で認められている関係性を疑ってみるというか、そういう関係性だけじゃないんじゃないのかということをテーマとして描いてみたいというのがありました。常識とされているものをまず疑ってみようと。友達だからとか、家族だからという言葉ほど信じられないものはないと思いませんか。そんなものは最初から信用していないのが、ダー子たちなんです。でも、だからこそ常識ではない、特別な繋がりがあるんじゃないのかと僕は思うんです。常識や決まり事を一度取っ払わないと見えてこないものもある。目に見えるものが真実とは限らないし、常識に囚われていると本当のものは見えてこないよ、というテーマが描ければいいなと思いながら書いていたドラマなんです。

――古沢さんの代表作である映画『キサラギ』(07年)や『外事警察 その男に騙されるな』(12年)、それに『リーガル・ハイ』(12~14年/フジテレビ系)などを振り返ってみると、主人公たちは不確かな存在というか、「この主人公を信用してもいいのかな?」と視聴者や観客すら不安を覚えるキャラクターであることが多いように思います。『コンフィデンスマンJP』のダー子たちと通じるものを感じるんですが、意図的なものでしょうか?
常識とかモラルを疑うというキャラクターを僕が好きなんだと思います。僕が書く脚本にも、そんなテーマをなるべく盛り込みたいんです。そのせいかもしれませんね。それに今、挙げられた作品の主人公たちのキャラクター設定というか履歴を、はっきりとは作っていないんです。それもあって、不確かな感じがするんだと思います。それに加え、僕自身が僕の生み出したキャラクターのことをあまりよく知らないんです。というか、そういう関係性でいたいんです。
――自分の創作したキャラクターは、いわば自分の分身ですよね?
もちろん分身は分身なんですが、でも他人でもあるわけです。その人のことを僕はすべて知っているわけではない。特に最近の僕が書くオリジナル作品は、そういう傾向が強く出ているかもしれません。よく「君のことは分かっている」みたいに話す人がいますが、そういうふうに言われるのが僕は嫌だし、そんなふうに話す人のことも嫌なんですよ。

――いますね。一方的に他人にラベルを貼って、ジャンル分けしてしまう人。
僕は言われがちなんです(笑)。子どもの頃から、それがすごく気になっていました。「そんな人だと思っていなかった」とか「あっ、そんなことするんだ」とか。親から言われるのも嫌なんです。親って「あんたは私の子なんだから、私にはよく分かる」みたいに言いますけど、絶対に子どものこと分かってないじゃないですか(苦笑)。作家とか創作活動している人は、特に言われがちかもしれません。少女を作品に出すと、ロリコンだとすぐ言われてしまう。
――コメディドラマの旗手、現代のヒットメーカーと古沢さんは呼ばれることが多いかと思いますが……。
それは言われても、気になりません(笑)。まぁ、それほどのヒットメーカーでもありませんけど。でも、人間ってそう簡単に分からないものだと思うんです。そのことは大きな前提として脚本を書いていたいなと思っているんです。