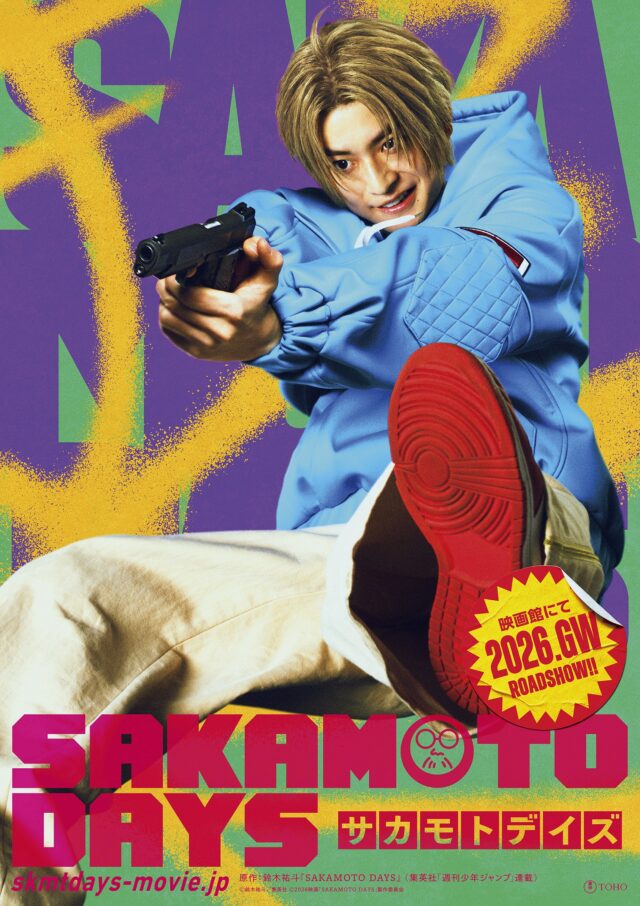フランケンシュタインの孫の物語
『ヤンフラ』は、映画『プロデューサーズ』でアカデミー賞脚本賞を受賞しているメル・ブルックスが、古典的名作小説『フランケンシュタイン』(メアリー・シェリー)を下敷きにして撮った映画版『ヤング・フランケンシュタイン』(74年)を、自らミュージカル舞台化した(2007年)もの。トランシルヴァニアにて怪物を生み出し、人々を混乱に陥れたヴィクター・フォン・フランケンシュタイン博士(宮川浩)の孫フレデリック(小栗旬)は、祖父の行いがいやで、素性を隠して、ニューヨークで脳外科医として過ごしていた。だが、祖父が亡くなり、遺産相続のこともあって、婚約者エリザベス(瀬奈じゅん)を残し、いったん故郷トランシルヴァニアに戻ることに。

トランシルヴァニアにはヘンな人ばかり暮らしている。昔、ヴィクターの作り出した怪物に襲われたことを根に持っているケンプ警部(ムロ)、いやに怪しさをふりまくアイゴール(賀来賢人)と、無駄にエロかわいい助手・インガ(瀧本美織)、祖父の代から家政婦をやっているフラウ・ブリュッハー(保坂知寿)など、強烈な個性ある人たちに、フレデリックはたじたじ。

だが、城の中で祖父の実験記録を発見し、脳外科医としての血が騒ぎだす。試行錯誤の結果、フレデリックはついに、怪物(吉田メタル)を生み出すことに成功したが、思いがけないアクシデントにより、怪物は暴走してしまい、再び村はパニックに……。
と、ここまでが第一幕。
この概要に、福田ならではのギャグがかなりたくさんプラスしてある。
小栗旬の存在感
開幕早々、ムロが、『ヤンフラ』の世界を、愉快な福田雄一ワールドに塗り替えていく。一方、しぶしぶ故郷に戻って来たら、案の定、怪しい人たちばかりに振り回されるフレデリックを演じる小栗旬のうかない表情は、ミュージカルらしからぬものがある。たいていのミュージカルは、どんなに悲しい役でも、その悲しみをはっきりした発声で明確に表現し、朗々と歌い上げるものだが、小栗旬はどこか心ここにあらずの印象がある。もともと小栗は、スカッと爽やかキャラではなく、ナイーブで屈折しているところが魅力なので、明快なミュージカル世界に馴染めないのかと思って観ていると、徐々に周囲に感化されて、楽しげに歌い踊るようになっていく。おそらく、これは、そういう計算がされているのだと思う。

前述のムロのように、福田は、観客が違和感を抱きそうな部分は、どんどん先回りして、笑いのネタにしてしまうので、小栗に関しても、彼のパブリックイメージと役との距離感を笑いとして使う。慣れないミュージカルをやるに当って不利になりそうなところを、全部フォローして、そういうものなんです、と言い切ってしまう福田雄一は、味方にしたらこれほど頼りがいのある人もいないであろう。
小栗に付き従うアイゴールとインガは、ザッツ・ミュージカルな感じで、迷いない動きをするので、小栗との差が面白い。賀来賢人と瀧本美織の演技や歌は、柔軟で明るい。怪物役の吉田メタルは、本人とわからないくらい怪物化している。

ここからややネタバレします。