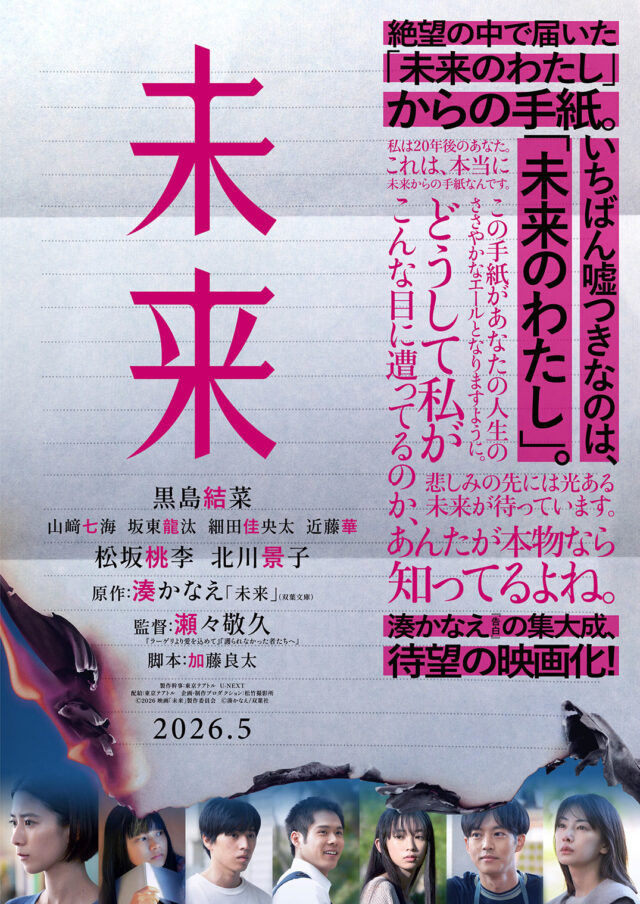映像言語で描かれた研ぎ澄まされた世界
『流浪の月』が特異なのは、小児性愛者とおぼしき大学生と誘拐された少女が再会し、関係を深めていくところにある。事件から15年が経過し、インターネット上に刻印された事件の痕跡はデジタルタトゥーとなって記憶の風化を拒み続けるものの、大人になった更紗(広瀬すず)は、恋人の中瀬亮(横浜流星)と同居しながらファミレスでバイトしている。しかし、突発的な文との再会によって、仕事も恋人も棄てて、彼の身近な場所で暮らそうとする更紗に、周囲は誰ひとりとして理解を示す者はいない。
凪良ゆうの同名原作(創元文芸文庫)には、週刊誌が報じた内容として、「被害女児は加害少年の洗脳から抜け出せないまま、今も加害少年と同じマンションで暮らしている。(中略)これは完全なストックホルム症候群であり、彼女に手を差し伸べる誰かが必要だ」という文章が記されている。また、勤務するファミレスの本社から詰問された更紗が、「隣に住んでいるのは本当です。でもストックホルム症候群とかじゃありません。相手の人も世間のみなさんが思っているような犯罪者じゃありません」と抗弁する場面が小説には書かれている。
しかし、映画では「ストックホルム症候群」という言葉は周到に伏せられており、その症状なのかどうかは、映画を観終わった観客が最終的な判断を担うことが出来るようになっている。つまり、過度な説明が付されていない。これは本作の特徴でもあり、ストーリーは、ほぼ原作そのままと言って良いが、小説と映画でこれほど印象が異なる作品も珍しい。

映画を観た後に原作を読めば、映画で点としか描かれていなかった部分の細部がすべて説明されていることに驚くだろう。逆に原作を先に読んでいれば、映画だけを観た人はこれですべて納得できるだろうかと思うかもしれない。小説は言葉によって語り、映画は映像によって語るという基本原則を行っているだけだが、今ではそうした原作小説と映画の関係は稀有なだけに、本作が突出して見えるのは、映像言語で語ることに徹したからである。
本作のストイックな映像世界では、言葉による説明を削ぎ落として映像で語ることが主軸に置かれており、演技も余計な夾雑物がどんどん削がれている。松坂桃李も広瀬すずも、限界まで装飾を剥いだかのような演技で圧倒させる。その分、横浜流星は映画の中の喜怒哀楽を一人で背負った感があり、その大役を見事に果たしている。かつて、それまではそう印象に残っていなかった松坂桃李が、『ピース オブ ケイク』の脇役あたりから目に見えて際立つようになった時期を彷彿とさせ、今後の横浜流星が大きく飛躍していくのは間違いない。

撮影監督ホン・ギョンピョが映し出す〈水と橋〉
公園のブランコに揺られる少女時代の更紗の後ろ姿をウエストショットで見せながら、ブランコに合わせてカメラが一緒に動くことで、更紗の目線の先にかすかに見え隠れする文の姿を捉えた冒頭からして、本作の映像は際立つ。続いて、雨が降り始めた公園でベンチに座ったまま濡れる更紗と、そこに傘を差し出した文を映したロングショット、次に文を見上げる更紗の顔のアップから彼女が一瞬目線を下に向ける動作へと繋げる撮影と編集の素晴らしさには感嘆せずにいられない。言葉を一切使わなくとも、彼女がその瞬間に何を決意したかが明確に伝わってくる。なぜ、この男に彼女はついていったのかという理由を映像だけで納得させてしまうのだ。これまでも李相日監督の作品は、画面の力強さでは突出していたが、『バーニング 劇場版』『パラサイト 半地下の家族』の撮影監督ホン・ギョンピョを招聘した本作では、いっそう映像が饒舌に語りだす。
その意味で言えば、本作に〈水〉というキーワードを見つけるのは容易い。冒頭の雨に始まり、川の濁流、大人になった更紗が、文と恋人が歩くのを尾行する際の濡れた路面、湖、文が経営する隠れ家のようなカフェが川沿いにあり、店内には青の色ガラスが窓枠に配置され、水底のような雰囲気を漂わせる。
しかし、それ以上に印象的なのは、〈橋〉である。映画の冒頭、公園で傘を差し出された少女時代の更紗は、次のショットで川の上に架かった橋を、文と寄り添うように歩いている姿がロングショットで映し出される。彼女は橋を渡って〈越境〉してしまったのだ。したがって、2人の世界が終わりを遂げるのは、原作では動物園で警察に保護されることになっていたが、映画では湖の桟橋になったのは必然だろう。橋が途中で途切れてしまう桟橋こそは、もうそれ以上は進むことが出来ない、現世と水の中の境界なのである。映画がどのような結末を迎えるかを記すことは出来ないが、終盤に橋が登場するかどうかで2人の未来を予想することが出来るはずである。