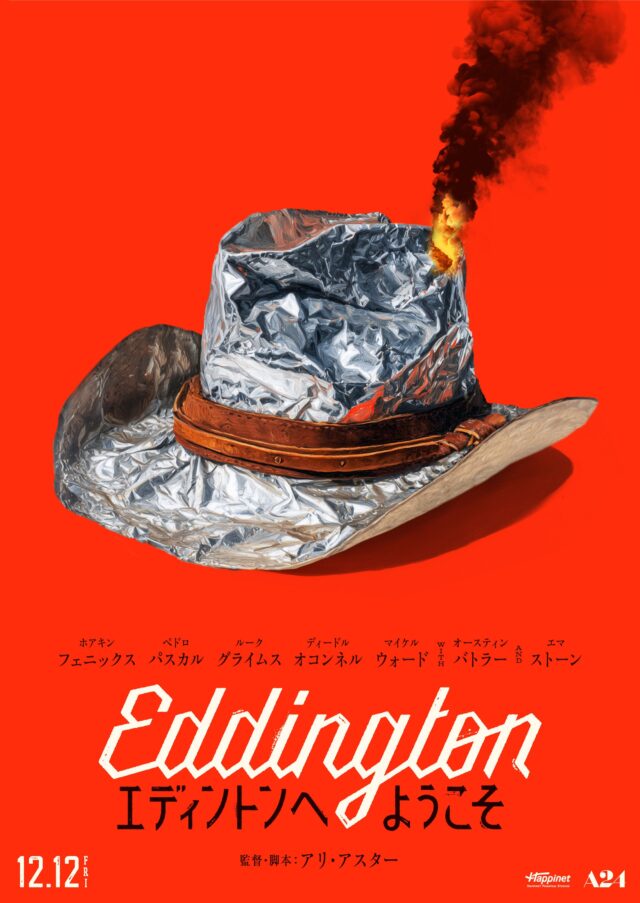一方で、ロックンロール誕生(仮に1955年として)から60数年を経た今日。ありとあらゆる人種が融合し、それにともない音楽も多種多様なものが混ざり合うことが普通になった。もはや黒人が黒人音楽だけを聴かなければならないということも、白人が白人音楽だけを聴かなければならないということもない。そもそも音楽を人種で分けることさえナンセンスになりつつある。その音楽がいいかどうか、自分の心を打つかどうか、そこに尽きてくる。
エルヴィスがかつて成し遂げたことは、ブラック・ミュージックを自分の栄養とし、自身の血と肉とし、それを彼独自のものとして世界に投げかけたということだ。そしてそのことは、50年前には理解されなかったかもしれないが、2022年の今日、十分多くの人たちに「歴史」として理解されるだろう。彼がこれだけの世界的スターになったのは、もちろん歌った楽曲がよかったことは大前提だが、やはり、あの声、あの歌唱法、そしてなにより腰を動かし体をゆらし、全身で観客に向かい合ったからだ。

ロイ・ハミルトン
映画にはでてこないが、エルヴィスがその歌唱で影響を受けたアフリカン・アメリカンのシンガーの一人にロイ・ハミルトンという人物がいる。僕は彼のことを約10年前に知ったのだが、その歌声を聴いて「黒人版エルヴィスか」と思ったほど。だが、ハミルトンは1929年4月16日ジョージア州リーズバーグ生まれ。ニュージャージー州に引っ越し、教会などで歌っていたが、1953年メジャーのエピックと契約。次々とヒットを出すようになる。
このハミルトンの歌唱は、サム・クックやエルヴィスに大きな影響を与えた。特にエルヴィスはハミルトンのバラードを気に入っていたようだ。エルヴィスの後には、ライチャス・ブラザーズがハミルトンの「ユール・ネヴァー・ウォーク・アローン」や「エブ・タイド(引き潮)」などをカヴァーする。ハミルトンの「ハート」などを聴くと、エルヴィスがいかにハミルトンの歌唱に傾注していたか手に取るようにわかる。「黒人版エルヴィス」ではなく、エルヴィスが「白人版ロイ・ハミルトン」だったのだ。
ロイ・ハミルトンとエルヴィスは1969年メンフィスのレコーディング・スタジオで邂逅するが、その後まもなく1969年7月20日40歳の若さで死去してしまう。1950年代初期に人気を博したブラックのシンガーとしては、ハミルトン以前にナット・キング・コールやビリー・エクスタインがいたが、ハミルトンは残念ながら彼ら2人ほどの人気を得ることはなかった。
頭に描かれている音像を口で伝える音楽的才能
もう一点、音楽面で言えば、エルヴィスは、楽譜はかけないが、その曲をどのようにするか、頭の中に描かれている。そこで、ここをこうしたい、ブラス・セクションをこういれたい、ここでギターをいれたい、など、ありとあらゆるアレンジを頭でして、それを口でミュージシャンに伝える。これはかのマイケル・ジャクソンも同じだ。
そして、ピアノ、ギターをそこそこプレイする。多くの人は、彼の腰を振る姿と歌で記憶するが、実はレコード面でもエルヴィス本人はプロデューサー/アレンジャーとしてとても優れているのだ。そんな一端もこの映画の中で描かれる。言ってみれば、そうしたアレンジ力、プロデュース力はエルヴィスの総合的な「セルフ・プロデュース」力につながっているわけだ。もちろん、1960年代にはそんな言葉もなかったが。その結果、素晴らしいアレンジの曲が生まれたのだ。これはマイケル・ジャクソンとも似ている。