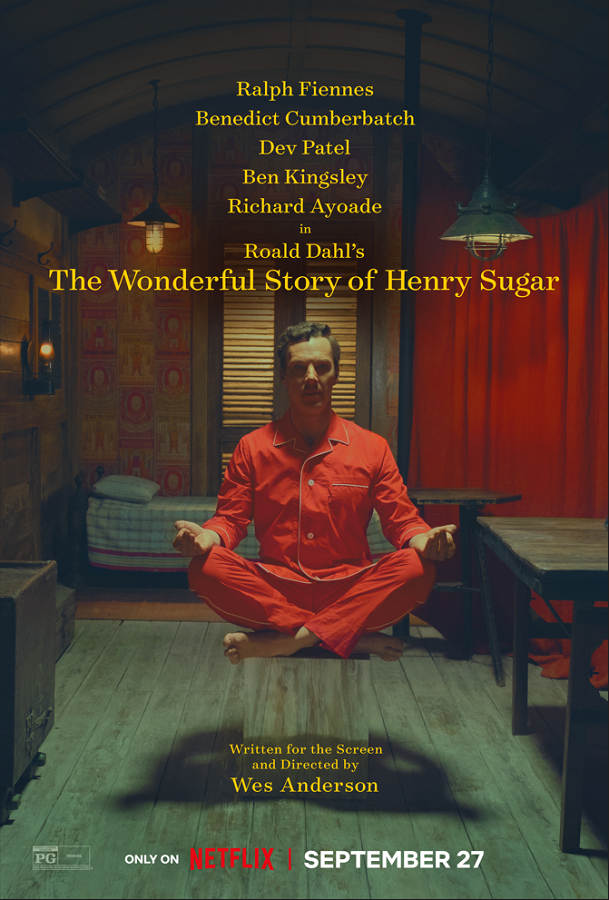パフォーマンスと人生
「マリリン・モンローのスチール写真が興味深いのは、カメラマンが自分の個性やスタイルでどのように撮ったとしても、そこにいるのはいつも彼女でしかないということです」(イヴ・アーノルド / Eve Arnold 「Marilyn Monroe: An Appreciation」)
ミッジとオーギーは、アステロイド・シティのダイナーで出会う。ミッジの娘ダイナもこの町に集められた天才少女の一人だ。横並びのカウンターの端と端に座る距離感が素晴らしい。オーギーはワッフルを食べるミッジとダイナに無許可でシャッターを切り始める。写真家のオーギーが被写体のミッジをとらえる距離感は、『アステロイド・シティ』という映画を豊かにしている。触れられそうなほど近くにいるのに、ミッジはカメラのファインダーやフレームの中にしか存在できないかのようなのだ。そしてミッジはいつも完璧な構図で収まっている。独学で映画スターのポージングを学び、人体の動きに関する本を読み、いわばカメラに関する“研究者”のようだったマリリン・モンローのように。ミッジは、ほとんど無意識のように完璧な構図に収まっていく。そしてミッジのリハーサル(スカーレット・ヨハンソンによる美しいパントマイム演技!)を窓枠越しに手伝うオーギーには、まるでスクリーンに投影されるスターを見ているかのような趣がある。
ミッジ・キャンベルのインスピレーション元となった、マリリン・モンローをとらえたイヴ・アーノルドの写真集には、『荒馬と女』の舞台裏で人生の不完全な問題を生きるマリリン・モンローの孤独と、被写体としてパブリックイメージに生きるマリリン・モンローのペルソナが収められている。『荒馬と女』の一連のスチール写真は、戦場・報道カメラマンとして知られるロバート・キャパたちが創設した写真家集団マグナム・フォトとの専属契約によって撮られたという点で、『アステロイド・シティ』のオーギーのイメージとつながっている。ウェス・アンダーソンの言葉でいうところの「傷つきやすい才能の持ち主」マリリン・モンロー。映画作家ジョナス・メカスは『荒馬と女』のマリリン・モンローを次のような言葉で賞賛している。
「男たちは世界を捨てた。この映画で真実を語り、告発し、裁き、明らかにするのはマリリン・モンローである」「Village Voice」February 9,1961 [MARILYN MONROE AND THE LOVELESS WORLD by Jonas Mekas]
脚本を手掛けた当時の夫アーサー・ミラーがマリリン・モンローの実人生を作り直したのかもしれない。それ以上にマリリン・モンローは、本当の自分をこの映画に曝け出したのかもしれない。『荒馬と女』は、マリリン・モンローにとって事実上最後の作品となってしまう。

ウェス・アンダーソンは『フレンチ・ディスパッチ』でレア・セドゥのイメージにフランス映画への愛を捧げたように、ミッジ・キャンベル=スカーレット・ヨハンソンのイメージに50年代アメリカ映画への愛を捧げている。ミッジはオーギーに演技と人生に関する弱音を漏らす。「演じたことはあるけど、経験がないの」。そして劇作家による物語を演じる俳優と俳優の実人生が入れ子状に描かれる『アステロイド・シティ』は、演技と人生、芸術と人生に関する映画だ。
自身の体験の中からエモーションを引き出すことや徹底的なリサーチによってキャラクターの内面と同化することをアクターズスタジオはメソッド演技法で唱えている。劇中劇に配役された俳優たちには、「演技は人生(経験)を超えていくものなのか?」という問いがある。または、生まれる時代を間違えたのかもしれないという疑念。あるいは、すべてに間に合わなかったと感じるときの無力感。演技と人生はすれ違いを続ける。感情が後から追いつくこともある。しかし追いついたときには、もう手遅れになっているかもしれない。私たちの人生と同じように。トム・ハンクスの演じるスタンリーは言う。「タイミングは悪いものだ」。そう、多くの場合、人生のタイミングは合わない。