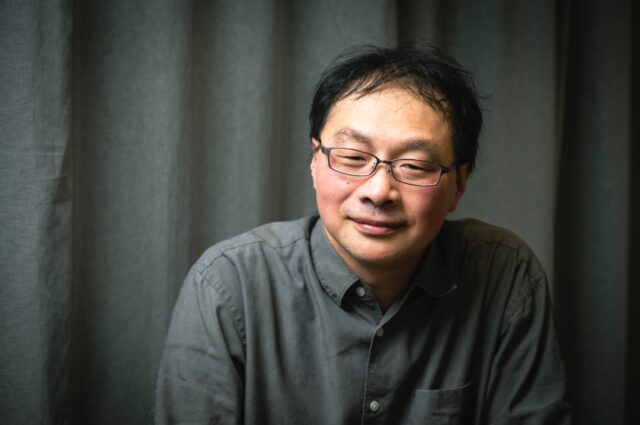「マーロン・ブランドに会いたい」「海外のインターナショナルな映画業界で働きたい」。映画館のない大分県の田舎から、そんな夢だけを頼りに、伝手もなく単身ローマの映画学校へ、さらに激動のヨーロッパで、未婚の母として子育てをしながら、アカデミー賞受賞作を含む数々の名作・話題作を手掛け、今なお国際的に活躍する日本人女性プロデューサーのパイオニアである吉崎道代氏が、この度、自身の半生と手掛けた映画や監督との交流、そして映画への尽きない思いを1冊の本にまとめた。
予告編制作会社バカ・ザ・バッカ代表の池ノ辺直子が映画大好きな業界の人たちと語り合う『映画は愛よ!』、今回は、『嵐を呼ぶ女〜アカデミー賞を獲った日本人女性映画プロデューサー、愛と闘いの記録』を上梓された吉崎道代さんに、ご自身の半生、映画への想いなどをうかがいました。


映画との出会い
池ノ辺 吉崎道代さんは、1975年に、日本ヘラルド映画に入られて、20年ほど、ディストリビューターとして主に欧州映画の日本配給権の買付に携わってこられました。さらに92年にはご自身で映画製作会社を立ち上げ、今度はプロデューサーとして活躍されています。
そもそも、どうして映画業界の道に入られたんですか?
吉崎 うちの父は教員で、母もごく普通の主婦ですから、どうして私が映画好きになったのか、自分でもわからないんです。大分県の田舎に生まれ育ち、最初に心惹かれたのが紙芝居です。小学生の頃になると、『類猿人ターザン』(1932)を観て、主演のワイズミュラーに憧れ、近くの山をジャングルに見立て、ターザンと猿と自分が出てくる物語を頭の中で作ったりしてました。
その後、10代の私が崇拝していたのがマーロン・ブランドです。『欲望という名の電車』(1951)を観て衝撃を受けて、マーロン・ブランドに会いたいという思いが強くなっていました。そして、海外に行きたい、インターナショナルな映画界の、その土俵の片隅にでも足が入ればいいと、思ったんです。

池ノ辺 マーロン・ブランドに会うためには、普通はアメリカですが、吉崎さんはイタリアに留学されたんですよね。
吉崎 そこが私の変わったところで、マーロン・ブランドに惹かれる一方で、『自転車泥棒』(1948)や『無防備都市』(1945)などのイタリア映画に深く感銘を受けていたんです。そこに描かれているイタリア人の生活が、日本の戦後の状況に似ていると母に言われたのも影響したのかもしれませんね。それでイタリアで映画を学びたいと。結果的には、その選択は正解だったと思ってます。

池ノ辺 それで高校卒業後、一人でイタリアに行くって、すごく勇気がいることだと思いますけど。
吉崎 とにかく、行きたいという思いだけは強かったので、あとはどうやって父を説得するかでした。うちは7人兄弟で教育費も大変でしたから、とにかく毎日毎日、頼み込みました。自分は結婚はしないだろうから、その結婚資金を留学費用として使わせてくれと。後で利子をつけて返すからと言って1年間かけて説得したんです。
池ノ辺 それでお父様が折れた。
吉崎 ちょうど何かで不意にお金が入ったみたいで許してくれたんです。
池ノ辺 お金は返したんですか?
吉崎 いいえ。それはまあ、人に資金を出させる、私のプロデューサーとしての腕ということで(笑)。
池ノ辺 それでイタリアの映画学校に入学したんですね。あちらで勉強して、日本に戻ってこられたわけですが、あの頃の映画業界は、特に女性にとってはなかなか入れない狭き門でしたよね。