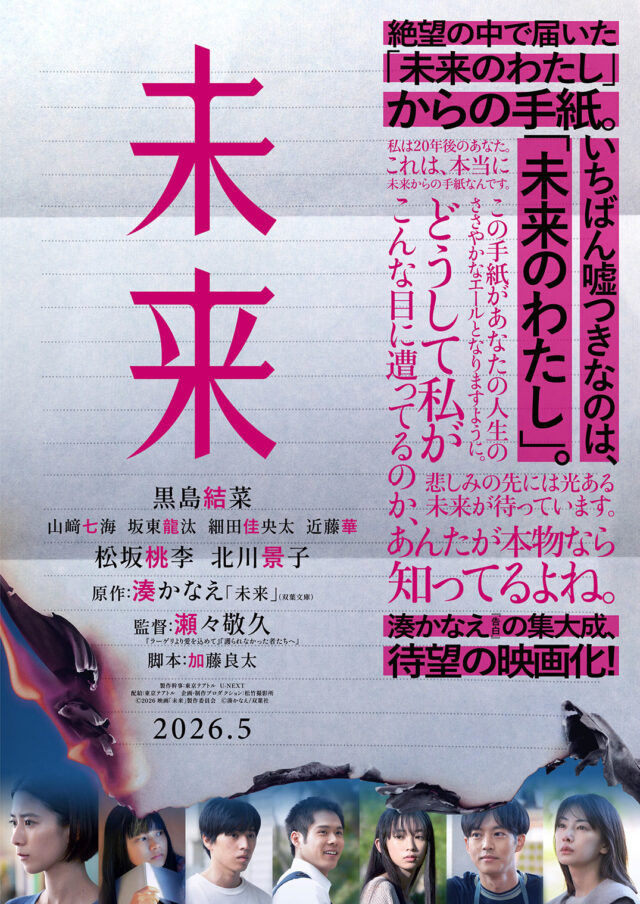誘拐された女児と誘拐犯。15年後、2人は再会する。1人は被害者として今も好奇の目にさらされながら社会の片隅でひっそり生き、もう1人は社会の目を逃れるように気配を消し、静かに生きている。『悪人』『怒り』など、画一的な社会に一石を投じ続けてきた李相日監督 待望の最新作『流浪の月』の見どころに迫る。

『流浪の月』と「ストックホルム症候群」
誘拐事件、あるいは監禁事件が題材となる映画に、「ストックホルム症候群」が持ち出される例は少なくない。1973年、ストックホルムの銀行に押し入った強盗犯による立てこもり事件は、人質の一部が犯人に協力的な姿勢を見せ、解放後も犯人を擁護する被害者がいた。翌年に起きた「パトリシア・ハースト事件」(『市民ケーン』のモデルとなったメディア王、ウィリアム・ランドルフ・ハーストの孫娘が誘拐され、犯人グループと共に銀行襲撃に実行犯として参加)の裁判時に、弁護士は彼女が洗脳されてストックホルム症候群に苦しんでいるのだと主張したあたりから、この言葉は加害者に同調、同情を述べる被害者に使用されるようになった。
『流浪の月』で描かれる15年前の女児誘拐事件も、そうした症例と合致するように見える。大学生の佐伯文(松坂桃李)は、10歳の家内更紗(白鳥玉季)を自宅に連れ帰り、数日を共に過ごす。父が死に、母が家を出た後、伯母に引き取られて窮屈な生活を送る更紗にとって、公園で声をかけられた文に何の警戒もなくついていったのは、こうした事情があったからである。そんな更紗にとって、文と過ごした時間は、何者にも束縛されない自由が横溢した日々だった。

しかし、ちょっと待ってほしい。少女がどんな境遇であろうと――ましてや、救けを求めたわけでもないのに見知らぬ男子大学生が保護者に無断で自宅へ連れ帰れば、当然、責任を問われることになる上に、何らかの目的があったと見るのが自然だろう。幸い乱暴されることもなく、自宅に居るよりも伸び伸びとした時間を過ごすことが出来たと更紗は主張するが、それは結果に過ぎない。
更紗が行方不明になったことは、やがてニュースでも報じられるようになる。テレビを眺めながら「私、帰ろうか?」と文の立場を慮る更紗に、「帰りたいなら、いつでも帰って良いよ」と、その選択権は更紗にあるのだと文は告げる。こうして、更紗はそこに滞在することを〈自らの意志で〉決定する。そして、もはや遠慮なく物を言える仲となり、「ロリコンって辛い?」という核心に迫る質問もするが、文は「ロリコンじゃなくても、人生はつらいことだらけだよ」とだけ答える。
終局は突然訪れる。湖へ2人で行楽に来ていたところを、いつの間にか警官に囲まれ、桟橋に追いつめられる。しっかりと手を握りあった2人を、警官たちが引き離す。更紗は泣き叫びながら、文の名前を呼ぶ。

なぜ誘拐犯に「好意」を持つのか
この出来事を、「ストックホルム症候群」に当てはめるのは容易い。この言葉を生んだ精神科医のニールス・ベジェロットの定義を噛み砕いて説明すれば――死に直結するような脅威を前にした被害者が、食と排泄の自由を奪われることで幼児化する。加害者から食べ物を与えられる、トイレへ行く自由を与えられるという〈好意〉に対して、過度の感謝を抱くようになるのだ。
この説に従えば、更紗は連れ去られるとき、命の危険に陥ることも感じたはずだ。しかし、それでも今の暮らしよりもマシかもしれないという可能性に賭けて行動を共にしたと思われる。しかし、いざ文の部屋で暮らし始めると、晩ごはんにアイスクリームを食べたいと言えば用意してくれるし、ケチャップを大量にかけたいと言っても、ピザを食べたいと言っても咎められることはない。それに、拘束していながら、「帰りたいなら、いつでも帰って良い」と自由であるかのような幻影を持たせてもいる。更紗が文に好意を持つだけの条件は揃っていると言えるだろう。
こうして見ていくと、典型的な「ストックホルム症候群」だと思いそうになるが、近年は安易にこの言葉が使用されすぎているという批判もある。加害者に迎合したと被害者の精神的な弱さを責めるような論調もあるからだ。今ではこうした行動は、むしろ生存のための合理的な判断なのだという視点もある。では、『流浪の月』で描かれた誘拐事件は、どう判断すべきなのだろうか。