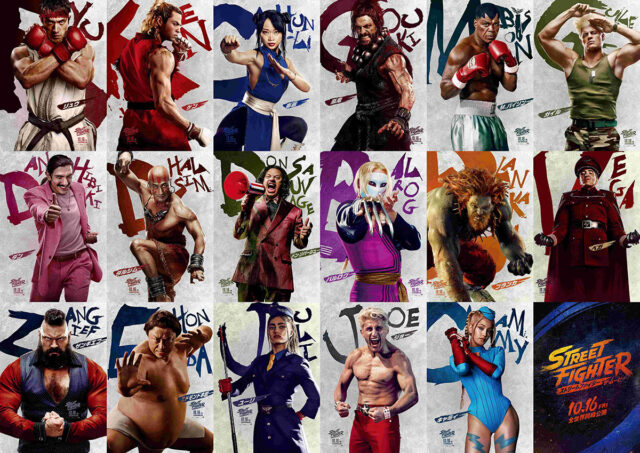SNSの発達で変わった、世間の事件への反応
――我々観客はテレビでは描けない凶悪犯罪事件を扱った作品に興味を持ち、劇場へと足を運んでしまいます。瀬々監督はピンク映画時代から、実在の事件に触発された『黒い下着の女 雷魚』(97年)、『汚れた女(マリア)』(98年)、『HYSTERIC』(00年)などを撮ってきました。映画を作る側も観る側も、人はなぜ犯罪映画に惹かれるのでしょうか?
僕が90年代に撮っていた犯罪映画は、アパートの隣人はもしかしたら殺人犯かもしれないという恐怖心がもとになっていました。2008年~09年にかけて撮影した『ヘヴンズ ストーリー』のころには、もし自分の妻や子どもが殺されたらどうするか、逆に自分の家族が罪を犯した立場だったらどうするか、という事件に対する“当事者性”がテーマになってきました。時代によって、事件と社会との関係性は変わってくるんです。それがここ最近、また大きく変わってきた。SNSの発達も影響しているように僕は思います。事件が起きると、SNS上でみんな一斉に責めるわけです。罪を犯すような人間は、もともとそういう資質の人間だったと、容疑者をパージする。法を犯す者は信用できない、社会から除外すべき存在だと決めつけます。ようやく、当事者性を受け止める人たちが現れる時代になってきたのに、逆に自分にはまったく関係のない他人事として事件を捉える風潮になってしまった。ヤバい時代だと思います。日本社会が右傾化してきていることと通じるものを感じています。事件に対する世間の反応には、社会状況がリアルに浮かび上がっているんじゃないですか。

――瀬々監督が『ヘヴンズ ストーリー』や『友罪』など凶悪犯罪をモチーフにした映画を撮り続けているのは、人間のディープな部分も描きたいという気持ちもあるんでしょうか?
そこに謎があるからでしょうね。最近も埼玉県で小学4年生の男の子がメーターボックスで死体となって発見され、義父が逮捕されるという痛ましい事件がありました。なんでそんな酷い事件が起きるんだと思うわけですが、そこには謎も多いわけです。「どうして人は人を好きになるんだろう」という謎があるのと同時に「どうして人は人を憎むのだろう」という謎もあるわけです。そこには人間の剥き出しの感情が現れているように僕は思うんです。そこを観たい、映画として撮りたいという気持ちがあるんでしょうね。

――米国の作家トルーマン・カポーティは獄中の連続殺人犯を取材し、ノンフィクション小説『冷血』を発表しましたが、殺人犯の心の闇に近づきすぎ、その後は長編小説を書けなくなったともいわれています。瀬々監督はそのような心境になることはありませんか?
僕が犯罪映画をいまも撮り続けているということは、事件に対する向き合い方がカポーティに比べて甘いということかな…。
――いえ、瀬々監督が撮った犯罪映画をディスる気はありません。危険な心の闇に対して、不容易には近づかないように気をつけているんじゃないですか。
それはあるかもしれません。例えば、今回の『楽園』だと善次郎(佐藤浩市)は村八分にされ、精神的に追い詰められていく。善次郎が犯行に及ぶシーンを映像化することも考えられたわけですが、でもそこは監督である僕は観たくなかったし、撮りたいとも思わなかった。人間の持つ狂気そのものではなく、狂気に満ちた事件を生み出した状況、因果律みたいなもののほうに僕は興味があるんでしょうね。もちろん、凶悪事件を起こすには一線を越える何かがあるわけで、そこにはある種の狂気性があるとは思います。でも、今回の『楽園』では、そこを描こうという気にはなれなかったんです。