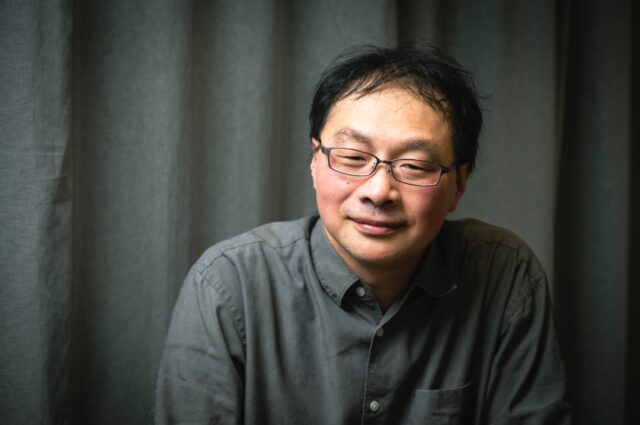伊江島で撮ること、本物のガジュマルの上で撮ることの意味
池ノ辺 この作品では、脚本からの参加ですね。
平 舞台版では、木に登ったところから降りるまでの2年間を描いています。まず、映画で同じように2時間をずっと木の上の映像とするのは難しいと思いました。この二人が木の上で、何を守ろうとして、どういう葛藤があって、なぜ降りられないのか、そこに説得力を持たせるためには、木に登るまでの背景を描く必要があると思ったんです。

池ノ辺 実話がベースだそうですが、実際に彼らはガジュマルの木の上で生活していたそうですね。ある意味では、実話自体がとてつもない壮絶なお話ですよね。
平 映画というのはフィクションです。ですが、それがどれだけ荒唐無稽なものであっても、その中に「事実」というものがベースにあれば、そこは安心できる、信頼できると思ったんです。木の上で兵士として2年間過ごしたという事実を映画を観る人が知らなかったとしても、確固たるリアリティを持たせることができると思いました。この二人の兵士の話が、伊江島で事実として言い伝えられていることが、何とも不思議な説得力をこの映画にもたらしてくれて、それは僕にとって、すごく安心材料になりました。

池ノ辺 撮影にあたってガジュマルの木を準備された時に、大変なことが起きたと聞きました。
平 まず、僕らが決めていたことは、この映画は実際に激戦があった場所であり、二人が暮らしていた場所である伊江島で撮らなければならないということです。ガジュマルも、本物のガジュマルの木の上で撮りたいと思ったんです。それで本物の木を、ロケ地となる公園に植樹することになったんですが、別の場所にあったガジュマルの木を、公園に植える前に、一旦別の場所に移す必要が出ました。その土地に穴を掘った時、ひと掘り目で戦時中の遺骨が出てきたんです。結果的に全部で20体の遺骨が出てきました。
池ノ辺 それはびっくり。驚きますよね。
平 最初は怖かったです。怖かったし、かわいそうだなとも思いました。でも次第に、ああ見つかってよかったなとも思いました。
池ノ辺 見つけられるのを待っていたのかもしれないですね。
平 たとえば自分の家の庭で、死体が20体出てきたとなればたぶん怖いだけで終わったと思います。逆に、隣とか離れたところで遺骨が出てきたら、ご先祖様に会えてよかったねとなるかもしれない。最初にもお話したように、僕はこれまで、沖縄戦に対して向き合ってこなかった。僕の中で当事者意識もなかったですし、僕の両親も戦争を知らない世代です。だから80年前の戦争に対しても、昔のおとぎ話のような、どこか対岸の火事で、自分には無縁の、他人事のような距離感があったんです。僕は、この2年間のさまざまな取材や調査を通して、自分の意識が、それまでの対岸の火事の意識と全く違うものに変わっていたことに気づいたんです。考えてみれば、たった80年前ですから、その時に銃弾を喰らった人たちもまだ生きている。小学生の頃、おじいさんやおばあさんが、学校に来て当時の話をしてくれたことを思い出しました。涙ながらに語ってくれたあの証言は、普通に殺人事件の被害者であり、さらにいうなら加害者かもしれない、そういう人たちが、死ぬ気で勇気を振り絞って話してくれたんだということに、改めて気づかされました。
池ノ辺 今回の話がなければずっと気づかずにいたかもしれませんね。
平 この映画を撮るにあたって、僕は二人の価値観に近づくための努力をして取材しました。彼らの価値観に近づくということは、自分にとって戦争が身近になるということでもあったんです。