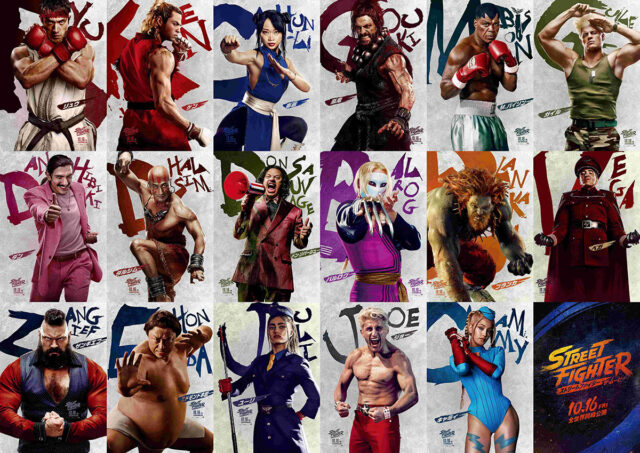──2009年に、和歌山県太地町のイルカ漁を取材したアメリカ映画『ザ・コーヴ』が世界中で公開されます。同年に米国アカデミー賞の長編ドキュメンタリー映画賞も受賞しています。『ザ・コーヴ』をご覧になったときの感想を教えてください。
その年の夏に『ザ・コーヴ』が公開されたときにニューヨークで観て、衝撃を受けました。よくできた映画なのですが、冷静に考えてみると「イルカ漁は良くない」「太地町の漁師たちは悪者だ」ということが前提になっていた。結論ありきで、そこにむかって独善的に作りこんでいっている。ドキュメンタリー映画は既存のメディアにできないことができ、武器にもなります。たとえば、権力を使って悪いことをしている人たちにカメラを向けるとか。しかし、そのカメラを向けた先が、日本の小さな漁村の漁師さんたちということは、力関係からいっていじめに近い。そのようなやり方に腹が立ちました。10年に『ハーブ&ドロシー』の日本公開が決まったので、その準備のために日本へ戻ってきたので、仕事の合間をぬって太地町へ取材にいきました。

(C)「おクジラさま」プロジェクトチーム
──『おクジラさま』は20回近く現地で撮影したということですが、スタートした時期の現場の雰囲気についてお話ください。
太地町での最初の撮影は、2010年9月1日でした。イルカ漁の解禁日でした。その後、10月10日に太地町の飛鳥神社で秋祭りがあるので、それを撮りに戻りました。翌日の早朝、漁師さんたちの出漁風景を港で撮った後に畠尻湾に行ってみたら、ちょうどシーシェパードが来たのでインタビューをしました。そうしたら、彼らが質問に答えている背後に、イルカたちが湾に追いこまれてくる姿が映りこんだきたのです。
シーシェパードの人たちが騒ぎはじめ、情報を発信し、周囲にいた外国人たちが集まってきました。さらに日本のマスコミ、警察、海上保安庁、右翼の街宣車まで来ました。映画に出てくる、大阪で教師をしているスティーヴンがプロテスト行動として海に飛びこむ場面も、その日のできごとです。「追い込み漁をされている20数頭のハナゴンドウを逃がすために、漁師たちにいくら払えばいいのか」とシーシェパードが交渉する場面も同じ日。その日は結局、20時間くらいカメラを回しっぱなし。目前で次々と事件が起きて、さまざまなモチーフが花開いていきました。ドキュメンタリーを撮ることの醍醐味を味わった一日でしたね。

(C)「おクジラさま」プロジェクトチーム
──登場人物のなかでは、ジャーナリストのジェイ・アラバスターの視点が秀逸です。彼は反捕鯨団体の外国人たちとはちがい、太地町の伝統的な食文化やイルカの追い込み漁を理解しようとして、漁師や町民から徐々に受け入れられていく。
10年に太地町で撮影を始めましたが、その後、東日本大震災の混乱があって撮影をいったん中断しました。14年に太地町に戻ったとき、ジェイがすでに住んでいて意気投合したんですね。ジェイはアメリカ人でありながら日本に長く住んでいて、わたしは日本人でありながらアメリカに長く住んでいる。外国から太地町の問題を見ている、ふたりの考えが一致したのです。『おクジラさま』のなかで、ジェイは主人公というよりは案内役というか、彼の視点にそって観客が物語のなかに入り、共感を持つことができるようにしています。その役割を日本人のわたしではなく、アメリカ人の彼が担ってくれたので、物語としても深みが出たのではないかと思います。