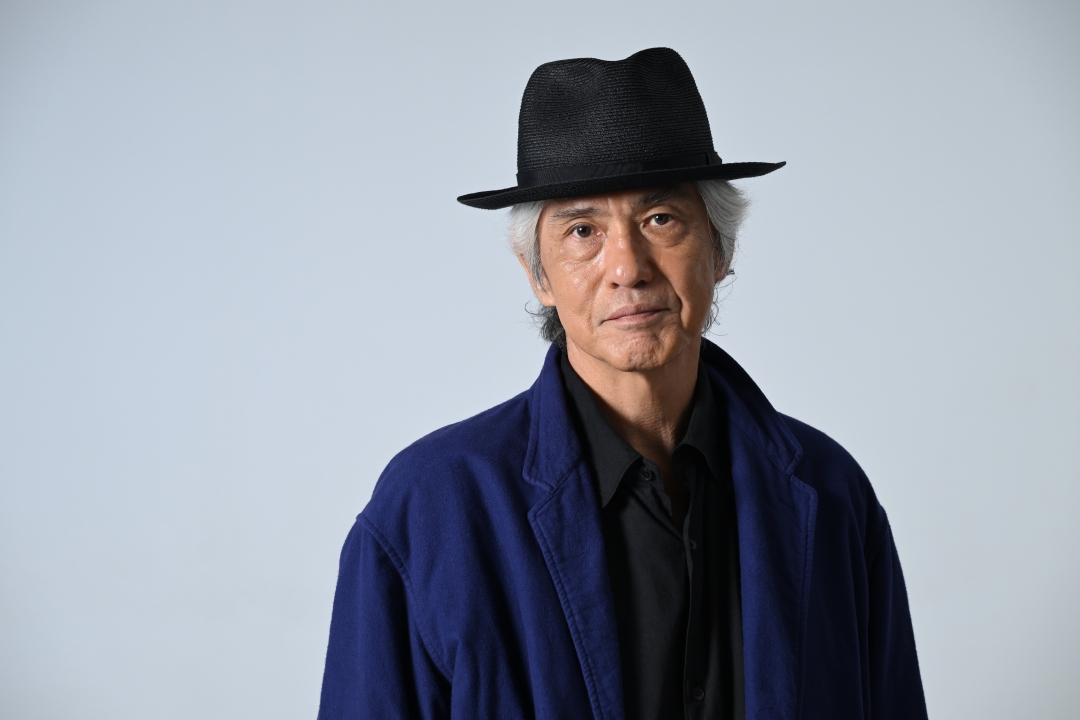――佐藤浩市さんは下の世代の俳優さん達との共演も非常に多いと思います。俳優をやっていきたい人にアドバイスをするとしたら何と言いますか。
どうかな。凄く二極化していると思うんですよね。何か貪欲に前の事も知りたいと思っている俳優さんと今と先ばかり見ていて、あまり前のことに興味を持っていない俳優、良い悪いではなくて、そんな風に二極化している気がします。何人かいる前者の人は「佐藤さん教えて下さい。こういう時はどうだったのですか」と聞いてくるんです。「そんなことにまで興味があるんだ」と驚かされることもあります。
個人的に思うのは、貪欲に先代達の話を聞く姿勢ってやっぱり嬉しいです。今でいうと継承とか伝承というのは、ちょっとネガティブな受け取り方をする人達も居るかもしれません。でも、決して損にはならないから。まして【演じる】ということを生業としている以上は、役者は過去の時代を演じなければならない場合もあるんです。それであるならば、それをしっかり知ることは無駄ではないと思うんです。
――俳優として継承したいことはありますか。
どうだろう‥‥ あんまり、それはないかな。僕らの時代は、やっぱり昔のことに興味があった。ちょっと古い映画を観てみたりして、そこから得られるものが案外あって、率先してやっていました。それは継承とは言わないけど、その中で自分が役を掴んでいくこともあったから。古い映画をよく観ていましたよ。
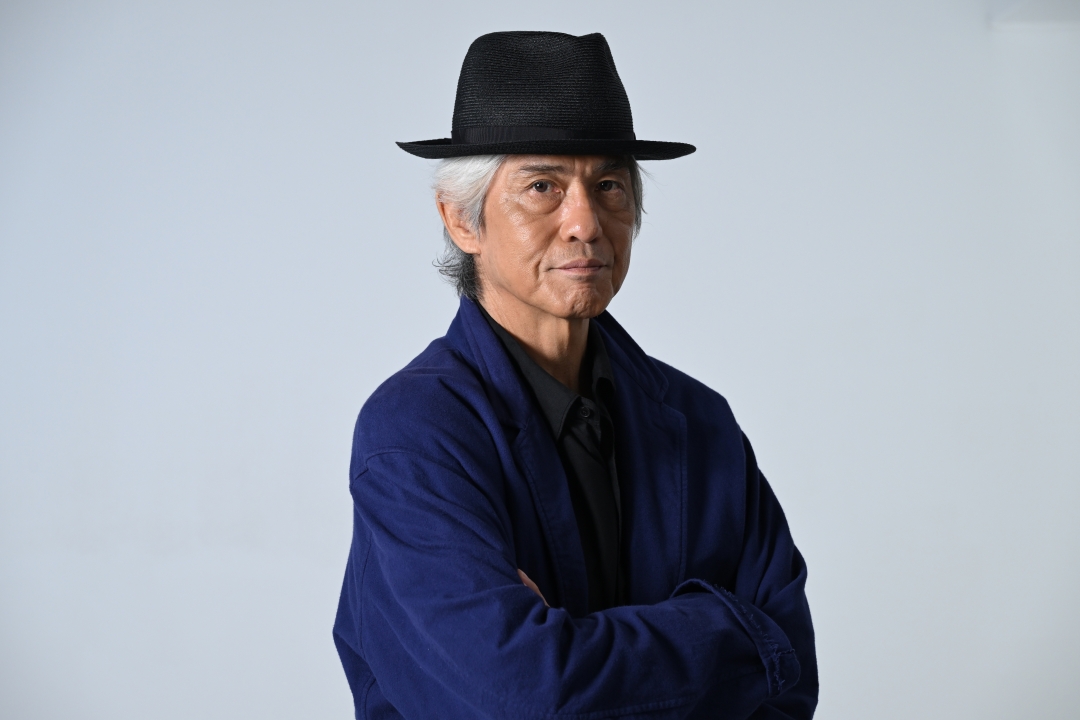
――難しいですね。佐藤浩市さんが若い頃は、クセの強い先輩俳優さん達が沢山いらっしゃいましたが、「この人は凄い」と衝撃を受けた、良い意味で刺激を貰った俳優さんはいらっしゃいますか。
緒形拳さん。緒方さんは貪欲でした。相米慎二監督の『魚影の群れ』(1983) という作品で数ヶ月ご一緒したのですが、緒方さんは、ガスも電気もないロケセットの漁師小屋にずっと住まわれて、風呂だけ入りに旅館に来られていたんです。それが良いとか悪いとかではなく、経験することで漁師としての流れを彼の中で掴みたかったのだと思います。撮影が終わって、京都で井筒和幸監督の『犬死にせしもの』(1986) という作品の撮影を真田広之とやっている時に緒方さんと偶然お会いしたんです。しかもすれ違いざまに「面白そうなものやっているな、お前」って言われたんです。それは本音としてきっと言った言葉で、その言葉を聞いた時に、“この人は本当に貪欲な方だな”と感動しました。芝居を面白がりたい、芝居を楽しみたいと思っていらっしゃる先輩でした。遊ぶという言い方は変かもしれませんが、「遊びたい」という考え方が根底にある方々が、当時は沢山いらっしゃいました。
――ギラギラしている演技がカッコ良かったですよね。ちなみに佐藤浩市さんは、奥様 (佐藤亜矢子) と一緒に「フレンドホーム (週末里親) 」など子どもに対する活動もされ、児童養護施設の子ども達が出演する映画『花束』(2024)にも出演されています。本当に素晴らしいことだと思います。活動を続けられている気持ちは、どこから来られているのですか。
あれは僕ではなく、女房がしていることです。女房が「やりたい」という気持ちに「いいよ」と、ちょっとだけ背中を支えているだけです。その活動を継続してやっていくことで、そこで知り合った子達 (児童養護施設で育った子達) と繋がっていくのは嬉しいです。しかも『花束』を作ったことで、役者として一緒に演技出来たり。齊藤工くんも彼らのドキュメンタリー映画 (『大きな家』) をプロデュースしていますよね。彼らの存在に気づいて何か自分が出来ることをやる。こういった活動が広がってくれれば嬉しいです。願うのは、児童養護施設出身の子達が普通に地べたを歩く、その姿を周りの人間達もちゃんと受け入れることが日常的に出来る社会になってくれることだけです。