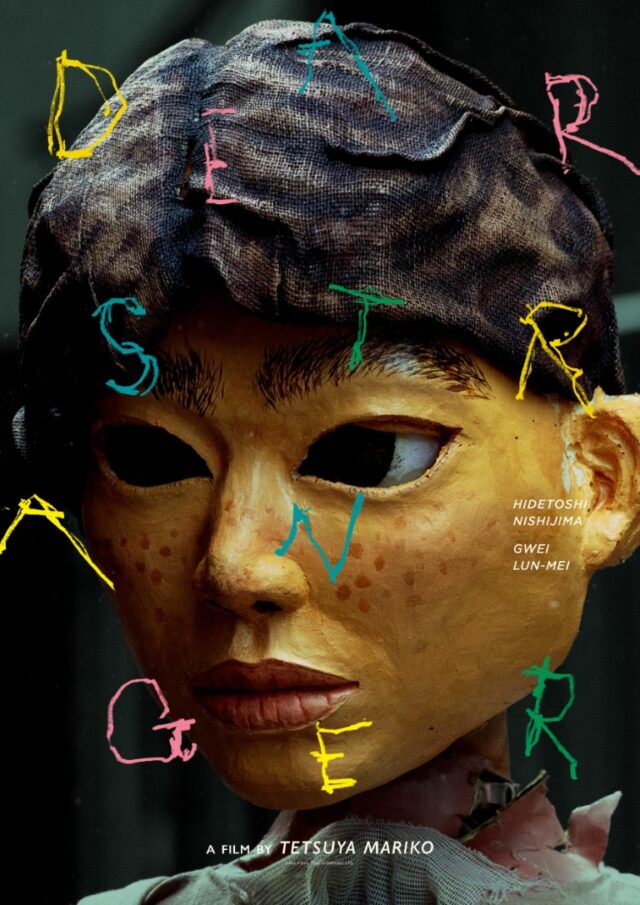戦国版『アウトレイジ』。久しぶりの北野武監督の新作『首』は、いくつもの説があるという本能寺の変にまつわる話を利用して、どこをどう切っても北野武作品としかいいようのない傑作に仕上げている。北野武は本作のインタビューでクエンティン・タランティーノの名前を出しているが、“歴史にもしがあったら”という意味において、タランティーノの『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(2019)に通じるところは確かにある(タランティーノは北野映画支持者でもある)。しかし本作に喜びを覚えるのは、まず第一に日本映画を代表するキャスト陣の素晴らしいパフォーマンスである。後にも先にもいったい誰がこの俳優にこのような役をオファーする/できるのだろう?という驚きの連続だ。キャスト陣は見事に期待に応えるばかりか、楽しんでいるのが伝わってくる。
一部では映画監督引退作品になるのではないか?とも噂された本作だが、北野武は既に次回作を準備しているという。新作『首』は日本映画界に、いや世界の映画界に北野武という映画作家がいることを心から喜びたくなる傑作だ。作家映画として始まり、『アウトレイジ』シリーズのようなエンタメ作品も何一つ美学を崩さずに成功に導いた映画作家 北野武。『首』にはこの映画作家がまだまだ進化・深化を遂げている刻印が見てとれる。北野武は何一つ無邪気さを失っていない。筆者は本作を2023年の日本映画ベスト1に推す。
俳優主義の映画
暴力に次ぐ暴力によって当世の最高権力者であることを誇示する血色の悪い織田信長(加瀬亮)。狂人織田信長に容赦なくボコボコに暴力を振るわれる明智光秀(西島秀俊)。直情突進型の農民(中村獅童)は、サムライになるために手段を択ばない。北野武監督による『首』は、まず第一に俳優の能力、新たな可能性を最大限に引き出すことに成功している。まったくもって役者冥利に尽きる。いったい他の誰が「ハゲ!」と罵倒され、足蹴りを食らう西島秀俊を撮ろうと思うだろうか?加瀬亮、西島秀俊、浅野忠信‥‥。現在の日本映画界の顔ともいえる俳優たちが、全員心の底から演技を楽しんでいるのが伝わってくる。このようなキャスティングを北野武以外の映画作家がするとも思えない。“斬首”というどこからどう見ても血生臭い題材が中心にあるにも関わらず、本作には普段演じることのない役を演じる俳優たちの幸福感が溢れ出ている。

武将たちが織田信長の元に集う会合で、早速織田信長の暴君ぶりは披露される。ここでの加瀬亮は、自身が演じた『アウトレイジ』シリーズにおける石原を想起させる(特に裏切りにより山王会の若頭に出世した『アウトレイジ・ビヨンド』)。石原もまた自身の権力が脅かされるのを恐れている男だった。北野武の映画において登場人物の多くは、いつ殺されるか分からない状況に身を置いている。織田信長は尾張のお国言葉でひたすらわめき散らす。興奮状態で繰り出される戯画化と紙一重な織田信長=加瀬亮の言葉は、武将たち、そして私たちオーディエンスに恐怖を植え付ける一方で、人を魅了するリズム感に溢れている。織田信長による暴力的な身振り、発話のリズム、そして歌舞伎者のような独特な衣装には、絶対的なカリスマ性の誇示や支配への執着の温度だけでなく、彼の怯えさえもが含まれている。北野武の映画における静と動の関係。恐怖政治を敷きトランス状態でわめき散らすからこそ、織田信長が黙して馬に乗る大名行列のシーンでは、その異様な静けさの中に彼の怖さが滲んでいる。血を吸いつくすヴァンパイアのような織田信長=加瀬亮!

北野武の映画は暴力描写の多彩なアイディアもさることながら、特に『アウトレイジ』シリーズにおける台詞の語尾、「なんだコノヤロー!」のリズム感のよさが恐怖のグルーヴ感を生み出している。たとえば『アウトレイジ』の木村(中野英雄)が、カッターで指詰めを強要されるシーン。指詰めに至る前の俳優たちの凄んだ発話、リズムの組み立て方は、暴力描写と同じくらい危険なものだ。相手を威圧する顔と顔と顔、言葉と言葉と言葉の反復。グルーヴを生み出す組み立ての上に、意表を突いた暴力が待っている。『首』には織田信長が刀の先に刺した饅頭を荒木村重(遠藤憲一)に食べさせるという壮絶なシーンが早速披露されるが、決定的な暴力シーンに至る前の俳優たちによる身振りや発話のリズムこそが恐怖への助走となっている。その意味で近年の北野武の映画は、より俳優主義的な視点に立って映画を組み立てているといえる。皆のイメージする織田信長を織田信長自身が演じているかのような加瀬亮の演技は、圧倒的なカリスマ性を放ちつつ、どこか喜劇のようでさえある。織田信長=加瀬亮は戯画的、ともすれば喜劇的な祝祭空間の中に悪魔的な“儀式”を紛れ込ませていく。笑いながら振るわれる暴力のように。だからこそ恐怖はより一層増していく。