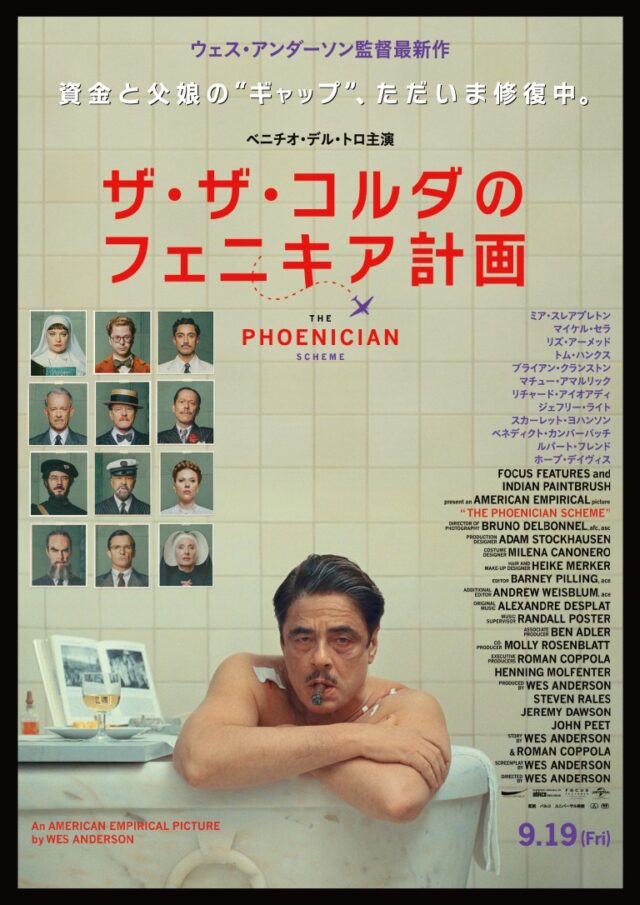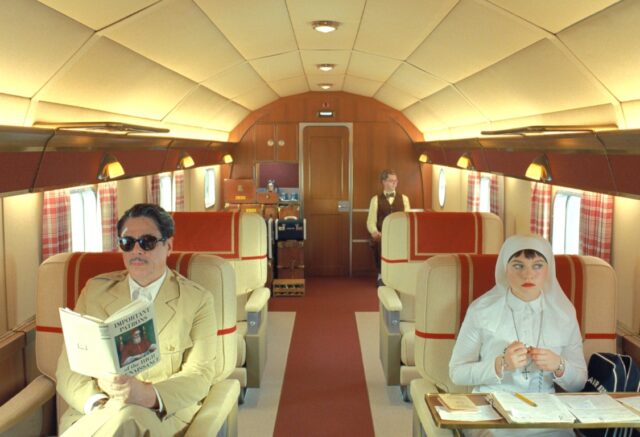ギャレス・エドワーズ監督曰く、「映画史には『ジュラシック・パーク』“以前”と“以後”という分水嶺がある」。すべての登場人物を一新して撮られたジュラシック・シリーズ最新作は、スティーヴン・スピルバーグが撮ったシリーズ第1作にして永遠の金字塔『ジュラシック・パーク』(1993) のスピリットに回帰しつつ、懐古趣味には終わらない新たなエンターテインメントの逸品に仕上がっている。人々は恐竜の巨大さに恐怖を覚え、生命そのものが放つ純粋な美に打ちのめされる。いずれも第1作目が持っていた原始的な映像体験である。では何のための回帰なのか?シリーズ7作目にあたる『ジュラシック・ワールド/復活の大地』は、この一大フランチャイズシリーズが背負っている遺産の歴史に対して自己言及している作品といえる。そこにはこのシリーズ自体が背負っている“繁栄と衰退”というテーマさえ含まれている。本作は“以後”の世界から始まっている。人々が恐竜に夢中だった時代は、既に遠くに過ぎ去っている。栄華は過ぎ去った。いわば“兵どもが夢の跡”の世界だ。『ジュラシック・パーク』のビジュアルエフェクト技術に衝撃を受けたことをきっかけにキャリアをスタートさせたギャレス・エドワーズと、“以後”の世界をサヴァイヴするにふさわしいヒロインを演じるスカーレット・ヨハンソンは、私たち映画ファンの“夢”をフィルムの上に再駆動させようとしている。
夏休み映画を再駆動させる
スティーヴン・スピルバーグは、『ジュラシック・ワールド/復活の大地』の制作中にギャレス・エドワーズへアドバイスしている。「映画を作ることはシェフが料理を作るようなものだ。唯一の違いは、映画館のシェフの場合、観客は空腹で帰らなければならないことだ。もし満腹で帰ったのなら、あなたは失敗したようなものだ」(※) 。観客がもう一度見たいと渇望するような映画。スピルバーグのアドバイスは、自身が手掛けた名作のみならず、80年代~90年代にかけて続々とシリーズ化されたモンスター級ヒット作たちのことを指しているように思える。博物館に勤務している古生物学者のルーミス博士(ジョナサン・ベイリー)は、人々が恐竜に夢中だった時代を懐かしむ。盛況だった博物館は閑古鳥が鳴いている。本作において恐竜、そして博物館は、かつて夏休みに人々を映画館に駆けつけさせたモンスター級ヒット作、映画館そのもののメタファーになっているように思える。
過去10年間の『ジュラシック・ワールド』シリーズでは、人間と恐竜の共存がテーマの主軸に置かれていた。恐竜たちはアミューズメントパークで人間と共存していた。しかし本作から始まる新たなシリーズでは、既に人々は恐竜に飽きている。残された恐竜たちは赤道近くの離島に隔離されている。人間たちは都合のいいことに、恐竜たちのことを忘れたいとさえ思っている。しかし人類の心疾患に効くとされる薬剤を作るため、再び恐竜が必要とされる。都合よく隔離されていた恐竜たちが再び必要とされるという皮肉。『ジュラシック・パーク』と第2作『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』を手掛けた脚本家のデヴィッド・コープは、本作においてシリーズの出発点となったテーマを再考している。「狂気の科学者が神の創造物に手を出すと、その代償を払うことになる」というテーマだ。巨大製薬会社は、白亜紀の陸・海・空の3大恐竜のDNAを採取しようとする。元特殊部隊の工作員で、百戦錬磨の女性戦士のようなゾーラ(スカーレット・ヨハンソン)がその任務に就く。

登場人物は一新されているが、ルーミス博士がシリーズの英雄アラン・グラントの教え子であることに過去シリーズとのつながりがある。そして本作はここ10年の間に作られた『ジュラシック・ワールド』シリーズの方向性を否定しているわけではない。デヴィッド・コープは、人間と恐竜の共存が不可能であると判断された“以後”の世界から物語を始めることで、むしろそのテーマを厳しい視点で深化させようとしている。不要と判断された恐竜たちが再び必要とされるという強烈な皮肉は、巨大生物に出会ったときに恐怖に怯えると同時に生命の美しさに感嘆することのように、流動的な矛盾を抱えている。ルーミス博士が言うように、人類は地球の支配者ではない。私たちは自然の力をコントロールすることができない。かつて恐竜たちが絶滅したように、地球の気紛れで人類が不要とされるときが来るかもしれない。