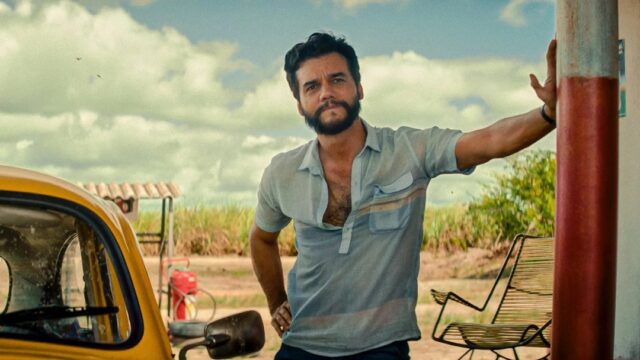第97回アカデミー賞授賞式が行われた。本年度のアカデミー賞にノミネートされた日本人制作者の作品は長編ドキュメンタリー『Black Box Diaries』、短編ドキュメンタリー『Instruments of a Beating Heart』、そして短編アニメーション『あめだま』と、多数の分野で大健闘。各国からの選りすぐられた作品と並んで紹介されたアカデミー賞前の「Oscar Nominee Spotlights」(ノミネートされた映像作家にフォーカスを当てるアカデミー映画博物館のイベント)でも観客が大勢訪れ、映画への関心の高さが見受けられた。3作品とも受賞にはいたらなかったが、3部門それぞれで、受賞した映画は想像を絶する人間の苦悩とその苦しみの中で育まれた希望や友情を映像に託した作品が多く見応えがあった。このコラムでは、上記のアカデミー賞3部門に注目して、一人でも多くの人に観てもらいたいオスカー受賞、そしてノミネート作品を紹介したい。


勇敢な映像作家は受賞スピーチも勇敢 『ノー・アザー・ランド 故郷は他にない』
イスラエル軍によって、自らが生まれた家を破壊され、強制追放を強いられたパレスチナ人青年バーセル・アドラー。2019年から2023年まで、彼が15歳のときから自らの家、故郷の村を守ろうと現状を記録してきた映像は、2023年10月7日のハマスのイスラエル人人質事件の背景を考えさせられる。
この映画は、家を壊された青年バーセルと意気投合したイスラエル人青年、ジャーナリストのユヴァル・アブラハームが4年間にわたって納めた映像を編集し、互いの視点の違いを反映して仕上げた長編ドキュメンタリー。抑圧される側と、抑圧する両国の人間がそれぞれ助け合い、憎しみ合うことなくパレスチナ元住民対イスラエル軍や入植者の理不尽を問い、非人間的行動を訴える。身の危険を顧みない貴重な映像は、住居が破壊された上に、井戸にセメントまで流し込み、その地に住めなくするような壮絶な入植者の行為も映し出し、パレスチナの民の受難を描いている。
舞台挨拶には、バーセルとユヴァル、そしてもう2人、ヨルダン側西岸地区出身の映画監督ハムダーン・バラールと、エルサレムを拠点に活動するラへル・ショールが壇上に上がってオスカー像を手にし、スピーチで国境を超えた連帯感を表していた。バーセルは「2ヶ月前、僕は父になりました。私の娘には僕のような、常に入植者の暴力を恐れるような生活をして欲しくないと心から願っています。」とこの受賞を機に、世界中でパレスチナ人の民族浄化をやめるように呼びかけてほしいと訴え、ユヴァルは「僕たち、パレスチナ人とイスラエル人が共同でこの映画を作りました。共同フィルムメーカーでパレスチナ人のバーゼルは僕の兄弟のようなものです。しかし、ぼくらの環境は平等ではありません。ぼくは市民権のある自由な政権の下にいて、バーゼルはイスラエル軍の管轄下にあり、そのせいで彼は子供のころから抑圧され、家族も身の危険にさらされています。民族間の優越性ではなく、それぞれの人権が認められるべきではないでしょうか?そして、この国、アメリカの外交政策はその道を阻んでいると言わざるを得ません。僕らイスラエル人が本当の意味で自由になるには、パレスチナ人が我々と平等に自由になることが必要です。一刻も早く、私たちはお互いが強調し合う道を切り開く必要があります。」と勇敢に発言し、観客から応援の拍手を浴びていた。


しかし、アカデミー賞でのスピーチを受け、イスラエルの閣僚で文化・スポーツ相のミキ・ゾハル氏は、この映画の受賞に際し、ソーシャルメディアで「イスラエルという国に対してのサボタージュだ。」と投稿。映画業界の最も悲しい瞬間だ、イスラエルのイメージを歪める一方的な語り口を強調することをあえて選択している。と強く批判。アメリカでは未だ正式な配給会社はきまっていないが、自主上映で、インディ映画館Laemmle (レムリー)などで上映されつづけていて、現在、米興収60万ドル弱というドキュメンタリー映画での記録を更新。ノミネートされた映画の中でトップの興収になっており、いかにこの問題の米国民の関心が高いかが窺われる。
アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門では過去2年間、ロシアの独裁者プーチンが最も恐れた男を描いた『ナワリヌイ』、その後のロシア軍によるウクライナ侵攻の悲惨さを捉えた『マリウポリの20日間』が受賞している。今年のウクライナ発信のノミネート映画『ポーセリン・ウォー』も話題作。原題は磁器彫刻家の戦争とでも訳すべきか、ウクライナの田舎で動物や鳥の置物を作っていたウクライナ人彫刻家夫妻が、筆を持つ手で銃を構え、ウクライナという国を守るために、住民レベルで素人が戦いの訓練に挑む。なぜ戦うのか、芸術家の目線で描く戦争の実態を、ウクライナの美しい自然の中で描いたドキュメンタリー。長引くロシア侵攻で明日の命がわからない夫婦は、自らのコミュニティの連帯を強めることに専念し、家族、友人、そして、ヨークシャーテリアの飼い犬と、ガラスのかけらで作る彫刻たちに祈りをこめた愛おしい作品で評価が高かった。
『Black Box Diaries』の伊藤詩織さんも授賞式のレッドカーペットに笑顔で登場。アカデミー賞1週間前のOscar Nominee Spotlightsには英国を拠点にしているカメラマン件プロデューサーのハナ・アクヴィリンさんのみが登場し、詩織さん自らの自殺未遂の言葉をこめた映像など、本人が撮ったことも忘れていたというほど、山ほどある映像を探し出した編集者にプロデューサーは感謝した上で、日本での配給が決まっていない現状を説明。使用した映像の権利問題には触れずに終わったが、欧米での関心は高く、多くの性被害者を奮い立たせる内容になっていたことは間違いない。権利問題を知らなければ、ドキュメンタリー映画としてかなりの説得力のある内容で、これがCCTVの映像なしにどう再編されるのか。伊藤詩織さんが、世の中をよくしたいと精魂込めて制作、アカデミー長編ドキュメンタリー作品ノミネートにこぎつけた作品の意図が伝わり、日本の性被害にかかわる司法関係者も納得する内容で日本でも公開されることを願いたい。